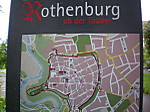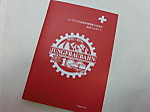ドイツは中欧(昔は東欧と呼ばれていたチェコ、オーストリア、スロバキア、ハンガリーなど)旅行の際に訪問したことがある。その時はベルリンの空港に降り、ベルリン市内を丁寧に見学、マイセン、ドレスデンといった旧東ドイツの諸都市を巡ってチェコのプラハに抜けている。
ベルリン近郊、第二次大戦の際、敗色が決定的になっている日本の戦後処理について話し合われたポツダムは、ただ、横を通過しただけであるし、第二次大戦で徹底的に破壊され、見事復元されて世界遺産に指定されているドイツ最大の大聖堂のあるケルン、メルヘン街道、古城街道、ロマンチック街道なども見ていないし、シンデレラ城のモデル、若きルードビッヒ2世が残した夢の城、ノウシュバンシュタイン城も見ていないし、ライン下りもしていない。
ということで、ドイツ旅行の各社のパンフレットを見比べていた。
ましおばさんは、ドイツは食べ物不味いし、いろいろヨーロッパ行ったけど、スイスだけがぽっかり穴があいていて、スイスの方が先じゃない、と言っている。
と、見残したドイツの主要観光地と、スイス、その両方を巡る上に、小国リヒテンシュタインにも寄るというツアーを発見する。
9日間のツアーで、3カ国をくまなく巡るというわけにはいかないが、見残したドイツと、未知のスイスを巡るということで、予約完了、2回分の旅行費が、1回分で済んだという、何だか得した気分になってくる。
今回も成田に前泊しようと、ホテルの予約を入れていたが、JTBの「泊まるんば」で同じホテルが、予約料金を下回り更に2週間までなら駐車料金も無料という記事を見つけて、そちらに乗り換える。
今回も下道をのんびり走って途中のジョナサンで夕食をいただき、ヤオコーで朝飯を購入してチェックイン、いつもの部屋よりも部屋が広い。
|
 集合時刻が早いので目覚ましを3つもセット。じじとババは、朝早いので、セットした時刻より早く目が覚める。 集合時刻が早いので目覚ましを3つもセット。じじとババは、朝早いので、セットした時刻より早く目が覚める。
7時45分が集合時刻であるが、少し間がある。まずは両替のため銀行へ。ユーロ危機でユーロが安いので、少し余分に調達する。数年前にベルギーとかオランダを巡ったときは1ユーロ170円くらいであったが、今は1ユーロは100円ほど、海外旅行者にとってはまことに有り難い。
今回はスイスにも行くので、スイスフランも必要ということで、日本円で1万円ほど調達する。この金額はかなり少ないような気もするが、今回のツアーは全部の食事が付いているし、何か買いたくなったらカードが使えるし、いざとなれば現地でも両替ができるので、外貨は最小限というのがコツなのだ。
添乗のHさんは集合時刻の30分も前に現れて受付を開始してくれる。手渡された数枚の注意事項は、今回のツアー用に作られたモノで、Hさんオリジナルのものであるが、これを読むだけで優秀な気の利く添乗員であることがわかる。良い添乗員に当たると旅の楽しさが倍増する。今回も良い旅行になりそうな予感がしてくる。
同時に手渡されたルフトハンザのeチケット、今回のツアーではドイツのフラグシップキャリア、ルフトハンザ航空に搭乗する。成田からフランクフルトまで、ミユンヘンから成田までの2回のフライトだけである。乗り換えがない分、楽な日程が組まれている。eチッケトには、それぞれの空港で使用するターミナルの他に、行きの便だけでなく、ミユンヘンからの帰りの便にも座席番号が記載されている。トイレが極めて近いへなおじさん、窓際席に押し込められて、通路にフランス人でも座ろうものなら、ヤツらは、成田で乗って到着地まで、12時間以上一度もトイレに立たないことも多く、地獄となる。今回は幸い通路席の番号が書かれている。
 ルフトハンザはANAのマイレージが貯められるので、窓口でマイレージカードを提示する。念のために座席の変更が可能か確認してみると、ヨーロッパへの主要便でフランクフルトでトランジットの客も多数いるため、本日は満席、従って無理ですと、断られる。
ルフトハンザはANAのマイレージが貯められるので、窓口でマイレージカードを提示する。念のために座席の変更が可能か確認してみると、ヨーロッパへの主要便でフランクフルトでトランジットの客も多数いるため、本日は満席、従って無理ですと、断られる。
ということで、ゴールドカードのラウンジでコーヒーを飲みながら時間をつぶし、Hさんの点呼を改めて受けて出国審査場へ。いつものように、ましおばさんの指紋を機械が読みとれず、時間がかかる。
タバコを購入するとPC用のスピーカーをおまけにくれるという。ちょうど、我が家の小さいPCのスピーカーが壊れているので、おまけ目当てに土産のタバコを2カートン購入する。

我々が搭乗する飛行機はエアバスA380、ボーイングのジャンボを抜いて、史上最大の巨大な航空機である。2階建てで定員は500人を超えている。それがなんと満席なのである。
搭乗すると、最後尾の席で、リクライニングを倒しても後に人がいないので、迷惑をおかけすることがない。ヨーロッパまでの行きの便では眠ることはないが、椅子が倒せるとかなり楽である。
尾翼の上に前方を映すカメラが付いていて、飛行機の背中、主翼、前方のターミナルビルがテレビに映しだされている。
離陸の風景もダイナミックに映しだされて、飛行機ファンには楽しいフライトである。
|
 飛行機はロシア上空を順調に飛行して、定刻通り、現地時刻の午後2時半にフランクフルトに到着する。フランクフルト空港は中央ヨーロッパ最大のハブ空港である。
飛行機はロシア上空を順調に飛行して、定刻通り、現地時刻の午後2時半にフランクフルトに到着する。フランクフルト空港は中央ヨーロッパ最大のハブ空港である。
ホテルは街の中心部分にあって、一日目からかなり立派なホテルである。部屋にエスプレッソをつくる機械が備えられているが、使い方がわからないので、早速ホテルの外にでてみる。
フロントで地図をもらい、コンパスを取りだして方位を確認、歩き出す。iPhoneにはコンパス機能があるが、これを使うとローミングの電波を拾い、1日あたり、2千数百円取られる可能性がある。ということで、オリエンテーリングのときに使用する昔ながらの方位磁石が活躍する。
マイン川に近く、レーマー広場にも近いということで、まずはレーマー広場の入り口に行ってみる。広場には多くの屋台がでている。日本ではあまり見かけないというか、日本ではもっぱら缶詰専用の白いアスパラガスが山積みになっている。今が旬の模様である。今回の旅行は全部の食事が付いているが、アスパラガスが食卓に供されないようなことがあれば、注文してでも食べてみよう。
 ここフランクフルトは、ギリシャ危機や、スペイン、イタリア経済の弱体化で破綻の危機に陥っているユーロ経済を支えるドイツの、というか、ヨーロッパ中央銀行がフランクフルトに設置されているので、ユーロ圏全域の経済を支える中心都市である。
ここフランクフルトは、ギリシャ危機や、スペイン、イタリア経済の弱体化で破綻の危機に陥っているユーロ経済を支えるドイツの、というか、ヨーロッパ中央銀行がフランクフルトに設置されているので、ユーロ圏全域の経済を支える中心都市である。
政治の中心は北部のベルリンであるが、経済の中心がフランクフルト、ヨーロッパ中央銀行だけではなくて、日本の日本銀行にあたるドイツの中央銀行、ドイツ連邦銀行の本店もここに置かれている。
第二次大戦で壊滅的なダメージを受けたが早期に復興が進み、東西冷戦時代には冷え込む東ドイツ経済に対し、好調な西ドイツ経済を支えた都市でもある。
一旦ライン川の支流のひとつ、マイン川に出て遥か新市街地の近代的ビル郡をながめ、旧市街地に向けて「コ」の字型に歩を進める。
レーマー広場の中心部に出ると、ギルドハウスに並んで、旧市庁舎の小豆色のギザギザ屋根が広場に面して立っている。
神聖ローマ帝国の中世にタイムスリップしたような雰囲気の広場に来てみると、まさにヨーロッパにいるという実感が湧いてくる。
大きな銅像があるので近寄っていくと、若きウエルテルの悩み、ファウストなどで知られるドイツの文豪ゲーテの像である。ゲーテはここフランクフルトで生まれたのだ。
 ゲーテハウスと呼ばれる生家がこの近くにあると地図に書いてあるので探してみるが、見あたらない。 ゲーテハウスと呼ばれる生家がこの近くにあると地図に書いてあるので探してみるが、見あたらない。
生まれてから16歳まで過ごしたゲーテの生家も見てみたいが、今回はまあいいか、などといいながら、もう一度マイン川の方に戻り、大聖堂の雄姿を下から見上げてみる。
ヨーロッパのどの都市にもありそうな大聖堂ではあるのだが、中央の塔は95メートルもの高さがあり、由緒がありそうな雰囲気を醸し出している。
中には入れないので外から眺めるしかないのだが、ゴシック様式のドームはカイザードーム(皇帝のドーム)と呼ばれているとのことである。
ヨーロッパ1日目、こんなに観光地に近く、こんなに自由時間があると予想しておらず、地球の歩き方もスイスのものしか持参していない。明らかに準備不足で研究不足である。
結局ゲーテハウスには行き着かず、ホテルに戻って湯を沸かし、成田で購入したおにぎり、パン、みそ汁で夕食とする。ヨーロッパ旅行では飛行機の中で最低2回は食事が出るし、夕食はその機内食で終わりということが大半である。そのため、毎回成田で夕食を買って持ってくることにしているが、今回は特に就寝時刻までかなりの間があり、夕食持参が大成功であったと自画自賛する。ホテルの窓は午後8時というのに明るい。夜が実に長いので、更におなかが空いてくる。
|
 ヨーロッパ2日目の朝の目覚めは早い。日本時間との時差の関係である。朝5時には目覚めて、それ以上は寝られない。
ヨーロッパ2日目の朝の目覚めは早い。日本時間との時差の関係である。朝5時には目覚めて、それ以上は寝られない。
ホテルを出ると同じツアーの仲間と思われるご夫婦に出会う。あちらさんも寝られないのだ。
昨日、白のアスパラガスを並べていた屋台があった広場に行ってみる。あれだけたくさんの屋台はすっかりどこかに行ってしまっていて、ただの広場になっている。
成田で買ってきた国際電話カードを使って、へなおじさん、ましおばさん、それぞれの母親に電話をしてみる。現地の公衆電話からかける国際電話カードを使っての電話が最も安直で最も安価な電話である。もちろん息子や娘には、無料Wi−Fiの利用できる環境からスカイプで連絡すれば無料で顔を見ながらハナシができるが、年寄りにはスカイプというわけにはいかない。今ドイツからと言うと、どちらの母親も「あっ、そう」とそっけない。外国からの電話なのに、あまりにクリアな音声が聞こえるせいもあって、違和感がないのだ。
 一流ホテルだからなのか、ホテルのバイキングの朝食はきわめて美味しい。ドイツの食事もバカにはできない。 一流ホテルだからなのか、ホテルのバイキングの朝食はきわめて美味しい。ドイツの食事もバカにはできない。
8時にホテルを出発、ライン川下りの出発点であるリューデスハイムに向かう。
ここリューデスハイムはドイツワインの産地であり、ドロッセルガッセ、つぐみ横町と呼ばれる有名な路地がある。
今は人通りが少なく、歩いているのは我々外国から来た観光客だけであるが、この上のワイナリーで造られたワインを飲ませる小さなレストランが軒を並べていて、夜は酔客で大賑わいという。
ブドウを象ったエンブレムをくぐって、つぐみ横町の路地の坂道を登っていく。
 案内されたのは小さなワイナリー、試飲をしながらドイツワインを売ります、日本にも発送しますというサービスをしている地下室に降りていく。
案内されたのは小さなワイナリー、試飲をしながらドイツワインを売ります、日本にも発送しますというサービスをしている地下室に降りていく。
アルコールを受け付けないへなおじさん、全く興味なし。皆さんはどれが甘いとか、どれが辛口だとか、忙しそうに試飲を繰り返し、お土産を選んでいる。
ヒマを持て余すましおばさん、甘口のアイスワインとロゼ、貴腐ワインを舐めながら早くも酔っぱらっている。
|
 ライン下りの船への乗船時刻まで間があるので、ここで一旦解散となる。ということで、つぐみ横町のあたりを散策することに。
ライン下りの船への乗船時刻まで間があるので、ここで一旦解散となる。ということで、つぐみ横町のあたりを散策することに。
この街並みを外れると、広大なブドウ畑がどこまでも広がっていて、そこで採取されたブドウでワインを造っているというのが、リューデスハイムなのだ。
ブドウ畑の上にはロープウェイというか、ゴンドラがあって、この街の一角にその乗り場がある。観光用なのか地元の人の移動用なのか、よくわからないが、ほとんど人は乗っていない。
狭い街並みなのに機関車型の観光用の乗り物がのんびり走っている。たくさんの観光客が乗車しているが、日本人は乗っていないようである。
 音楽を自動演奏する機械というか楽器を展示して、実際に演奏もしてくれる博物館がある。いかにも工業国で、しかもバッハ、ブラームス、ベートーベンなどを輩出して音楽にも造詣の深いドイツらしい博物館である。是非演奏を聴いてみたいのであるが、5人以上の観光客が集まらないと入場させないと書いてある。
音楽を自動演奏する機械というか楽器を展示して、実際に演奏もしてくれる博物館がある。いかにも工業国で、しかもバッハ、ブラームス、ベートーベンなどを輩出して音楽にも造詣の深いドイツらしい博物館である。是非演奏を聴いてみたいのであるが、5人以上の観光客が集まらないと入場させないと書いてある。
お土産店の入り口の左右に、色鮮やかな、大きなくるみ割り人形が置いてある。バレエ曲のくるみ割り人形を作曲したのはロシア人のチャイコフスキーであるが、物語の原作者のホフマンがドイツ人なのである。直立不動で律儀なそうなくるみ割り人形、いかにもドイツらしくてカワイイ。
かと言って、クルミを殻のまま入手することは我々都会人には稀であり、くるみ割り人形をお土産にしても使い道がない。
 ということで、ライン川沿いの道までつぐみ横町を降りてくる。ライン川は古代より、ヨーロッパを代表する物流の主要ルートである。そのライン川に沿って鉄道の線路がある。
ということで、ライン川沿いの道までつぐみ横町を降りてくる。ライン川は古代より、ヨーロッパを代表する物流の主要ルートである。そのライン川に沿って鉄道の線路がある。
先ほどから見ていると、結構頻繁に貨物列車が走って行く。列車には、フォルクスワーゲン社が製造する自動車が積載されている。クロネコヤマトなどの配送業者さんが使うような、箱形のワゴンが、100台単位で運ばれていく。オランダのアムステルダムあたりまで運んで、そこからアジアやアフリカに輸出されるのか、あるいはEU内で売られるのか、白のワゴンだけがこれだけ運ばれるというのは、いかにも経済好調なドイツらしい。
|
 リューデスハイムの船着き場に観光客が集まり始める。ドイツ語の他に英語、中国語、フランス語などの会話が聞こえてくる。
リューデスハイムの船着き場に観光客が集まり始める。ドイツ語の他に英語、中国語、フランス語などの会話が聞こえてくる。
今回の旅のハイライトのひとつ、ライン川下りの幕開けである。白の船体に赤いラインが引かれた観光船がやってくる。
我々が乗船するのはここリューデスハイムから少し下流のザンクトゴアハウゼンまでであるが、船にはケルンからコブレンツまで航行すると書いてある。
乗り込むとすぐに船は下流に向けて動き出す。波はないし、流れも極めて緩やかである。
日本からのドイツツアーでは、このライン川下りを、船で行うものと、川岸の道路をバスで行くものがある。どちらも同じような景色であるが船の方が進行が遅くて情緒がある。
 我々のツアーでは更に昼食が船の中でいただけるという日程になっている。 我々のツアーでは更に昼食が船の中でいただけるという日程になっている。
サカナのフライと、ジャガイモのフライ、つまりイギリスのファストフードの定番、フィッシュ&チップスがでてくる。食事が今ひとつという評判のイギリスとドイツ、食事では連携しているのかもしれない。イギリス旅行で食べたフィッシュ&チップスは思いの外美味であったが、ドイツのフィッシュ&チップスの味は果たしてどうか?ムムム、これがまた結構美味いのである。
船の左右の大きな窓から見えるライン川の両岸には、広大なブドウの畑が見えている。
船は集落毎に停まって荷物を降ろしている。地元の方と思われる皆さんも少数であるが乗り降りしている。河岸に住む皆さんの生活の足になっている船の模様である。
 両岸の小高い丘に古城が見え隠れしているが、川の中州にも城ができている。中世の時代、ここに武装した兵を駐屯させ、ライン川を行き来する船から関税を徴収していた城なのである。関税を支払わなければ城から出ている大砲で攻撃するという仕掛けになっている。中世の物流は大変だったのだ。 両岸の小高い丘に古城が見え隠れしているが、川の中州にも城ができている。中世の時代、ここに武装した兵を駐屯させ、ライン川を行き来する船から関税を徴収していた城なのである。関税を支払わなければ城から出ている大砲で攻撃するという仕掛けになっている。中世の物流は大変だったのだ。
コーヒーを注文してのんびり戴きながらのライン川下りは気持ちがいい。
艦内ではドイツ語、英語、フランス語にまじって、日本語での放送もある。右岸に見えるのが何とか城です、と放送しているが、日本語の番になったときにはその城を既に通過してしまっている。ドイツなんだからもう少し厳格に放送してほしいのだが、日本語は付け足し、まあ、既に通過してしまった城でも、日本語で教えてくれるだけで良しとしよう。
|
 ライン下りの船はのんびりとザンクトゴアハウゼンに向かっている。 ライン下りの船はのんびりとザンクトゴアハウゼンに向かっている。
美味しい昼食をいただいて眠気が襲ってくる。両岸にはいかにもヨーロッパらしい可愛らしい家が並んでいるし、大小さまざま、年代もさまざま、レンガや石の色彩もさまざまな城が見え隠れする。
シャガールのステンドグラスのある教会とか、ネズミが悪徳領主を食い殺したという伝説がある塔とか、放送ではいろいろ案内してくれるが、事前の勉強不足で頭には入ってこない。
地図を見ると、そろそろローレライの岩が近づいているはずとデッキにでてみる。子どもの頃に学校で習ったローレライのメロディが浮かんでくる。ハイネの詩を近藤朔風が訳詞した、「なじかは知らねど、心わびて」の有名な歌である。へなおじさんが小節を付けながら歌い出すと、ましおばさんが声が高いとたしなめる。
http://www.youtube.com/watch?v=z-ulZJfb7so
 ライン川は曲がりくねって、川幅が狭くなってくる。船の右舷側に小高い岩山が見えてくる。 ライン川は曲がりくねって、川幅が狭くなってくる。船の右舷側に小高い岩山が見えてくる。
川からわずかに130メートルほどの小山というか、岩の固まりがローレライですと言っている。
世界4大がっかり、マレーシアのマーライオン、ベルギーの小便小僧、デンマークの人魚姫と並んで、世界中の旅人に知られている岩である。
川幅が狭くて曲がりくねり、底も浅くて流れが急、しかも昔は川から岩石が露出して多くの船が座礁したという難所である。そこでこのローレライにたたずむ美少女が船乗りを誘惑し、川底に船を引き込むという伝説が生まれた。
 岩肌にローレライの文字が迫ってきた。今は浚渫されて河床の岩も撤去され、難なく通過できるようになっている。 岩肌にローレライの文字が迫ってきた。今は浚渫されて河床の岩も撤去され、難なく通過できるようになっている。
我が船は船足を落とすこともなく、難なくローレライを通過していく。
ローレライを過ぎるとすぐに目的地のザンクトゴアハウゼンである。
ここで我々を待っていたバスに再び乗り込み、ライン川の横の道路を上流方向に進んでいく。あっというまに午前中に船に乗り込んだリューデスハイムの船着き場を通過する。一体どうなっているんだ?地図で確認してみる。
|
 我々はハイデルベルグに向かってアウトバーンを疾走中である。 我々はハイデルベルグに向かってアウトバーンを疾走中である。
ドイツの交通インフラはヒトラーの時代から整備され、世界の模範になっている。もちろん当初は軍事目的であったのだが、ドイツ経済を支える物流の基礎になっている。
アウトバーンというのは自動車の専用の路という意味のドイツ語である。
無料で速度無制限というのがアウトバーンの売りとされているが、果たしてどうか?まず無料という点をみてみよう。ヨーロッパ特にEU域内はシェンゲン協定が結ばれていて、人も自動車も国境での審査はない。従って自動車道路も国の境がなくて、車はそのまま国境であることを意識せずに通過していく。しかも料金を徴収するようなゲートはほとんど設置されていない。
ということで、ほとんどが無料なのであるが、ドイツ以外の国では有料化が進められていて、日本のようなETCシステムに似た車に装着された特別の装置の情報を読みとり、課金が行われたたり、ヴィネットと呼ばれている高速道路利用券をあらかじめ購入し、それを車のウインドガラスに貼るとかの方法で課金が行われるようになってきている。
へなおじさん、ヨーロッパではレンタカーを借りたことはないが、借りる際にはどの国に行くのか、予め申告し、その国のヴィネットを購入するとか、ところどころにある高速道路のゲートで利用券を購入してフロントガラスに貼るとか、あるいは車に装着されたシステムの情報を返却時に読みとってもらって、料金を支払わなければならない。もちろん料金は日本のように驚くほど高額ではなく、非常に安いとのことである。
ドイツでも大半の車は従来どおり無料であるが、10年ほど前から12t以上の大型トラックだけ、日本のETCに似たシステムで課金が行われている。
それでは制限速度はどうか?トラックはもともと80キロ、バスも100キロという車ごとの制限はあるが、普通の乗用車ではどうだろうか?実際には100キロとか、120キロの制限速度が設定されている道路が多いような感じである。今走っている道路も100キロ制限の標識が見える。
時折120キロ制限になり、更に120キロの標識を打ち消す灰色の斜め線の入った標識が現れる。120キロ制限解除、つまり、無制限の区間に突入したという意味の標識である。速度無制限という道路はドイツ国内のアウトバーンの半分ほどの区間であるという。
日本の新東名は130キロで設計施工された道路であるが、80キロまたは、100キロの速度制限が設定されている。東名の豊田JCTあたりでは何故だか50キロ制限の区間がかなり長く続いている。高速道路が合流したり分岐したりと複雑な流れの区間ではあるのだが、どんな車も100キロ程度で走っていて、制限速度の50キロで走ろうものなら、あっという間に追いつかれて事故を惹起させるおそれもある。
また、一般道でもヨーロッパのどの国でも交通閑散で人家がないような道路では道が狭くても80キロ制限になっていたりすることが多い。一方日本では人家が近いと40キロ、閑散でも50キロ、たまに60キロとお役所仕事丸出しの速度制限である。
誰も守らないような速度制限は、もう少し緩やかにして、リスクはそれぞれが負う、万一人様にご迷惑をかけるようなら、厳しく罰する、ヨーロッパのような制限速度の設定の方が安全のような気がする。それには他人のクルマを煽らない、追い越しは必ず追い越し車線で行う、追い越したらすぐに走行車線に戻って、追い越し車線を占領しないなど、運転マナーの更なる向上が必要である。
アメリカやヨーロッパの旅ではバスに乗せてもらっていても、何故だか心地が良い。それは運転マナーや歩行者の交通マナーの良さが多分に影響している。中国やベトナム、エジプトなどでは、バスに乗っていても右足を思わず突っ張って、ブレーキを踏みたくなる。
|
 我々ツアーご一行様は28人、旅行会社にとっては物足りないかもしれないが、参加者には、ちょうど良い人数のツアーである。添乗のHさんにとっても、目が届きやすい人数である。
我々ツアーご一行様は28人、旅行会社にとっては物足りないかもしれないが、参加者には、ちょうど良い人数のツアーである。添乗のHさんにとっても、目が届きやすい人数である。
ドイツ、スイスのいいところを選んでいろいろ回り、しかも小国リヒテンシュタインにも行くという欲張りコンパクトツアー、そのためか、新婚さんが2組、その他の皆さんも海外旅行初心者の方が多い。ということで、平均年齢が若いツアーになっている。
28人なので、バスの座席もゆったりである。特に今日搭乗しているバスは、後輪のダブルタイヤが2組、つまり後輪が全部で8本もある長大バスで、ゆったりしている。エアサスペンションが効いてアウトバーンの走行も極めてスムーズである。
 ところがアウトバーンを出て山道を登り出す。こうなると長大バスの運転は大変である。ようやく丘の頂上に近い駐車場に到着するも、駐車スペースにバスを収容するのに何度も前進、後退を繰り返す。
ところがアウトバーンを出て山道を登り出す。こうなると長大バスの運転は大変である。ようやく丘の頂上に近い駐車場に到着するも、駐車スペースにバスを収容するのに何度も前進、後退を繰り返す。
到着したハイデルベルグ城、赤煉瓦でできた巨大な廃城である。14世紀のドイツ、皇帝は各地に点在する選帝候による選挙で選出された。選挙で選ぶことができるから選帝候である。このハイデルベルグを支配する貴族というか選帝候は、ブファルツ選帝候、皇帝不在時には皇帝の代理を務め、貨幣の鋳造権ももつドイツ最大の権力者であった。
17世紀の後半、ブファルツ候の継承を巡って戦争が勃発、ルイ14世、あのベルサイユ宮殿を建造したフランス皇帝に攻められて、ここハイデルベルグ城は廃墟になってしまう。
 以来何度も再建計画がもちあがるが、宮城のマンハイム、さらにはミユンヘンへの移転で、廃墟のまま現在に至る。 以来何度も再建計画がもちあがるが、宮城のマンハイム、さらにはミユンヘンへの移転で、廃墟のまま現在に至る。
建物の壁には目盛りが書いてある。これは中世の日時計である。もちろん、グリニッジ標準時とか、サマータイムの概念のない時代の時計である。壁から突き出たバーの影が当時の正しい時刻を表示している。
建物の中に入ると20万リットルを超えるワインを貯蔵できる超巨大な樽がある。樽というより、巨大な建造物のような木製の樽である。
巨大な廃城ということで、ドイツの多くの芸術家がここを愛し、絵画や詩作に残しているという。堀にかかる石橋の向こうは、やはりここを何度も訪れた文豪ゲーテが、スケッチをした場所があるという。そこに行って城を眺めても、ゲーテのような感性がないので何故ここが良いのかわからない。へなおじさんも、ましおばさんも芸術より食い気、城の入り口にあったアイスクリーム屋さんで、2ユーロのチョコバーでも食べよう。
|
 アイスクリームを舐めながらハイデルベルグ城の下を覗くと、そこには赤い屋根のハイデルベルグ旧市街が見えている。
アイスクリームを舐めながらハイデルベルグ城の下を覗くと、そこには赤い屋根のハイデルベルグ旧市街が見えている。
クロアチアのドブロクニクのような中世の景観がそこに広がって美しい。ネッカー川が流れているが、そこに架かる赤煉瓦の橋がアルテブリュッケ、古い橋と呼ばれているカール・テオドール橋である。全長は220メートル、中世には城の一部を形成する大橋であった。第二次大戦中、進軍してくる連合国を阻止するためにドイツ軍が自ら破壊、しかしこれは市民の大切な動脈の一部、戦後すぐに復興されて現在に至っている。
バスで丘を降りて旧市街を散策する。一段とそびえ立つ聖霊教会の他に、宗教改革のマルチンルターにゆかりのあるペータース教会など、ヨーロッパ史特に中世史にはきわめて疎いへなおじさん、添乗さんの説明をお聞きしても、少しも頭に入ってこない。
トイレ休憩を兼ねて民芸品店でショッピング、ここらはグミが名物らしいが、グミが苦手のへなおじさん、全く興味なし。ゾーリンゲンのピーラーなども売れているようであるが、前回ドイツに来たときに購入しているので、これも今回はパスである。
さてハイデルベルグを終えると次は今日の宿泊地、ローテンブルクまで160キロほどの移動である。バスはマイン川を遡ってアウトバーンに入る予定であるが、バスの運ちゃんが間違えて古城街道を驀進する。添乗のHさんが気づくも、既に手遅れである。もちろんアウトバーンをただ走るよりは、道の左右に中世の古城が点在する古城街道の方が景観は良いに決まっている。但し、下道であるのでバスの進みは遅く、しかも遠回り、ホテルへの到着、ひいては夕食がいただける時刻が遅くなりそうである。
感心するのは添乗のHさんである。道路の様子を見てアウトバーンに行く道でないことに気づくのもすごいが、通る予定がなかった古城街道を通過中も、このカーブを回ると、右手に何とか城が見えてきますとか、マイン川の右手遥か先に何とか城が見えますとか、まさに自分の故郷の道を案内するようにアンチョコも見ないで説明してくれる。
 道は空いていて予定通りローテンブルグ旧市街地の城壁内にある小さなホテルに到着する。 道は空いていて予定通りローテンブルグ旧市街地の城壁内にある小さなホテルに到着する。
夕食はホテルでロールキャベツ、白アスパラガスは13ユーロで皿に盛ってくれるというので注文する。メインのロールキャベツはキャベツが肉厚、ドイツ人は生のキャベツは食べませんというが、これでは生では無理であることがわかる。酢漬けにしてでも柔らかくする意味が判明する。
特注した白アスパラガスはタルタルソースのような美味しい白いソースがかかっていて、極めて美味、超満足である。
|
食事をいただきながら添乗のHさんが説明を開始する。バスの中でも説明をしていたが、寝ていた人も多かったので、再度繰り返しのサービスである。
 ここローテンブルクは中世の宝石と呼ばれるほど中世の雰囲気を残した街で、明朝歩いて観光します。このホテルから歩いて10分ほどのところに市庁舎があります。その横に建物があって、その建物には仕掛け時計があります。明朝そこまで行きますが、仕掛け時計が動くのは1日7回、11時から15時までの5回と、21時、22時です。朝は11時より早いので、動くのを見ることはできません。今から行けば21時に間に合います。動くのが見たい人は私に付いてきてください。
ここローテンブルクは中世の宝石と呼ばれるほど中世の雰囲気を残した街で、明朝歩いて観光します。このホテルから歩いて10分ほどのところに市庁舎があります。その横に建物があって、その建物には仕掛け時計があります。明朝そこまで行きますが、仕掛け時計が動くのは1日7回、11時から15時までの5回と、21時、22時です。朝は11時より早いので、動くのを見ることはできません。今から行けば21時に間に合います。動くのが見たい人は私に付いてきてください。
非常に要領の良い説明である。ほとんどの皆さんがHさんに付いていく。
市庁舎の横に小豆色の建物がある。上の三角形の底辺の中央部に時計がある。その左右にそれぞれ窓があって閉まっている。
 17世紀のローテンブルクに宗教戦争が勃発する。いわゆる30年戦争である。新教つまりプロテスタント側についたローテンブルクは、旧教カトリック側のテリー将軍率いるスウェーデン軍に攻められ、街を包囲されてしまう。 17世紀のローテンブルクに宗教戦争が勃発する。いわゆる30年戦争である。新教つまりプロテスタント側についたローテンブルクは、旧教カトリック側のテリー将軍率いるスウェーデン軍に攻められ、街を包囲されてしまう。
そこでテリー将軍、街に火を放ち、皆殺しを宣言する。
まずはその前にと、市の食糧倉庫に貯蔵されていたワインを差し出す。
美味しいワインを飲んで気分が良くなったテリー将軍、大きなジョッキになみなみとワインを注がせ、「もしこのワインを一気に飲み干すヤツがいたなら許してやろう」と提案する。
失敗したら街はもちろん、住民の運命も途絶えてしまう。
 ここで前に進み出たのは老いぼれのヌッシュ市長、3リットルを超える大ジョッキを傾けて一気飲み、その場で昏倒してしまう。 ここで前に進み出たのは老いぼれのヌッシュ市長、3リットルを超える大ジョッキを傾けて一気飲み、その場で昏倒してしまう。
あっぱれヌッシュというわけで、テリー将軍は約束通り軍隊を引き上げてローテンブルクの街は救われる。
三日後に目覚めた老いぼれ市長のヌッシュは、その後80歳まで長生きして英雄と称えられる。
そういう愉快な故事をもとに造られたのが、このからくり時計、マイスタートゥルンクである。
21時になると左右の窓が開く。左から現れたのはテリー将軍、松明を片手に火を着けるぞと構えている。
右の窓に現れたのはヌッシュ市長、赤鼻の酔っぱらい市長が、大きなジョッキを一気飲みする。音もなく窓が閉まって、それで終わりである。
あれれ、あっけない幕切れというか、からくり自体は、へなおじさんのDIYでも造れそうな、そんな仕掛けである。つまり、エピソードが面白いから皆が見上げるからくり時計なのである。
 帰り道はHさんと別れてホテルに向かう。道には馬車通行禁止という珍しい標識がある。そんな標識に見とれて、帰り道がわからなくなってしまう。
帰り道はHさんと別れてホテルに向かう。道には馬車通行禁止という珍しい標識がある。そんな標識に見とれて、帰り道がわからなくなってしまう。
幸いホテルのフロントでもらってきたカードにホテル名が書いてある。レストランに飛び込んでお姉さんにホテルまでの行き先を聞く。地元のレストランのお姉さん、英語ペラペラである。
お姉さんに言われたとおりのルートでホテルにたどり着く。バスタブがないのでシャワーを浴びて早めに就寝する。
|
 昨夜は雷鳴がとどろいていた。朝の目覚めは依然として早いというか、早すぎる。 昨夜は雷鳴がとどろいていた。朝の目覚めは依然として早いというか、早すぎる。
ふたりでホテルを出て、ここローテンブルク旧市街を囲む城壁の方に行ってみる。
立派な城壁が残っていて、その城壁に登ることができるよう、階段が付いている。
さすがの石でできた城壁も、年月を経ると劣化する。そこで修復が必要で、それには資金がいる。日本人も寄付をしているとかで、寄付をした方の名前が刻んであるという。日本橋の木屋、あのメチャクチャに斬れる包丁などを売っている老舗の木屋さんも資金を寄贈しているという。ゾーリンゲンの本場のドイツにまで来て、寄贈したというから、その名前を探すが、見つからない。
 階段を登って城壁の通路に出て旧市街側を上から見下ろす。赤いスレート屋根の建物、教会の尖塔が、いかにも中世の建物の雰囲気を醸し出している。
階段を登って城壁の通路に出て旧市街側を上から見下ろす。赤いスレート屋根の建物、教会の尖塔が、いかにも中世の建物の雰囲気を醸し出している。
苔むして朝露に濡れているが、中世から今に至るまで住民が居住し、教会では毎日曜日にミサが行われているのである。
日本の木造家屋は30年も経てばそろそろ立て替えとか、リフォームとかを考えるのであるが、ヨーロッパの建物は100年単位、ライフラインの配管は手入れしても、外観はそのまま使っているのである。
ホテルに戻って朝食、野菜類はないが、ボイルドエッグ、茹でたソーセージなどの暖かい食べ物もあって、ありがたい。ライ麦パンもことのほか美味しい。
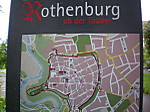 朝食後は添乗のHさんを先頭に、ローテンブルクの旧市街の散策である。 朝食後は添乗のHさんを先頭に、ローテンブルクの旧市街の散策である。
ドイツやこれから行くスイスは、制限が緩く、現地で手配したガイドでなくても、添乗員でもガイド役を務めることができるという。中国などは国営旅行社のガイドがいないと街が歩けない。しかも怪しい店に連れて行かれて、ニセモノをつかまされることが多いのであるが、そういう点ではヨーロッパ旅行は気が楽である。もちろん、イタリアやスペインのように、ガイドの資格を持った人しか説明できないという縛りをしている国も多いが、怪しい店に連れて行かれて、買い物を強制されるようなことはない。
ブルク公園という城跡から見下ろす景色も美しい。こちらにも城壁があって、日本橋木屋の名前はこちらの城壁に刻まれているということである。
 季節が良いときに来たのか、色とりどりの花が満開である。 季節が良いときに来たのか、色とりどりの花が満開である。
昨夜のからくり時計がある市庁舎前の広場で解散となる。広場では屋台が出ていて、アメなどを売っている。韓国から来た若い女性がアメ屋さんを冷やかしている。
我々は年中クリスマス用品を売っているという、クリスマス用品専門店に行ってみる。ましおばさんが買いたいモノがあるというので、開店前のお店を無理矢理開けてもらってお土産を買う。
|
 市庁舎前の広場から、今朝は迷わずにホテル前に戻ってくる。 市庁舎前の広場から、今朝は迷わずにホテル前に戻ってくる。
ホテルの前には広い駐車場があって、たくさんのクラシックカーが並んでいる。
商談会でもあるのかと聞きにいくと、マニアが自分のクルマを見せびらかして、あとでパレードをするという。つまり、動かなくなったようなクルマは1台もなくて、すべてが現役のクラシックカーであるという。
ベンツのエンブレムがついた、いかにもチャップリンが乗っていそうな雰囲気のクラッシックカーは、塗装部分はもちろんのこと、メッキの部分も銀色に輝いている。
 ミスター・ビーンの映画に出てきそうな、3輪の二人乗り乗用車がある。日本では3輪はかつて7のナンバープレートが準備されていたが、3輪の乗用車を登録する人がいないので、今は4輪と同じ扱いになってしまっている。
ミスター・ビーンの映画に出てきそうな、3輪の二人乗り乗用車がある。日本では3輪はかつて7のナンバープレートが準備されていたが、3輪の乗用車を登録する人がいないので、今は4輪と同じ扱いになってしまっている。
何とBMWのエンブレムが光っている。BMWは、こういう3輪乗用車も生産していたのだ。
日本では軽自動車より更に小さな超小型車の規格を検討しているとのことであるが、三輪で走行は不安定、ただし、時速30キロほどでノロノロ走るなら、こういうクルマも参考になりそうである。
しかしこのクルマ、座席は狭そうである。カラダの大きなアーリア系のドイツ人では、足がつかえてしまって、ブレーキが踏めないような気もしてくる。

ドイツで生産されたクラシックカーの一角に、トヨタのエンブレムのクルマがある。
セリカ1800GT、トヨタのスポーツクーペである。へなおじさんはこの1800GTではなくて、この後継車種である2000ccのセダンを所有していたことがある。
ということで、見ていると所有者が現れて、日本から来たのか、すごいだろうと自慢する。オレもセリカに乗っていたというと、さすが第二次大戦を一緒に戦った日本人とドイツ人、ハナシが弾んでくる。といっても、所有者は40歳台くらいの陽気な夫婦である。
外装はピカピカに磨かれて、エンジンルームの中まで磨かれている。このナンバープレートがすごいだろうと、末尾の81を見ろという。セリカ1800GTが生産されはじめた、その最初の年に生産されたクルマだから、1981年の81だという。翌年にターボチャージャーを付けた、更に性能をUPしたセリカが生産されはじめた、だから、このクルマは、ターボチャージャーなしのクルマである。それは、ともかく50年といわれるクラシックカーの定義からみれば、まだ年代を経ていないので、あと20年は乗ってクラシックカーの仲間入りをしてくれとエールを贈る。
|
ローテンブルクの出発は9時30分の予定であるが、ホテルのポーターさん、ラテン系のおっさんでのんびり仕事をしている。添乗のHさんが急かすが、No
Problemと返事をするばかり。結局荷物の積み込みが遅れて出発が遅れる。出発して程なく、新婚さんの1組が忘れ物をしましたと申告、早く気づいて良かったが、更に出発が遅れる。まあ良くあること。こちらが当事者になることも多い。ここであせってはいけない。
ホーエンシュバンガウまでの道のりは長い。我々が乗るバスの運ちゃん、安全運転であるが、少しトロい。添乗のHさんがトイレ休憩を指示したガソリンスタンドへの出口を見逃し、アウトバーンを降りそこなう。無事トイレ休憩をすませ、もう一度アウトバーンに戻ろうとするが、こんどはジャンクションの同じ道を、ぐるぐると2回程回っている。結局Hさんが進路を指示している。
もともと少し遅めの昼食の予定が、レストラン到着が2時、おなかはペコペコで、雨まで降ってきた。
昼食はパンケーキの細切りの入ったコンソメスープが暖かくて美味しい。同じテーブルには、松戸からご参加のご夫婦と、いつも二人で海外旅行を楽しんでおられるという、70台のご姉妹。松戸のご夫婦はアメリカに住んでおられたとかで、ご夫婦とも英語ペラペラである。今回の28人のツアー客で英語がOKなのは、このご夫婦と、へなおじさんの3人であることが判明する。奥様は腰痛の手術後、スポーツクラブのステップで腰の回りの筋肉を付け、ようやく歩けるようになってご参加とのことである。ステップはへなおじさんも熱心に参加しているが、効果がありそうであることを聞いて安心する。老姉妹のお二人は意欲旺盛で活動家、世界の秘境をあちこち回っておられるという。今回のツアーでもカメラ片手に早足に先回りして写真を写しておられる。聞くとお孫さんが10人もおられるとのこと。こういう出会いが海外旅行の楽しみである。
 ホーエンシュバンガウ城が眼下に霧でかすんでいる。この城はルートビッヒ2世のお父さん、マクシミリアン2世の城である。シュバンガウというのは、ドイツ語で白鳥の里、これぞワグナーが作曲したローエングリンの白鳥伝説ゆかりの場所なのだ。今回のツアーでは訪問地に入っていないが、この城には中世の騎士伝説の壁画、ローエングリンの世界を描いた壁画があるという。
ホーエンシュバンガウ城が眼下に霧でかすんでいる。この城はルートビッヒ2世のお父さん、マクシミリアン2世の城である。シュバンガウというのは、ドイツ語で白鳥の里、これぞワグナーが作曲したローエングリンの白鳥伝説ゆかりの場所なのだ。今回のツアーでは訪問地に入っていないが、この城には中世の騎士伝説の壁画、ローエングリンの世界を描いた壁画があるという。
息子のルートビッヒ2世がこの城に触発され、この近くの山の上にノウシュバンシュタイン城を建設したのであるが、彼が、現実と夢幻の境界線がわからなくなり、狂気に走った原因がこのホーエンシュバンガウ城にあるとすれば、両方の城を見物しないことには想像力を働かせることはできないのである。
今日はこの地の領主様の息子の結婚式とのことである。もちろん共和国のドイツに貴族制度はいまや存在しないのであるが、王政の敷かれていた当時からの貴族は未だに爵位を名乗り、気高く、広い敷地を所有し、高額な税を納め、更に多額の献金をしたり、社会貢献活動に従事して活躍し、尊敬されているのである。ノイシュバンシュタイン城の麓の領主さんということは、ルートビッヒ2世にゆかりの貴族の末裔なのであろうか?
明日行く予定のヴィース教会でプリンスが式を挙げ、駐車場の先にしつらえてある仮設のテントで地元の皆さんを招待して披露宴をしているとかで、普段ならバスで進入できる駐車場までの道が通行止め、おかげで雨でぬかるむ坂道を歩いて登らなければならない。ドイツも観光収入が頼りのハズ。貴族の皆さん、地元民だけではなくて、異国から来た観光客のことも少しは考えなさい。
|
ドイツ観光の目玉のひとつ、ディズニーランドのシンデレラ城のモデルになったといわれるノイシュバンシュタイン城をこれから見物する。
先ほど霧に霞んでいたホーエンシュバンガウ城がたたづむ場所にかつてあった、シュバンシュタイン城に対して、ノイ(新しい)のシュバンシュタイン城というのが命名の由来である。
 若きルートビッヒ2世は中世の騎士道精神に憧れをいだき、作曲家ワグナーに傾倒していく。そんな中パリのベルサイユ宮殿などを見てしまうと、ルートビッヒは、自らの城を築こうと決意する。父の城のホーエンシュバンガウ城にも触発されて、その地の山の上に、一段と豪華なノイシュバンシュタイン城を建設し始める。
若きルートビッヒ2世は中世の騎士道精神に憧れをいだき、作曲家ワグナーに傾倒していく。そんな中パリのベルサイユ宮殿などを見てしまうと、ルートビッヒは、自らの城を築こうと決意する。父の城のホーエンシュバンガウ城にも触発されて、その地の山の上に、一段と豪華なノイシュバンシュタイン城を建設し始める。
首都のミユンヘンにも戻らず、この地でワグナーのローエングリンに酔いしれるルートビッヒ、この城だけではなくて、更に各地に城の建設を企画するのである。
「ワグナー作曲、歌劇「ローエングリン」より"第3幕への前奏と婚礼の合唱"
川崎吹奏楽団 、3分を過ぎたあたりから皆さんもご存じ、結婚行進曲が流れます。」
http://www.youtube.com/watch?v=D-zPhAiRdGg
これではドイツ帝国の崩壊とばかり、バイエルン政府はルートビッヒを精神異常として幽閉、ある日精神科の主治医とともに、ベルク城近くの湖で水死体になっているところを発見される。
それ以来建設は中断されて、一般に公開されたという運命の城である。未だに未完成、歴史的には130年ほど前の新しい城であり、ユネスコの世界遺産への登録はなされていない。
城は山の中、専用のバスに乗車して急勾配を登っていく。バスを降りて、まずは、絶景の城を見ましょうと、ペラート渓谷にかかるマリエン橋に向かうことに。ところが一面の霧で、ノイシュバンシュタイン城は全く見えない。
ということで、仕方なく城のゲートから、入り口広場に入っていく。我々の入場時刻は午後5時、電光掲示板が今入ることができるチケットの番号を表示する。
ようやく入場すると、トランシーバーのような機械を渡され、案内のお姉さんに連れられて、部屋に案内される。お姉さんは英語での説明をしてくれるが、トランシーバーからは日本語の説明が聞こえてくる。我々と同時に入場したメンバーは、国籍さまざま、それぞれのトランシーバーからは、それぞれの国の言語が流れている。内装は思いの外豪華に完成されている。
 この城にもう一度来ても良いのであるが、せっかくここまで来たのだから、何とかマリエン橋からのノイシュバンシュタイン城を見てみたい。絵はがきのノイシュバンシュタイン城はマリエン橋からの景色である。
この城にもう一度来ても良いのであるが、せっかくここまで来たのだから、何とかマリエン橋からのノイシュバンシュタイン城を見てみたい。絵はがきのノイシュバンシュタイン城はマリエン橋からの景色である。
幸いHさんに指示された集合場所は今バスで登ってきた坂道の麓のお土産屋さん、集合時刻にも間がある。
ということで、マリエン橋まで走るかと、ましおばさんと意見が一致する。その前にトイレである。場内のトイレは日本と同じ形をしているが、下にアブが止まっている。よく見ると、陶器に書かれている絵のアブであることがわかる。
おしっこをあちこち飛び散らさないように、このアブを目がけて用を足しなさいという配慮のようである。直立不動の真面目なドイツ人を想像するが、案外ドイツ人はユーモアにあふれた皆さんかもしれない。
 すっきりしたところで、ましおばさんと小走りでマリエン橋を目指す。 すっきりしたところで、ましおばさんと小走りでマリエン橋を目指す。
途中で新婚の夫婦が抜いていく。若い彼等はさすがに足が速い。何と、今回のツアー客の中では最年長と思われる70台の姉妹も、カメラ片手に小走りである。
細い吊り橋の中央まで出て、城の方向を見てみる。何という奇跡、先ほどまでの霧が一瞬晴れて、絵はがきと同じノイシュバンシュタイン城が見えている。先ほどは霧で気づかなかったが、この橋の下は深い渓谷で、足下を透かして遙か下に川が流れているのも見えている。それに気づいたましおばさん、足がすくんで、急に動きが鈍り、顔色も悪く、記念撮影は恐怖に顔がゆがんでいる。ということで、このブログに掲載するのは、へなおじさんの記念写真である。それにしてもノイシュバンシュタイン城、左側面には足場が組まれて修復中である。見えたは見えたで興ざめの城、それがノイシュバンシュタイン城である。
|
本日の宿泊はオーストリア国境に近いガルミッシュパルテンキルヘン。ヒトラーの時代に冬季オリンピックを開催した場所で、標高が高く、バスはぐんぐん高度を上げていく。名前が長いのはもともとガルミッシュ村とパルテンキルヘン村が合併してそれぞれの名前をくっつけたからであるが、ヒトラーがオリンピック誘致の際、それぞれの村では規模が小さくて誘致の要件に合わないため、無理矢理合併させたといういわくがあるという。
リヒャルト・シトラウスの「アルプス交響曲」は、彼がここの街の山荘に滞在中にインスピレーションを得て作曲された曲と言われていて、この街の名誉市民にもなっており、リヒャルト・シトラウス博物館もあるという。
http://www.youtube.com/watch?v=GdG1pP3GYmQ
さて、このツアーに参加している親子(母と娘)づれ、バスの中では親子そろって、いつも居眠りしているが、今は娘の方が起きてスマートホンをいじっている。もう一方の手にはスマートホンと同じくらいの大きさの機械を持っている。聞くと、スマートホンは自前のものであるが、もうひとつの機器は成田で借りてきたWi−Fiであるという。
ドイツテレコムなどの地元の携帯電話の電波を拾い、Wi-Fiの電波を発信、それを自前のスマートホンで受けてインターネットをしているのだ。ちゃんと繋がって、速度もまあまあですよという。レンタル料は行き先の国によって異なるが、1日あたり1500円ほど、保険料などを入れると今回のツアーで合計2万円弱ほどのレンタル料で、使い放題という。
キャリアがソフトバンクのiPhoneでは、日本時間での1日あたり(ヨーロッパだと、時差の関係で、少しだけの利用でも2日間に跨ることがあるので注意)、2980円であることを考えると、毎日利用するならば成田でこういう機器を借りてきた方が安いということである。
仕事で不特定多数の人に電話をするというニーズがあるという人でなければ、インターネット回線を利用するスカイプで音声電話をすれば良いし、普通のインターネットメールで、メールをすればOKである。
ホテルに到着して各自の部屋のキーを配り終えた添乗のHさん、スマートホンでインターネットのサイトを見ている。どうのような方法でwebに繋げているか聞くと、ホテルが用意しているWi−Fiの電波を使っているという。ここのホテルは一晩10ユーロであるが、ホテルによって値段はまちまちで、今は無料のホテルも多く、10ユーロ取るというのは高い方で、明日のホテルは無料のはずですよという。
成田で宿泊した日航成田では、部屋にイーサネットのケーブルがあり、それに家から持ってきた機器を繋いでWi−Fiに変換し、それでIphoneを使っていたが、これは無料であった。海外でもイーサネットのケーブルで、無料でインターネットOKというホテルが増えてきていて、どのようにwebにつなげるか、方法と料金の選択肢が増えてきたのである。
もちろん、ホテルに備え付けのパソコンを備えているホテルも多く、これも無料だったり有料だったりまちまちである。もちろん、備え付けのパソコンは、キーボードがここではドイツ語であるし、アラビア語だったり、ギリシア文字だったりすると、お手上げである。日本語の入力は難しいし、@を出すのも一苦労である。
15年ほど前、それぞれの国に合わせた電話のアダプタを持参し、これまた日本から持参した重たいノートPCを電話回線にそのまま繋げて、メチャクチャに遅いレスポンスにイライラしながらメールを送ったり、インターネットのサイトを閲覧し、翌日電話代を1万円も取られたことを考えると、今は天国である。
 ということで、海外旅行の際のwebをどうするかという結論であるが、毎日、しかもホテルを離れて街中でもwebをするなら、成田でレンタルのWi−Fiを借りてくるというのがベスト、ホテルに入ってから、たまに日本に連絡したりwebを閲覧できればいいやというなら、ホテルのイーサネットケーブルか、ホテルが準備しているWi-Fi、それも安く上げようというなら、無料のホテルでだけ使うというのがベスト、それにホテル備え付けの無料のパソコンを使ったり、日本の年寄りに電話するというなら、時差を考慮の上で、成田で購入してくる国際電話カードで、街角の公衆電話から電話するというのが、結論のようである。もちろん、重たいPCを持参するのではなくて、日本で日常使っているスマートホンを、ローミングをOFFにし、Wi−Fiの電波があるときだけ使うというのが良いように思われる。但しローミングをOFFにしておくと、携帯電話のメール(SMS)が届かないので、かつて、いつ危篤になるかわからない親を抱えていた我が家では、ましおばさんの普通の携帯電話はONの状態にして、親戚には、いざというときは、そちらに電話かメールをするよう、予め頼んでおくことが必要である。スマートホンのローミングをONにしておくと、位置情報を勝手に知らせたり、ソフトのUPデート情報を勝手に送ってきたりと、知らない間にローミング通信をしているという危険性がある。
ということで、海外旅行の際のwebをどうするかという結論であるが、毎日、しかもホテルを離れて街中でもwebをするなら、成田でレンタルのWi−Fiを借りてくるというのがベスト、ホテルに入ってから、たまに日本に連絡したりwebを閲覧できればいいやというなら、ホテルのイーサネットケーブルか、ホテルが準備しているWi-Fi、それも安く上げようというなら、無料のホテルでだけ使うというのがベスト、それにホテル備え付けの無料のパソコンを使ったり、日本の年寄りに電話するというなら、時差を考慮の上で、成田で購入してくる国際電話カードで、街角の公衆電話から電話するというのが、結論のようである。もちろん、重たいPCを持参するのではなくて、日本で日常使っているスマートホンを、ローミングをOFFにし、Wi−Fiの電波があるときだけ使うというのが良いように思われる。但しローミングをOFFにしておくと、携帯電話のメール(SMS)が届かないので、かつて、いつ危篤になるかわからない親を抱えていた我が家では、ましおばさんの普通の携帯電話はONの状態にして、親戚には、いざというときは、そちらに電話かメールをするよう、予め頼んでおくことが必要である。スマートホンのローミングをONにしておくと、位置情報を勝手に知らせたり、ソフトのUPデート情報を勝手に送ってきたりと、知らない間にローミング通信をしているという危険性がある。
パソコンやスマートホン、インターネットに関し、ある程度の基礎的な知識がない人、このブログを読んでも、何が書かれているのか、意味がわからない人は、海外にはスマートホンを持っていかない、あるいは持っていっても、電源を切っておくか、ローミングをOFFにしておいた方が無難である。
|
今日も朝早く出発する予定で、目覚めは早い。ガルミッシュパルテンキルヘンは高地にあるためか、あるいは小雨のせいなのか、かなり寒い。
バスで7時半にホテルを出発する。添乗のHさん、ここらは、少し大きめの白いソーセージが名物ですが、皆さん朝食で食べましたか?と聞く。バイキングの朝食で、供されていた食材が多かったせいか、残念ながら見逃し。また次の機会にいただきましょう。
 ノイシュバンシュタイン城近郊の領主のプリンスが昨日結婚式を挙げたヴィース巡礼教会に到着する。 ノイシュバンシュタイン城近郊の領主のプリンスが昨日結婚式を挙げたヴィース巡礼教会に到着する。
ヴィースというのは、ドイツ語で草原という意味とのこと、確かに草原の中に建つ、外観はどこにもありそうな教会である。
あれ、世界遺産のマークがあるわよ、でも、たいしたことなさそうね、小馬鹿にしながら、入り口に向かって進んでいく。
到着は早かったのだが、今日は日曜日、早朝からミサが行われていて、その間、内部は写真撮影禁止。しかも信者さんの後ろで、静かに見学してくださいねと念を押される。
 中に入るとびっくり仰天、ロココ調のきらびやかな装飾が、実に豪華絢爛、素晴らしい教会なのである。立体的な彫刻が見事で世界遺産に登録されるのは当然と思えてくる。
中に入るとびっくり仰天、ロココ調のきらびやかな装飾が、実に豪華絢爛、素晴らしい教会なのである。立体的な彫刻が見事で世界遺産に登録されるのは当然と思えてくる。
信者の皆さんが向いている方向に、鎖で縛られている、少し古そうなキリスト像がある。豪華絢爛な装飾に対して、少し違和感のある古い像である。
これぞ、涙を流すキリスト像、農夫の奥さんがある修道士の彫った鞭で打たれるキリスト像をもらい受けると、そのキリスト像、夜に血の涙を流している。そのウワサは近隣にまたたくまに広がり、信者がこの地に巡礼し、その像を見にくるようになる、ということで、この像を安置する教会を建てて、ヴィース教会と名付けるという、それが18世紀のことである。
 キリスト像までは遠くて、よく見えないが、確かにキリストの目からは涙が流れているようである。 キリスト像までは遠くて、よく見えないが、確かにキリストの目からは涙が流れているようである。
キリストや聖母マリアの像が、血の涙を流すというのは世界各地にあって、我が国にも秋田湯沢台の教会に涙を流す聖母マリア像がある。こういう涙は奇跡と呼ばれているが、バチカンの正式な認定を受けないと、奇跡とは呼ばれない。もちろん、秋田の聖母マリア像もバチカンお墨付き。
このヴィース教会、辺鄙な田舎町にあるのだが、ヨーロッパはもちろん、世界中から奇跡を信じる信者が巡礼に訪れるという。何が世界遺産か?などと一時思ったへなおじさん夫婦、勉強不足を恥じることしばし。
さて今日も観光の目玉が目白押し。その前にトイレということで、教会の前の有料トイレにみんな並ぶ。ドアに料金を入れて入るような仕組みで、ドアを閉めると中からは開くが、外からはお金を投入しないと開かない。ということで、用を済ませて出たら、ドアを閉めないようにして次の人が入るを繰り返して、最初の人だけ有料で、あとの人は合法的に?料金を免れる。どうも、世界共通の知恵のようである。
|
今日は日曜日、高速道路上にはキャンピングカーの数が目立って増えてきている。へなおじさんのキャンピングカーはいすゞエルフをベースにした日本車であるが、キャビン内部の機器は、ほとんどがドイツ製、ドイツはキャンピングカーが多いヨーロッパ諸国の中でも際だってキャンピングカーの登録が多く、また、製造メーカーも多いキャンピングカー王国なのである。
 バスはドイツからオーストリアに入る。ドイツ、オーストリア国境にはEUの標識があるだけで、ツアーの皆さんはほとんど誰も国境を通過したことに気づいていない。
バスはドイツからオーストリアに入る。ドイツ、オーストリア国境にはEUの標識があるだけで、ツアーの皆さんはほとんど誰も国境を通過したことに気づいていない。
本来はオーストリア国境にある事務所に税を申告して、お土産を大量購入した人のTAXフリーの手続きをする予定であったのだが、日曜日で事務所は無人、そのままの速度で通過したのだ。
オーストリアから一旦スイスに入る。スイスは永世中立国、EUには加盟していないので国境にはゲートが設けられている。
国境は写真やビデオの撮影は厳禁、ということで、目を凝らしていると、前を走る乗用車はバーが開いたままのゲートをそのままの速度で通過していく。
スイスもシェンゲン協定には署名しているので、国境はノーチェック、乗用車はそのままの速度で通過していくのである。但し、シェンゲン協定は人の通過だけ、トラックやバスは停車して、ゲートの窓口に書類を出して、必要とあらば関税を支払うことになる。我がバスの運ちゃんをとみると、係の人に聞きながら、一生懸命書類を書いている。このドイツ人の運転手、国境通過の手続きには慣れていない模様である。
スイスに入ったと思ったら、すぐにリヒテンシュタインとの国境である。
リヒテンシュタインも永世中立国、スイスとはいろいろな協定を結んでいて、国境ではノーチェックのフリーパスである。
 さて、このリヒテンシュタイン侯国、人口3万人あまりの小国であるが、立派な独立国である。 さて、このリヒテンシュタイン侯国、人口3万人あまりの小国であるが、立派な独立国である。
ヨーロッパには、バチカン、モナコ、ルクセンブルクといった、へなおじさんも訪れたことのある小国が数多い。今回のリヒテンシュタインへの入国で、小国4カ国目である。
まだ、イタリアにあるサンマリノとか、地中海に浮かぶ島国マルタ、スペイン・フランス国境に位置するアンドラ公国もあるので、ヨーロッパの小国は全部制覇しましたと胸を張ることはまだ先である。
リヒテンシュタインの国家元首は国王ではなくて侯爵、かつての神聖ローマ帝国の貴族のひとりが、神聖ローマ帝国滅亡後独立、そのまま統治を続けているという構図。一応国民の自治は保証されてはいるのだが、他の国が国家元首は象徴という位置づけにしているのに対し、リヒテンシュタイン侯の権限は絶大で、独裁ではないものの、最後の絶対君主などと言われることもあるという。
 国境がフリーパスなので、パスポートコントロールという概念はヨーロッパでは死語になっている。 国境がフリーパスなので、パスポートコントロールという概念はヨーロッパでは死語になっている。
このリヒテンシュタインも例外ではなくて、パスポートには出入国の印は押されない。ということで、バス停の前のインフォーメーションで、パスポートに国の印を押してくれるというサービスを展開中。もちろん有料の国策である。我々のメンバーは誰も並ばないが、アメリカやオーストラリアから来た人達はパスポート片手に並んでいる。へなおじさん、日本の出入国印だけでも押されないように指紋登録をしているわけで、ここでも、お金を頂けると言われても並ぶ気は全くなし。
スイスと同じように精密工業などでも収入を挙げているが、タックスヘイブンとしてのペーパーカンパニーも世界中からリヒテンシュタインの人口よりも多く集まり、そこからの収入で国民は所得税は免税というから、豊かな国である。
 更にイタリアにあるサンマリノのように切手にも力を入れているとのことで、歩道にはリヒテンシュタインの切手がデザインされている。
更にイタリアにあるサンマリノのように切手にも力を入れているとのことで、歩道にはリヒテンシュタインの切手がデザインされている。
日曜日のため広場の前の郵便局は休みであるが、開店中のお土産屋さんでは、絵はがきと並んでかなり売れているようである。
公用語はドイツ語、通貨はスイスフラン、オーストリアとスイスに挟まれた小国のリヒテンシュタイン、神聖ローマ帝国の時代から、時々の世界情勢をうまく読み切り、自国の通貨もなく、軍隊もないのに、したたかに存在を誇示している。ちなみに隣国スイスは永世中立の元祖のような国であるが、強力な軍隊を保有して国防に力を入れている。バチカンの衛兵もスイス人である。リヒテンシュタインは通貨のみならず、軍もスイスに依拠、国を守ってもらっているのである。
|
今我々はリヒテンシュタインの首都ファドーツにいる。
山手線内の面積の3倍ほどの小国リヒテンシュタイン、東京都区内がひとつの独立国だとすれば、東京都区内全域が首都で良さそうなものであるが、要はリヒテンシュタイン公爵家のおわします場所、ファドーツを首都にしているのである。リヒテンシュタイン家は超お金持ち、ファドーツ以外の場所にも領有地がある。従って、首都ファドーツには飛び地がある。これも東京に例えれば、皇居のある丸の内が首都、それに赤坂や、霞ヶ関、浜離宮などに丸の内の飛び地がある、そんな感じで考えるとわかりやすいのかもしれない。
 首都ファドーツ、ドイツ語表記でVaduz、英語読みではバードゥーズなどと発音しているようである。にぎやかな広場から見上げると、ファドーツ城が見えている。
首都ファドーツ、ドイツ語表記でVaduz、英語読みではバードゥーズなどと発音しているようである。にぎやかな広場から見上げると、ファドーツ城が見えている。
国家元首はリヒテンシュタイン家の当主、ハンス・アダムス2世、本名はヨハネス・アダム・フェルディナント・アロイス・ヨーゼフ・マリア・マルコ・ダヴィアーノ・ピウス・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタインさん、落語の寿限無(じゅげむ)のように長い名前であるが、いかにも代々の貴族の血を継承してきたという歴史が感じられる。
実はこの国家元首、長男のアロイス・フィリップ・マリア・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタイン氏を摂政にたてて第一線を退き、悠々自適の生活を送っておられるわけであるが、リヒテンシュタインを実質統治する青年摂政のアロイス公、スイスのチューリッヒ生まれ、リヒテンシュタインの大学を出てイギリスの士官学校に入学、イギリス兵としてロンドン、香港で兵役につき、更にオーストリアのザルツブルク大学で法律を学んで、イギリスの民間企業に勤務という、ヨーロッパを股にかけた、いかにも神聖ローマ帝国の時代からの貴族そのままの経歴をお持ちなのである。
リヒテンシュタイン家は全ヨーロッパを支配したハプスブルク家との関係も深く、リヒテンシュタイン家の城はハプスブルク家の城、世界遺産シェーンブルン宮殿のあるオーストリアのウィーン市内にもある。かつての名門貴族、ハプスブルク家やメディチ家などが没落後は、このリヒテンシュタイン家がヨーロッパに残った最も資産家の貴族ということらしい。
そういった昔からのオーストリアとの結びつきから、リヒテンシュタイン家の当主はオーストリアの国籍もお持ちで、居所もリヒテンシュタインというよりは、むしろオーストリアとかスイスなどの城におられることが大半ということ。陛下がイギリスの国籍もお持ちで、いつもオーストラリアやカナダにお住まいになっているということですよ、と例えられても、我々凡人には理解が難しいのである。
本日の昼食はリヒテンシュタインの首都ファドーツの、最もにぎわっている広場の前にあるレストランでいただくことになっている。
かぼちゃのスープ、さいころポテトのフライ、大きなホワイトソーセージ、それにデザートはアイスクリームである。
|
さて今回のツアーはスイスでの滞在期間が長い。ということで、成田でスイスフランの両替をしてきている。スイスは金融大国であるが、スイスフランがヨーロッパ全域で使えるわけではない。日常の通貨としてスイスフランが通用するのは、スイスとリヒテンシュタインのみである。特にコインはこの2カ国では通用するが、他の国では使えない。
逆にスイス、リヒテンシュタインでトイレに行きたいなどというとき、スイスフランのコインがないと困ってしまうことになる。お店などでの買い物とか、レストランで食事をいただくというときは、スイスでもリヒテンシュタインでも、ユーロの紙幣は受け取ってもらえるし、もちろんカードも利用できる。
ということで、成田でのスイスフランの両替は2人で日本円で5000円ほど、これで充分なのである。スイスフランが余ってしまい、日本円に再両替すれば、また手数料をとられてしまうので、余るほど多額のお金を両替する必要はないのである。
外国での両替でコインを入手するのは不可能である。つまり、成田での両替所で入手できたのは、スイスフランの紙幣のみである。これからスイスに入るにあたって、早速にもスイスフランのコインが必要となってくる。
ということで、お土産屋さんに入り、コカコーラを購入、ユーロ紙幣を出してスイスフランのコインでお釣りをもらう。
 スイスフランのコインは5フラン、2フラン、1フラン、それにハーフフラン(50サンチーム)、20サンチームなどがある。特に5フランコインは、500円玉をひとまわりも、ふたまわりも大きくした感じの、特大コインである。
スイスフランのコインは5フラン、2フラン、1フラン、それにハーフフラン(50サンチーム)、20サンチームなどがある。特に5フランコインは、500円玉をひとまわりも、ふたまわりも大きくした感じの、特大コインである。
ということで並べて、どれが、いくらのコインなのか、覚えることに。
リヒテンシュタインといっても、取りたてて観光すべきような場所はなさそうである。それでも小国ゆえのめずらしさからなのか、観光客はかなり多い。
さて集合時刻である。バスはスイスに向かって走り始めた。
|
 ライン川もここらあたりまで来ると川幅が狭い。そのライン川がリヒテンシュタインとスイスの国境になっていて、橋を渡るとスイスである。
ライン川もここらあたりまで来ると川幅が狭い。そのライン川がリヒテンシュタインとスイスの国境になっていて、橋を渡るとスイスである。
バスはマイエンフェルトにあるハイジの家に向かっている。ここから17キロ、30分ほどの道のりであるが、道が狭くてバスの進みはノロい。対向車でも来ようものなら大変であるが、幸い対向車はないので事なきを得ている。
日本でいえばハイジの家がありますというだけで行きたくなる観光地のはずである。山梨県にある「ハイジの村」は、あのハンナ・シュピリ原作のアニメの舞台ではないことがわかっていても行ってしまうほどである。
 それが、ハンナ・シュピリ原作の舞台そのもの、ハイジがおじいさんと暮らしている家まであるとなれば、観光客は目白押しというハズなのであるが、ここまでの道路は未整備で、大型バスはすれ違いが困難、というわけで、観光客もそんなには多くはなく、静かな村である。
それが、ハンナ・シュピリ原作の舞台そのもの、ハイジがおじいさんと暮らしている家まであるとなれば、観光客は目白押しというハズなのであるが、ここまでの道路は未整備で、大型バスはすれ違いが困難、というわけで、観光客もそんなには多くはなく、静かな村である。
http://www.dailymotion.com/video/xhsy59_yyyyyyyyyy-op-ed-hd_shortfilms
赤いほっぺのハイジを思い出しながら、アルプスの少女ハイジのテーマソングを歌いながら歩くへなおじさんと、ましおばさん、実にのどかな景色である。
 彼方にアルプスの山々が見えている。芝生がどこまでも広がる起伏の多い丘を、添乗のHさんを先頭に皆で散歩する。
彼方にアルプスの山々が見えている。芝生がどこまでも広がる起伏の多い丘を、添乗のHさんを先頭に皆で散歩する。
色とりどりの花が咲いていて、向こうからハイジやペーター、おじいさんが歩いてきそうな、そんな気がしてくる。
ハンナ・シュピリが物語を書いた1871年頃、日本でいえば明治の初頭からそんなに景色は変わっていないのかもしれない。
日本でアルプスの少女ハイジといえば丸顔で赤いほっぺ、大きなブランコに揺られているアニメのハイジである。
 それが、こちらでは、もう少し年上のいかにもスイス人の少女という感じの女の子で描かれている。 それが、こちらでは、もう少し年上のいかにもスイス人の少女という感じの女の子で描かれている。
明治の初頭、我が国にやってきたイタリア人のおかかえ外国人画家、キヨッソーネが描いた神功皇后の5円札の肖像を見た日本人も、同じような感想を抱いたのではないかと思われる。まさか、この看板に書かれている女の子、ハイジじゃないよね?そんな疑問が日本人観光客からわき上がっている。
|
ハイジの里からそんなに遠くないところにランドバッサー橋が架かっているというので、バスはそこを目指し川に沿った細い道を進んでいる。
少し広くなったところにバスを停めると、ここから歩いてくださいという。水音が聞こえる細い道を歩いていく。ウドとかタラの芽などの山菜でも生えていそうな、そんな山道であるが、残念ながら食べられそうな草は生えていない。
むしろクマでもでそうな感じで、鈴でも鳴らしながら歩いた方がよさそうな、そんな道である。
 突然視界が開けると、見えてきましたランドヴァッサー橋、長さ136メートル、高さ65メートルの巨大な石橋である。
突然視界が開けると、見えてきましたランドヴァッサー橋、長さ136メートル、高さ65メートルの巨大な石橋である。
ドイツ人技術者の指導の元、1903年に完成した橋というから、既に100年以上も実用に供されてきた現役の橋なのである。
最近鉄筋コンクリートの橋に架け替えられた兵庫県の日本海側にある余部鉄橋の完成が1912年というから、余部鉄橋より9年も前に架けられた橋なのである。
列車がトンネルから抜けるとこの橋に差し掛かるという設計も余部鉄橋に似ていなくもない。
余部鉄橋が出たついでに旧余部鉄橋と比較すると、余部鉄橋は長さが310メートルのほぼ直線であるのに対し、ランドヴァッサー橋はカーブしているものの長さはその半分に満たない。但し高さは余部鉄橋が41メートル、ランドヴァッサー橋の方が1.5倍も高いというから恐れ入るところである。
実は明日我々は氷河特急に乗ってこの上を列車で走るのであるが、あっというまにこの橋を通過してしまい、しかも、列車の中から見たのでは、橋の立派さや地上からの高さが全くわからないということから、わざわざ下から見上げるような日程を組んでくれたのである。
標高2284メートルのユリア峠を越えて、本日宿泊するサンモリッツに向かっている。何と雪がちらついているし、ここから見える山は万年雪をいただく白い山である。
 サンモリッツのホテルの前には寒暖計がある。見ると摂氏5度、おーっ寒い、いよいよスイスに来たぞという気がしてくる。
サンモリッツのホテルの前には寒暖計がある。見ると摂氏5度、おーっ寒い、いよいよスイスに来たぞという気がしてくる。
部屋は広くてバスタブも付いている。
夕食までは少し間があるというので、近くを散歩する。
さすがに観光立国スイス、近隣のEU諸国のナンバープレートを付けたクルマが多数駐車している。
 あらまびっくり、エアストリームが駐車している。このエアストリーム、アメリカ製のキャンピングトレーラーで、我々キャンピングカーを保有するオートキャンパーの間では、いつかはエアストリームで世界一周というあこがれのクルマなのである。
あらまびっくり、エアストリームが駐車している。このエアストリーム、アメリカ製のキャンピングトレーラーで、我々キャンピングカーを保有するオートキャンパーの間では、いつかはエアストリームで世界一周というあこがれのクルマなのである。
銀色に光るエアストリームの車体には通し番号が付けられていて、所有者のIDというか、メーカーお墨付きの所有者の印なのだと言われている。
ただ、重すぎて、これを引っ張るには日本では牽引免許が必要ということで、日本にもエアストリームの代理店は存在するのだが、実際にこれが走っているところは日本で見るのは稀である。へなおじさんも、実は牽引免許までわざわざ取って、これに乗る気は、ありません。
|
 ホテル前の広場から雪山が見えている。いかにもスイスという感じ、日本でいうと、春先の南アルプス、あるいは富山から見える立山連峰という感じである。
ホテル前の広場から雪山が見えている。いかにもスイスという感じ、日本でいうと、春先の南アルプス、あるいは富山から見える立山連峰という感じである。
マッターホルンはどこだべ?と言いながら360度見渡す。あれれ、ないぞ、と言っていると、マッターホルンは明日のツェルマットでご覧下さいな、ここサンモリッツからでは見えませんと、Hさん。
明日のツェルマット、日本から持ってきた地球の歩き方を見ると、ガソリン車乗り入れ禁止と書いてある。ヨーロッパ列強に囲まれたスイス、観光立国のスイスでは環境問題に熱心に取り組んでいて、いくつかの街でガソリン車の乗り入れ規制をしているのだ。
豊かな自然を守りたい、観光客は誘致したい、しかしヨーロッパ中央部に位置するスイス、アルプスを貫くトンネルでスイスを通過する物資満載のEU諸国のトラックは年間100万台を超えるという、そんなスイスの環境汚染は、見た目以上に深刻なのだ。ということで、一部の街ではガソリン車乗り入れ禁止、もちろん軽油を燃やす我がバスも乗り入れができないのである。
ということは、我々のスーツケースはどうするのよ?その前に夕食である。
 夕食の前菜はモッツァレラチーズとトマトのサラダ、メインは白身サカナのムニエルにズッキーニとポテト添え。 夕食の前菜はモッツァレラチーズとトマトのサラダ、メインは白身サカナのムニエルにズッキーニとポテト添え。
モッツァレラチーズはイタリアのチーズであるが、アルプスを越えればそこはイタリア、イタリアに近いせいかメチャクチャに美味しい。
この白身のサカナは何だろう?ウェイターとの間で、What is this
fish?Cod?Fish.このサカナ何?タラ?いやサカナです。などという珍妙な会話が交わされる。ドイツ語が母国語のウェイター、タラの英語名がわからないのか、サカナの種類などはどうでも良いという外国人の特性なのか、結局はよくわからない。スイスは海に面していないので、淡水魚の可能性はあるのだが、味はタラに違いないというのが多数派。
 デザートはティラミス、手抜きのない盛りつけである。甘くて美味しいが、どうみてもメタボ体型には良くなさそう。
デザートはティラミス、手抜きのない盛りつけである。甘くて美味しいが、どうみてもメタボ体型には良くなさそう。
ところで、荷物は?明日の朝バスにスーツケースを積み込むと、次にスーツケースに遭遇するのはあさってという。
スーツケースをバスに積まずに、氷河特急に持込み、更に明日のツェルマットのホテルまで引っ張るという選択肢、それぞれのスーツケースのうち、明日のホテルで必要なモノだけを一つのスーツケースにまとめてそれを持っていくという選択肢、これが皆さんの多数派のようである。
我々は、へなおじさんが日本から持参している少し大きめのデイパックに明日の夜必要なものを詰め込んで、スーツケースは2個ともバスに乗せたままにするという選択肢を選ぶ。
このホテル、Wi−Fi無料ということで、フロントでIDとパスワードをもらい、久しぶりにiPhoneを取りだして、日本の情勢、世界の情勢をチェック、更には留守番の子どもたちにも、久しぶりの連絡をする。それに荷物の整理、どれが必要で、どれはいらないと選別がはじまる。忙しい夜になりそうだ。
|
朝の目覚めは早い。幸い無料でwebにつながるので調べると、今日と明日は晴れまたは雪、気温は最低がマイナス6度、最高はマイナス1度と、いかにもスイスらしい気候ということで、寒さに備えた服装を準備している。
朝食は7時からだが、10分前にはレストランに人が入っていく、ということで、我々も中に入っていく。レストランの部屋はいくつもあるのだが、小さな1部屋しか開いてないので、西洋人東洋人入り乱れて早くも大混雑。
Hさんがスイスのパンはあまり美味しくないですと言っていたが、ここのホテルはパンだけではなくて、卵もハム、ソーセージもあって、手抜きはない。但しドイツからスイスにかけて、朝のサラダ類が少ないのが難点。また、卵は生で自分でお湯にいれて茹でるようになっている。茹で上がるまで付いているワケにはいかないので場所を離れると、他の人も卵を入れるので、自分の卵がわからなくなるのも難点。行楽地に来たなら、卵が茹で上がるまで待ちなさいということかも知らないが、忙しいせっかちなへなおじさんには、無理な相談。
エスプレッソも美味しくて、朝から気分が良い。
サンモリッツの駅まではバスで15分、ここであさってまでバスとお別れだ。

我々が今日お世話になる氷河特急、グレッシャーエクスプレスは赤と白のツートンカラー、中国やエジプトの列車とは違って、日本のJRの列車のようにピカピカに磨かれている。世界中からのお客さんを乗せて夢のような景色の中を走る列車である。これくらいきれいに磨いてもらわないとスイスの鉄道の名が廃る。
ここサンモリッツからツェルマットまで、8時間かけて走行するわけであるが、距離を調べるとこれがわずかに280キロ、東京、浜松間ほどの距離である。新幹線なら1時間半もかからないほどの距離、氷河特急が世界一遅い特急列車と言われる所以である。
先ほどスイス鉄道と書いたが、この氷河特急、マッターホルン・ゴッタルド鉄道とレーティッシュ鉄道の2社の運行である。
2010年に脱線事故を起こして日本人乗客が一人死亡しているが、それはスピードの出し過ぎが原因ということで、安全運転頼みますよ。
 1等車は横に3人席、2等車は横に4人席、我々は2等車で前後の4人席の間にテーブルがある食堂車のような配列である。2等車で十分のグオリティである。
1等車は横に3人席、2等車は横に4人席、我々は2等車で前後の4人席の間にテーブルがある食堂車のような配列である。2等車で十分のグオリティである。
へなおじさん夫婦だけが皆さんの席から離れている。なぜか団体ということで予約したのに、2人分だけ団体の中に他の客が入った模様である。そこらは観光立国の鉄道なのに、間が抜けている。
間もなく、ニュージーランドから来たカップルがやってくる。彼等にその席が割り振られていたのだ。事情を説明して席を替わってもらう。彼等にしてみても、日本人団体の中に割り込むような席では気詰まり。ということで、簡単に了承してくれる。もっとも今日はこの氷河特急空いていて、空席の方が多い状態である。何もぎしぎしに密集して座ることもあるまいと、皆さん少しづつ景色が良さそうな快適そうな空間に移動していく。
 列車は走り出すと大きなカーブの連続である。列車は長いので先頭に近い車両にいる我々から、大きなカーブになると後の車両が良く見える。
列車は走り出すと大きなカーブの連続である。列車は長いので先頭に近い車両にいる我々から、大きなカーブになると後の車両が良く見える。
また、我々の頭の上もガラスになっていて、迫る山の頂上に白く積もる雪も良く見える。まさにパノラマビューの素晴らしい構造の車両である。
座席にはヘッドホンの出力ジャックがある。チャンネルを日本語に合わせると、日本語での説明が聞こえてくる。
まもなくランドヴァッサー橋を通過しますというアナウンスがヘッドホンから聞こえてくる。トンネルを抜けると、おーーーっ、まさに昨日見上げたランドヴァッサー橋を我が列車が通過している。列車はノロいが、あっというまに通過してしまう。昨日見上げておいてよかったよかった。
|
 列車はクールという駅にしばらく停車したと思ったら、逆向きに走っている。 列車はクールという駅にしばらく停車したと思ったら、逆向きに走っている。
昔の中央線の塩尻駅や、近鉄の伊勢中川駅のようなスイッチバックになっているのである。景色が流れる向きが変わるので居眠りしていたましおばさん、目覚めて目をパチクリ。
クール駅で積み込んだお弁当が配られる。この列車、食堂車というか、キッチン車両が付いていて、メイドさんが各車両を回り、注文を取りに来て、注文した食事を座席まで運んでくれる。我々は、予算の関係なのか、あるいは確実性を重んじたのか?お弁当である。
どうみても800円くらいの弁当にしか見えない。わざわざ添乗のHさんが回ってきて、もともと物価が高いスイス、このお弁当も、みなさんびっくりされるでしょうが、日本円で2500円もするんですよと、弁明している。
確かに日本の800円の弁当の方が豪華であるが、パンもチーズもハムも、材料は良さそうで美味しい。
 この列車、7つの谷を越え、291の橋を渡り、91のトンネルを越え、カーブを回りながらゆっくりと進んでいく。
この列車、7つの谷を越え、291の橋を渡り、91のトンネルを越え、カーブを回りながらゆっくりと進んでいく。
1982年、フルカトンネルをトンネルで越えることができるようになるまでは、ローヌ氷河を見ながら進んでいた。ということで、氷河特急という名称であるが、今はトンネルで下をくぐってしまうために、残念ながらローヌ氷河を見ることはできない。
それでも604メートルの最低地点から、2033メートルのオーバーアルプ峠まで、標高差1400メートル以上を進むのである。
標高が最も高いオーバーアルプ峠に向かうには、機関車をアプト式のものに変更することが必要となる。30分の停車予定が対向の列車が遅れていて1時間停車になるという。ここまで来れば1時間だろうが2時間だろうが、待ちますよという気分である。
アプト式といえば、長野新幹線の開業で廃線になってしまった旧信越本線の碓氷峠を思い出す。そのアプト式がスイスでは今も現役で使われているのだ。カチカチャという歯車が噛み合うアプト式独特の音がして、列車は標高をぐんぐん稼いでいく。
 列車が遅れたというので、おわびにということで、メードさんが回ってきて、コーヒーか紅茶を無料でサービスしてくれるという。
列車が遅れたというので、おわびにということで、メードさんが回ってきて、コーヒーか紅茶を無料でサービスしてくれるという。
氷河特急をサンモリッツからツェルマットまで、すべて乗車したという記念に、あなたは氷河特急を全線乗りましたよという、A4版の照明書が配布される。ドイツ語英語の他に、日本語でもその旨が書かれている。
うれしいやら、うれしくないやら、まあ、荷物にはならないので記念にいただいておきましょう。
|
 氷河特急は予定時刻より少し遅れて午後6時少し前にアルピニストの聖地、ツェルマットに到着する。 氷河特急は予定時刻より少し遅れて午後6時少し前にアルピニストの聖地、ツェルマットに到着する。
駅を出ると四角いタクシーが並んでいる。ガソリン車の走行が禁止されているので、いずれも電気自動車で、小さな電気モーター独特の音だけ響かせて走っている。むしろタイヤが地面をこする摩擦音の方が大きいくらいである。
ここツェルマット、4000メートルを超える29ものアルプスの峰々に囲まれた標高1600メートルの街であるが、谷が深すぎるのか、駅前の広場からは氷河はおろか、ひとつの峰も見えない。
あれー、マッターホルンはどこよ?探しても見あたらない。皆さんあせらないで下さいね、今日も明日も天気は良いですから、マッターホルンは見えますからね、とHさん、しかも皆さんのホテルの部屋は全部マッターホルンビューのお部屋ですからね。
夕食はホテルの外のレストランの予定であるが、夕食の時間までは間があるので、まずはそのホテルに急ぐ。駅からホテルまでは歩いて5分ほど、我々はスーツケースはないが、皆さんのスーツケースは先ほどの電気自動車でホテルまで運んでくれるという。
 アンバサダーホテルに到着し、部屋に急ぎ、ベランダに出てみる。 アンバサダーホテルに到着し、部屋に急ぎ、ベランダに出てみる。
見えましたよマッターホルン、ピラミッドのような正四面体の霊峰が思ったより近くに鎮座しているではありませんか。
マッターホルンはドイツ語でマットが牧草地、ホルンが山頂ということで、牧草地の頂上という意味だそうだが、氷で覆われていてなぜ牧草地の山頂なのか意味不明である。フランス人の諧謔的な性格ならわかるが生真面目なドイツ人やスイス人のセンスからは良くわからない命名である。
標高は4478メートル、もともと今いる場所が標高1600メートルではあるのだが、すぐ近くに見えすぎて、そんなに高い山だとは思えない。
イタリア・スイスの国境にそびえていて、イタリア語ではチェルヴィーノである。テレビの鉄腕ダッシュという番組でジャニーズのTOKIOが、イタリアのドロミテ側からアルプスを越えて、スイス側に降りてきたことがあるが、それを見て以来、それを再現したくて、今回のツアーはその下見も兼ねているのだ。
 さて夕食の時間である。ホテルから少し歩いて川沿いにでると、またも見えましたよマッターホルン、一段と雪が映えてきれいに見えている。
さて夕食の時間である。ホテルから少し歩いて川沿いにでると、またも見えましたよマッターホルン、一段と雪が映えてきれいに見えている。
このマッターホルン、先が尖っているということもあるのだが、むしろ霊峰で人は登ってはいけないという観念もあったとのことで、初登頂は1865年、江戸時代最晩年と比較的最近である。
今ではルートも開拓され、登山技術や用具の進歩で経験を積んだアルピニストなら誰でも登れるようになったとのこと。
そんなこといわれても、登山素人のへなおじさんからは、とても登ることができるような山には思われない。
|
さて夕食はスイス名物のフォンデュ。マッターホルンを背にしてスレート屋根の民家を見ながら歩いてすぐのレストランでいただくことに。
我が家でのチーズフォンデュは、フランスパン、ブロッコリー、ソーセージ、ジャガイモなどを串に刺し、チーズにひたしていただくが、本場では少し違うようだ。
チーズにはフランスパンのみ、パンを食べるとスペアリブが出てくる。オイルフォンデュの鍋が出てきて、スペアリブはオイルに浸してくださいと説明される。牛肉の素揚げという感じである。
 朝5時に起床、今朝の日の出は5時58分、ということで、きっちり着込んで町外れの教会に急ぐ。 朝5時に起床、今朝の日の出は5時58分、ということで、きっちり着込んで町外れの教会に急ぐ。
皆さんはもう少し遅く、Hさんの先導でホテルから近い川沿いの道で朝焼けのマッターホルンを見物の予定であるが、我々は一足先にマッターホルンを見るには最高のポジションといわれる教会を目指したのだ。
雲一つ無い上天気の空は群青色に輝いている。マッターホルンは白く見えているが、日の出にはまだ少し時間がある。
ということで、教会の近くを散策する。新婚さんの一組がこちらに歩いてくる。やはり彼等は元気いっぱい、ホテルから離れたこの場所を目指したのだ。
 教会の裏に日本の国旗を見つける。そのプレートを見ると、ツェルマットと妙高高原町の姉妹都市の提携の碑である。
教会の裏に日本の国旗を見つける。そのプレートを見ると、ツェルマットと妙高高原町の姉妹都市の提携の碑である。
妙高高原町は、隣の妙高市、新井市などと合併して妙高市になっているが、その平成の大合併前の提携である。
妙高高原町、ましおばさんの父親の出身地である。山男だった彼の墓はまさに妙高山が見えるところにある。生きていたら今回の旅行に同行してきたに違いない。氷河に輝くマッターホルンを見せたかったね、といいながら、先ほどの教会の方に戻っていく。
 マッターホルンを見ていると、先ほど群青色だった空は、薄い水色になってくる。 マッターホルンを見ていると、先ほど群青色だった空は、薄い水色になってくる。
白かったマッターホルンの先端が少し赤くなってきた。日の出である。
あっという間に山頂の近くが燃えてきた、そんな感じである。ふいごの風で熱せられた鉄のように赤いのである。
すごい景色でしばし声が出てこない。シャッターを押すのも忘れてしまうほどの、すごい景色である。
Hさんに引き連れられた皆さんも、こんなにきれいな景色を見ることができたのだろうか。
 ホテルまでの帰りはツェルマットの街のメインストリート。観光客は誰もいない。あんなにすごいマッターホルンの朝焼けを、外国からの皆さんは見ないのだろうか?
ホテルまでの帰りはツェルマットの街のメインストリート。観光客は誰もいない。あんなにすごいマッターホルンの朝焼けを、外国からの皆さんは見ないのだろうか?
商店街は防犯のためか、電気はついているがひっそりと静まっている。パン屋さんだけが電気自動車にパンを積んで走っている。
ホテルに戻って朝飯にするか、少しだけ仮眠をとって今日の観光に備えるか、中途半端な時間帯である。
|
|
|
 マッターホルンの朝焼けはいかがでしたか?皆さんに聞くと、部屋のベランダから見ていた人は見逃したとおっしゃる。ほんの一瞬の炎のマッターホルンは、凝視していないと難しいことがわかる。へなおじさん、妙高山の朝焼け(朝の炎)は見たことがあるが、これで、提携している二つの街の代表的な山の朝焼けを見たことになる。
マッターホルンの朝焼けはいかがでしたか?皆さんに聞くと、部屋のベランダから見ていた人は見逃したとおっしゃる。ほんの一瞬の炎のマッターホルンは、凝視していないと難しいことがわかる。へなおじさん、妙高山の朝焼け(朝の炎)は見たことがあるが、これで、提携している二つの街の代表的な山の朝焼けを見たことになる。
朝食後手荷物はホテルに残したまま、ツェルマットの鉄道駅まで行く。その鉄道駅の前に、ゴルナーグラート鉄道の始発駅がある。
アルプスの山、すべて見放題という意味で、世界でも屈指の展望台であるゴルナーグラート展望台まで一気に登ることのできる登山鉄道の始発駅なのだ。
開業は1898年というから、日本なら明治31年、開業して110年を上回る古い鉄道である。

標高1600メートルのツェルマットの駅から、わずか30分あまりの間に3089メートルの標高のゴルナーグラート展望台駅まで、標高差1500を一気に登っていく。そんな傾斜を普通の鉄道で登ることは不可能、ということで、もちろんラック&ピニオンのアプト式の鉄道である。
朝早いので観光客はまばら、これがシーズン中の昼間なら観光客でごったがえしているという。
幸い始発電車に一番乗り、マッターホルンビューは右側の座席ということで、右側に陣取る。
今日は雲一つ無い上天気、一年を通じても稀な上天気という。これが曇天でマッターホルンが見えない場合は左側に陣取りなさいと地球の歩き方に書いてある。もちろん今日は右側がベストポジション。
 天気が良すぎてマッターホルンが近くに見えすぎるという感じである。遥か彼方にあるはずなのに、手を伸ばすと頂上に手が届きそう、そんな感じである。山男の皆さんも、頂上を征服しようと思ったとき、天気が良いとすぐそこに見えて、感覚が狂ってしまうのではなかろうかと思えてくる。
天気が良すぎてマッターホルンが近くに見えすぎるという感じである。遥か彼方にあるはずなのに、手を伸ばすと頂上に手が届きそう、そんな感じである。山男の皆さんも、頂上を征服しようと思ったとき、天気が良いとすぐそこに見えて、感覚が狂ってしまうのではなかろうかと思えてくる。
あっという間にゴルナーグラート展望台駅に到着する。
雪が積もっていて歩くのは気を付けなければならない。
マッターホルンからこちらにかけて、ごつごつした万年雪が見えている。聞くと氷河だという。確かに雪の間にエメラルド色の氷が見えている。
 我々と同じ一番電車に乗ってきたセントバーナードも仕事を開始した。セントバーナード、気付けのウイスキーのミニ樽を首に巻いて、アルプスでの遭難者を救助する犬である。
我々と同じ一番電車に乗ってきたセントバーナードも仕事を開始した。セントバーナード、気付けのウイスキーのミニ樽を首に巻いて、アルプスでの遭難者を救助する犬である。
もちろん、救助犬としての仕事ではなくて、観光客と一緒に写真に納まり、その写真を現像焼き付けしてふもとのツェルマットの売店で売るという仕事である。そのため、観光客が勝手に写真を撮ると、写真を撮らないでくれと飼い主が騒いでいる。ただ、何度もここにくるHさんとはお友達、そのツアーのメンバーということで、我々だけは大目に見てくれている。まだ生まれて1年未満、訓練中のセントバーナード犬ということで、動きはあまりきびきびしていない。観光客に抱かれてまったりしている。
|
 積雪に注意しながら展望台に登っていく。 積雪に注意しながら展望台に登っていく。
アルプス最高峰のモンブランは見えないが、360度どの方向にも雪をいただくアルプスの山々が見えている。
アルプス第二の標高を誇るモンテローザが見えている。4634メートルである。そのモンテローザから標高4478メートルのマッターホルンまでの間に、4000メートルを超える白い峰が5つも見えるという。確かにすぐそこに見えているのだが、どの山がどの山か、区別がつかないところが寂しいところ。
外国から来た夫婦が写真を撮ってくれるという。キレイに撮ってくれたのでお礼をいうと、Where are you
from?日本と答えて彼等の出身地を聞くとUSAだという。どの州かたずねると、アラバマだという。
ということで、へなおじさん得意のオースザンナを英語で歌う。
http://www.youtube.com/watch?v=FCjEaqpHQDE&feature=related
負けじとアラバマからの夫婦もへなおじさんと合唱、オースザンナの日米合唱になり大はしゃぎ。
 思わぬ日米友好の合唱のあとは少し疲れてくる。標高が高いので酸素が薄く、急に大はしゃぎするのは、年寄りには辛いのだ。
思わぬ日米友好の合唱のあとは少し疲れてくる。標高が高いので酸素が薄く、急に大はしゃぎするのは、年寄りには辛いのだ。
ということで、展望台の下の建物に行く。ここはホテルになっていて、アルプスの山々の展望を目当てに泊まる方も多いという。ただ、酸素が薄ので、呼吸が苦しいのが玉にキズという。
レストランがあるのでホットチョコレートを注文する。マッターホルンを眺めながらのホットチョコレートはことのほか美味しい。
|
ゴルナーグラート鉄道でふもとのツェルマットに降りて自由時間。量り売りの生チョコレートを購入、美味しいのですぐに食べてしまう。またこの近くのグリュイエールという街で造られているグリュイエールチーズを売っていたので、お土産屋さんでなくて地元の人が行くコープで購入する。これは日本へのお土産。昼食を食べ、昨日宿泊したホテルに戻って荷物を受け取り、列車で一駅乗ってバスの待つ駐車場に到着する。
インターラーケンまで、地図上の直線距離は短いが、山脈にはばまれているので、かなり大回りしている模様で、レマン湖のほとりを走行している。天候は徐々に下り坂、雨模様になってきて、バスの窓からの視界も悪い。
 インターラーケンに到着する。 インターラーケンに到着する。
スイスアルプスを代表する3つの山、アイガー、メンヒ、ユングフラウ、その登山口となっているベルン州の丘陵地帯をベルナーオーバーラントというが、このインターラーケン、トゥーン湖と、ブリエンツ湖の間にある観光地を巡る拠点となる主要な街である。
インターは、「間」、ラーケンは「湖=lake」、つまり湖の間という、そのまんまの名称の街である。
ヴィクトリア・ユングフラウホテルの前で一旦解散、そこらを少し散策する。ホテルの前は広大な芝生の広場になっていて、遥か先にはユングフラウのふもとが少しだけ見えている。
 この馬車が通る道を挟んでホテルからユングフラウが見えるというのが格式あるホテルの「売り」。ということで、このホテルがホテル前の広大な敷地を購入して広場にしたのだという。
この馬車が通る道を挟んでホテルからユングフラウが見えるというのが格式あるホテルの「売り」。ということで、このホテルがホテル前の広大な敷地を購入して広場にしたのだという。
残念ながら少し小雨模様で、ユングフラウの山頂は雲に隠れてしまっている。
マッターホルンで運を使い果たしてしまったのかなー、といいながら、いつまでもユングフラウの方向を見つめるのだが、残念ながら雲は晴れそうもない。
売店でカウベルを購入する。日本で山菜を採るときの熊よけの鈴を先日上州屋で2つ買ったのだが、あまりに良い音だったので、3つ目の熊よけの鈴として買ってしまったもの、スイスの国旗がデザインされて見た目もカワイイ。
 街を散歩すると高山の花、あのエーデルワイスが花屋さんで売られている。山で滅多に見られない稀少な花を見つけるとうれしいのだが、これだけ密集して植えられていると、ありがたみがない。
街を散歩すると高山の花、あのエーデルワイスが花屋さんで売られている。山で滅多に見られない稀少な花を見つけるとうれしいのだが、これだけ密集して植えられていると、ありがたみがない。
もともとエーデルワイス、近づいてよくよく見ると、そんなに綺麗な花でもないのである。
時間になったので、カジノ・クアザールのレストランに急ぐ。
部屋にはいると外は大雨になってきた。
 レストランの前方は舞台になっていて、ショーを見ながら夕食をいただくという趣向。客席は世界中からの観光客の皆さんであふれている。
レストランの前方は舞台になっていて、ショーを見ながら夕食をいただくという趣向。客席は世界中からの観光客の皆さんであふれている。
女性のヨーデルははじめて聴いたが、見事である。アルプホルンだけではなく、スプーンをふたつくっつけたようなカスタネット、大小様々なカウベルなどの演奏も楽しい。
また、陶器のボールの中に2つのコインを入れ、それをグルグル回しながらの演奏もユニークである。
へなおじさん、ウイリー沖山のヨーデルなかでも「山の人気者」が大好きである。じじいになって声がでにくくなってしまったが、舞台に登って歌いたくなってきた。
http://www.youtube.com/watch?v=lt09kSqY0cI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=foyNWSNyIgg&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=t7XSgK3snuw&feature=related
|
インターラーケンでのフォークロアショー、いかにもスイスらしいアルプホルンの演奏と、ヨーデルの歌声は最高の思い出である。
ここからグリンデルワルトまでは20キロ、1時間ほどの道のりである。ブリエンツ湖を左に見ながら谷あいの道をぐんぐん標高を上げていく。
左手にはアイガー、メンヒ、ユングフラウというアルプス3山が見えているはずであるが、雨に煙って雲も厚く、景色はほとんど見えない。数年前、洪水で日本からのお客さんが孤立し、ヘリコプターで救出されたというどん詰まりの山道を、グリンデルワルトに向かっているのである。ヘリに乗ってアルプス3山を見たいなどと、へなおじさん、不穏な発言をしてましおばさんに叱られる。
 バスはグリンデルワルト駅前の広場に到着する。 バスはグリンデルワルト駅前の広場に到着する。
駐車場の前には日本人向けの観光案内所がある。外は明るいが時間は遅い。もちろんこんな時間に係の人はいないが、いかに多くの日本人が訪れる街であるか、日本語表示の観光案内所を見ただけでわかるのがうれしい。
この脇の道を登っていくとシュレックホルン(標高4078m)、ヴェッターホルン(標高3701m)の方向という。山のふもとはかすかに見えているが、上の方は雲に隠れている。
すぐそこに見えているのは、アイガーの北壁から東の壁の方向である。明日この下を掘ったトンネルを登ってユングフラウ山の中腹まで行くことになっている。
 アイガーの北壁は見えているが、天気が良くてもここからユングフラウ(標高4158m)を望むことはできないという。アイガー(標高3970m)やメンヒ(標高4107m)の陰に隠れているためである。
アイガーの北壁は見えているが、天気が良くてもここからユングフラウ(標高4158m)を望むことはできないという。アイガー(標高3970m)やメンヒ(標高4107m)の陰に隠れているためである。
アイガー北壁は前人未踏の壁であったが、今では多くのアルピニストが普通に挑戦する壁になっているという。目を凝らせば今日も中腹にビバークしている山男達の光が見えているハズですよという。近くは見えないが遠目は効くへなおじさん、じっと暗闇に目を凝らすものの、雲が厚くて残念ながら見えてこない。
今日のホテルはその駅前広場の真ん前、絶好の立地のホテルである。残念なのはみぞれまじりの雨と厚い雲のため、肝心の雪山が見えないことである。スイスに来ているのにアルプス3山の雄姿が見えないというのは誠に情けない。スイスは駆け足で通り過ぎるのは無理な国であることを実感する。
|
 朝からみぞれがちらついている。今回のスイス旅行の中で最大の目玉であるユングフラウヨッホの観光なのに、前途多難な夜明けである。
朝からみぞれがちらついている。今回のスイス旅行の中で最大の目玉であるユングフラウヨッホの観光なのに、前途多難な夜明けである。
多くの安いスイス旅行では、ユングフラウヨッホの観光がオプションになっていて、日本円で2万円ほどのツアー代金を支払って参加するようになっていることが多い。
我々のツアーは結構お安い代金のツアーであるのだが、ユングフラウヨッホ観光が付いていてお得感満載だったのに、残念な天候である。
グリンデルワルトの鉄道駅まで徒歩2分、7時45分発の始発電車でクライネシャイデック駅に向かうことになる。
クライネシャイデックの標高は2000mを超えている。みぞれは本格的な雪になって、吹雪きになってきた。せっかくの登山電車なのに、窓からは何も見えない。
 クライネシャイデックで、乗り換えのために下車する。今日も首にウイスキーのミニ樽を付けたセントバーナードの出勤である。成犬はもう少し大きいはずだから、この子はまだ子どもなのであろう。ちょこんと座ってはいるのだが、今日は景色が見えないから商売は厳しそうである。
クライネシャイデックで、乗り換えのために下車する。今日も首にウイスキーのミニ樽を付けたセントバーナードの出勤である。成犬はもう少し大きいはずだから、この子はまだ子どもなのであろう。ちょこんと座ってはいるのだが、今日は景色が見えないから商売は厳しそうである。
10分ほど経過するといよいよアプト式の列車がホームに入ってくる。列車に乗りこむが、車内は冷え冷えしている。
列車が動き出すとすぐに外は真っ暗になる。
アイガーの北壁を掘り進んだトンネルに入ったのである。今から100年前のスイス人、アイガーの北壁を登るのはアルピニスト以外には無理である。特に冬は経験を積んだ山男でも難しい。トンネルを掘って電車を通せば、世界中からの観光客が軽装で登れるぞ。とにかくそういうスイス人の発想がすごいトンネルである。外が暗いので見えないが、とにかくものすごい傾斜角度で坂道を登っている。
 列車はアイガーの壁の中のアイガーバント駅に到着する。標高は2865mである。列車はここでしばらく停車する。オレンジの服を着た保線の担当の人達と記念撮影をする。
列車はアイガーの壁の中のアイガーバント駅に到着する。標高は2865mである。列車はここでしばらく停車する。オレンジの服を着た保線の担当の人達と記念撮影をする。
ここから少し歩くとアイガーの北壁に穴が開けられていて、外の景色が見えるという。
ということで、通路を進んでいく。
通路が明るくなってくる。天気が良い日にはここで下車してアイガーを登る人もいるという。今日はそういう登山家はいないようである。
 アイガーの壁にはガラス窓がはめられている。天気の良い日にはここからトゥーン湖など、スイスの美しい街や湖が箱庭を見るように見えるというのだが、今日は少し先のアイガーの壁すらも見ることができないほどである。
アイガーの壁にはガラス窓がはめられている。天気の良い日にはここからトゥーン湖など、スイスの美しい街や湖が箱庭を見るように見えるというのだが、今日は少し先のアイガーの壁すらも見ることができないほどである。
雪が風に巻き上げられて下から上に降っている。巻き上げられた雪がガラス窓に貼り付いて、更に視界を妨げる。
そろそろ列車の発車時刻である。ということで、駆け足で列車に戻る。
|
 アイガーの壁をくり抜いて掘られた急角度のトンネルを、アプト式の我が列車はあえぎながら登っていく。 アイガーの壁をくり抜いて掘られた急角度のトンネルを、アプト式の我が列車はあえぎながら登っていく。
トンネルはアイガー、メンヒを抜けて、ユングフラウに向かっているはずである。
アイガーの標高は3970m、メンヒが4107m、ユングフラウが4158mと、いずれも我が国の最高峰富士山の標高を凌いでいる。
このアイガー、メンヒ、ユングフラウをアルプス3山というのだが、トンネルはこの下を掘り進んでユングフラウの中腹、標高3454mのユングフラウヨッホに向かっているのである。
トンネルの途中でいくつもの駅があって、登る途中にはそれぞれに列車は5分ほど停車する。それぞれには展望のための窓が開けられていて、下が見られるようになっている。
列車はアイスメーア駅に到着する。標高は3160m、空気が薄くなってきた。ここの壁にくり抜かれた窓からも荒天のため何も見えない。
トイレの近いへなおじさん、駅にトイレがあるので用を済ませる。さすがスイス、100年も前に掘られた施設なのに水洗である。標高3000メートルを超えてなお水洗、凄すぎる。
 ふたたび列車に乗り込み、最後の坂道を登っていく。 ふたたび列車に乗り込み、最後の坂道を登っていく。
ついに我が列車は終着のユングフラウヨッホ駅に到着する。赤い車体に黄色のストライプ、へなおじさんが30年ほどお世話になった地下鉄の丸ノ内線を思い出す。
この駅もトンネル内である。ここで、添乗のHさんの指示で耳太郎を装着する。この耳太郎、阪急の旅で配られるもので、ガイドさんがハナシをすると無線でその話し声が聞こえてくるというスグレモノ。但し、ガイドさんの声がいつまでも聞こえてくるので、うっかりすると迷子になりやすい。
Hさんが点呼すると、早くも3人ほどが行方不明である。まあ行方不明でもこれからの道は一方通行、ということで、皆さんHさんのあとを付いて歩き出す。
 ユングフラウヨッホ、ヨーロッパの最高地点、3454mという看板が見えたので、ここで記念撮影。 ユングフラウヨッホ、ヨーロッパの最高地点、3454mという看板が見えたので、ここで記念撮影。
こんな吹雪の中を、きわめて軽装備で標高3454mという富士山山頂に匹敵するような高さまであっというまに登ってこられるところが、すごい、凄すぎるのである。
今日はお客さんが少ないというものの、それでもコンコースは結構混み合っている。
寒いので速く歩きたいのだが、空気が薄いので駆け足では呼吸が苦しくなる。
|
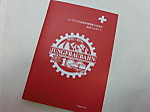 ツアー客に赤い冊子が配布される。ユングフラウヨッホまでの鉄道乗車記念のパスポートである。 ツアー客に赤い冊子が配布される。ユングフラウヨッホまでの鉄道乗車記念のパスポートである。
実は標高3454mのユングフラウヨッホまでの登山鉄道、今年2012年が開通100周年の記念の年。その記念のパスポートと書いてある。
日本ではというか、世界の先進国の鉄道が蒸気機関車の時代、ようやく京都に我が国はじめての電車が走り始めた1895年(明治28年)、ヨーロッパの小国スイスの皆さんはものすごいことを考える。
アイガーにトンネルを掘れば、ユングフラウヨッホまで登れるのではないか?トンネルなら吹雪でも猛烈な風が吹いても登ることができる。ロープウェイならそんなに難しくないかもしれないが、ロープウェイでは天候に左右される。それに、そんなにたくさんの観光客は乗せられない。
トンネルに蒸気機関車は無理か、トンネル内に煙が充満してせっかくの景色が台無しである。ならば、電気モーターならいいのでは、でも250パーミルなどという勾配の坂道をどう登るか?歯車を噛み合わせて登ったらいいんじゃないの?
そんな途方もないことを考えて掘り始めたのである。固い岩盤と永久凍土に悩まされ、しかも資金難、それでも16年もの歳月をかけてようやく完成したのが1912年、今からちょうど100年前、アイガーの北壁が征服される26年も前のことである。
 アイガーの北壁を登って尾根づたいにこなくても、ザイルにハーケン、ピッケルを持って危険を冒さなくても、軽装備でヨーロッパ最長のアレッチ氷河まで来られるようになったのである。
アイガーの北壁を登って尾根づたいにこなくても、ザイルにハーケン、ピッケルを持って危険を冒さなくても、軽装備でヨーロッパ最長のアレッチ氷河まで来られるようになったのである。
エレベーターを登って標高3571mの地点に建てられているスフィンクステラスというガラス張りの建物にたどり着く。
ガラス越しにアレッチ氷河が見えるはずの方向を凝視する。猛吹雪で何も見えない。ここまで来て何も見えないのか?
スイスの観光番組などを見ていると必ず映しだされるのがここからのアレッチ氷河のながめである。
 テラスまで出てみればもう少し見えるんじゃないの?ということで回転ドアを押し開ける。強風で東京ドームの回転ドアの感じである。
テラスまで出てみればもう少し見えるんじゃないの?ということで回転ドアを押し開ける。強風で東京ドームの回転ドアの感じである。
外に出ると床は金網である。金網越しに下から雪が吹き上げてくる。マリリンモンローの地下鉄どころの騒ぎではない。
猛烈に冷たい空気に吹き上げられて、下からの雪という残念な結果である。
アレッチ氷河どころか、目が開けておられない、1分も経過しないうちに全身が凍傷になりそうな猛烈な寒さ、ということで部屋に逆戻りである。
天気が良ければアレッチ氷河に降りていけるなどと書いてあるが、今日出たらすぐに遭難しそうで無理である。スイスはまた来なければならない。
|
 ということで、ふたたびエレベータに乗って駅の建物に戻ってくる。 ということで、ふたたびエレベータに乗って駅の建物に戻ってくる。
建物には巨大なスクリーンがあって、アルプスの絶景が映しだされている。天気が良ければここからこういう景色が見えますよという映画である。スクリーンが孤になっていて、景色が目の前に見えるような映像である。
先ほど行ったスフィンクス展望台の上に巨大なドームがあった。ここがヨーロッパ最高峰の測候所とのことである。街の光も届かず澄み切った空気のユングフラウヨッホはまさに測候の最適地、1982年中性子線の爆発的な増加を観測して太陽活動が活発化したのを世界で最初につかんだのがこの測候所だという。
 氷の宮殿があるというので行ってみる。氷河の中をくり抜いたトンネルである。何千年、何万年前の氷だろうか、触れると固くて冷たい。
氷の宮殿があるというので行ってみる。氷河の中をくり抜いたトンネルである。何千年、何万年前の氷だろうか、触れると固くて冷たい。
毎日多くの観光客が通るが溶けてしまうことはないという。
但し氷河である。だから1年に数センチづつ動いている。従って、何年か先にはまた新しいトンネルを掘らなくてはならないという。今触れているトンネルの壁は、100年後くらいには溶けてなくなっているか、あるいはアレッチ氷河の一部になってもう少し標高の低いところに留まっているのかも知れない。
氷河をそのまま掘り進んだトンネルである。ということで、床ももちろん氷である。滑らないように注意しながらゆっくり歩いている。
 氷に埋め込まれた小さいがきれいな看板がある。 氷に埋め込まれた小さいがきれいな看板がある。
ユングフラウ、ヨーロッパの最高地点と書いている。ここらはドイツ語圏、表記は英語である。ということで、世界からやってくる観光客に向けて造られた看板である。
この通路の途中にも外への出口がある。ここを出るとプラトーと呼ばれている展望台まで行けるという。そこで雪の感触を自分の手で確かめて下さいと書いてある。
もちろん今日外に出たら、プラトーに到着する前に遭難である。
 駅の建物に戻ると赤いポストがある。どこかで見かけたポスト、そうまさしく日本で現役として使われていた赤くて丸い郵便ポストである。富士山5合目郵便局との提携を記念して日本から贈られたとのことである。
駅の建物に戻ると赤いポストがある。どこかで見かけたポスト、そうまさしく日本で現役として使われていた赤くて丸い郵便ポストである。富士山5合目郵便局との提携を記念して日本から贈られたとのことである。
売店では絵はがきや切手も販売されている。ここで投函すれば日本まで届けられる現役のポストである。
富士山の山頂にもポストがあるので、このポストが世界最高峰のポストではないと思われるが、富士山頂郵便局の開設は富士山の山開き以降、ということで、今もたれているユングフラウヨッホのポスト、これが世界最高峰の「常設」郵便ポスト、かもしれない?
|
 100年前の工事の状況が写真で展示してある。強固な岩盤を手彫りで進んだスイス人技術者が誇らしげに写っている。
100年前の工事の状況が写真で展示してある。強固な岩盤を手彫りで進んだスイス人技術者が誇らしげに写っている。
ユングフラウヨッホからの下りの列車は、トンネル内の途中駅で停車はしない。そのままクライネシャイデック駅まで降りてくる。
外は依然として雪である。しかもこの雪、しばらく前までは緑の草原だったところに突然の寒波でまた一面を白くした雪だという。どこまで運が悪いんでしょうか?
本日の昼食はこのクライネシャイデックの駅の中にあるレストランでいただくことになっている。
 この駅、3方向からの線路が合流する地点にあるので、いろいろな列車が入線してくる。 この駅、3方向からの線路が合流する地点にあるので、いろいろな列車が入線してくる。
雪まみれのきれいなアルミボディの列車が入ってきた。ヨーロッパのどこかの街のトラムのような美しい車体である。ということで、2人で記念撮影する。
昼食はポタージュスープ、メインは、アルペンマカロニ、マカロニにクリームソースがかかっている。それにリンゴジャムにガーリックトースト、奇妙な取り合わせだがまあまあの味。
お土産屋さんで孫の室内履きを購入して、ふたたびインターラーケンに戻る。
 インターラーケンに近づくとさすがに標高が低くなったためか雪はやみ、雨となり、やがて太陽が雲間から覗くようになる。
インターラーケンに近づくとさすがに標高が低くなったためか雪はやみ、雨となり、やがて太陽が雲間から覗くようになる。
トゥーン湖のクルーズのはじまりである。向こうからきれいな白い船体の観光船がやってくる。
我々は2等で下のフロア、ホットココアを注文していただく。ゴルナーグラート展望台でマッターホルンを見ながらいただいたホットココアの方が美味しかったが、それは標高のせいか?
まあ、あまり贅沢は言ってはいけない。
 やがて開聞岳のような山が見えてくる。聞くとニーセンという山、標高は2400mもあるとのことでびっくり。 やがて開聞岳のような山が見えてくる。聞くとニーセンという山、標高は2400mもあるとのことでびっくり。
確か同じような形に見える鹿児島の開聞岳は標高1000m以下。開聞岳が海からいきなり立ち上がっているので、実際の標高よりは高く見えるのだが、それにしても標高が倍以上の山というのはオドロキだ。
途中のシュピーツという波止場で下船すると、我々のバスがお出迎え、首都ベルンに向けて出発する。
|
 スイスの首都ベルンに到着、まずは高台のバラ公園にバスは停車する。 スイスの首都ベルンに到着、まずは高台のバラ公園にバスは停車する。
馬蹄型に弯曲するアーレ川に囲まれた世界遺産ベルンの旧市街、赤い屋根の中世の住宅地がそのまま残っている。
ヨーロッパの主要都市が度重なる戦乱で廃墟と化す中、永世中立を保ったスイスの首都は無傷で残ったのである。
もともとは木造の家並みであったが、1405年の大火で焼失、石造りの建物群に建て直され、それが今に残っている。
 ベルンの旗は黒いクマのマーク、クマがシンボルなのである。この地に進出してきたツェーリンゲン公、狩りで最初に射止めた動物をこの地の名前に付けようと宣言する。
ベルンの旗は黒いクマのマーク、クマがシンボルなのである。この地に進出してきたツェーリンゲン公、狩りで最初に射止めた動物をこの地の名前に付けようと宣言する。
最初に捕まったのがクマ、英語ではベア、ドイツ語でベーレン、だからスイスの首都はベルンとなったという。もし最初に捕まったのがウサギだったら、とか、猪だったらとか想像すると楽しい。
バラ公園から降りて旧市街に入ってくる。
クマ公園と名付けられた場所でしばらく解散ということで、クマがいるという場所に行く。
 ベルンのシンボルのクマがごろごろしている。 ベルンのシンボルのクマがごろごろしている。
質量は相対的である、時間の進み方は速度によって違ってくるなどという、凡人には説明されても理解できない相対性理論を発表したアルベルト・アインシュタイン、ドイツ生まれの理論物理学者が残した理論は現代科学の基礎をなしているが、彼はスイスのチューリッヒの大学を出て、ここベルンに住居を構え、特許局に勤務していたという。
彼がここに住んでいた3年間は光電効果の理論、ブラウン運動の理論、特殊相対性理論を発表するという奇跡の年といわれている。
これから見に行く時計塔の近くにそういう奇跡を生んだ家と彼が思索を巡らしたデスクがあるというが、残念ながら今回のツアーのコースには入っていない。
|
 夕食はベルンの市内の予定である。市の繁華街に移動すると、若者のグループがたむろし、奇声をあげながら騒いでいる。
夕食はベルンの市内の予定である。市の繁華街に移動すると、若者のグループがたむろし、奇声をあげながら騒いでいる。
何でもヨーロッパのサッカーリーグの試合が終わったばかりで、球技場から出てきたサポーターが徒党を組んで騒いでいるとのことである。
警察が出て取り締まりをしているのだが、治安が悪くなっている。ということでHさん、サポーターを刺激しないようにしてくださいと注意して、一旦解散となる。
道路の両脇には頑丈な開き戸がいくつもある。聞くと、地下への入り口なのだという。地下には部屋があって、レストランとかバーとか、多くの飲食店が店を出していて、準備が整えばここを開けてお客さんに入ってもらうとのこと。
 そろそろ午後6時、時計塔のからくり時計は5時56分に動き始めるというので、通りの端にある時計塔に我がツアー客の皆さん、世界各地からの観光客の皆さんが集合してくる。
そろそろ午後6時、時計塔のからくり時計は5時56分に動き始めるというので、通りの端にある時計塔に我がツアー客の皆さん、世界各地からの観光客の皆さんが集合してくる。
この時計塔、1218年から時を刻んでいるというが、今見ている天文時計とからくり時計は1530年の製造、以来500年近くにわたって時を刻み続ける由緒ある時計である。
今何時というのは把握しにくいが、太陽や月、それぞれの星の動きがわかるようになっている精密な天文時計である。さすがに時計のスイスの面目躍如、この時代にこれほど精密な時計を造る技術に感服する。となりのからくりの人形の動きもユーモアに富んでいて楽しいが、動き出したと思ったらあっというまに終了する。
 いよいよ本ツアーの最後の晩餐である。コルンハウスケラーと呼ばれる由緒あるレストランの中に入っていく。穀物倉庫を改装したという建物の中はいかにも高級レストランの雰囲気。
いよいよ本ツアーの最後の晩餐である。コルンハウスケラーと呼ばれる由緒あるレストランの中に入っていく。穀物倉庫を改装したという建物の中はいかにも高級レストランの雰囲気。
ここでHさん、ドライバーがどこかに行ってしまったというので探しに行く。するとひょうっこりドライバーが戻ってくる。このドライバー、ドイツ人だが英語は通じる。Hさんが君を捜しているので、携帯電話で電話をしなさいと告げると、わかったという。
デザートを食べ、へなおじさんがトイレに行ったところへ、HさんからレストランにTELが入る。こんどは松戸の英語ペラペラご夫婦の出番。
結局はドライバーが電話をしなかったことが判明、怠惰なドイツ人のおかげで、英語ができる3人が振り回される結果に。日本経由の国際電話になるHさんあての電話など、ドイツ人はかけたりしませんというお粗末。
|
夕食を食べたベルンからチューリッヒまでは127キロ、ホテル到着は午後9時をすぎる。
 ここチューリッヒ、商工業、金融、文化、芸術の中心で、スイス最大の都市である。 ここチューリッヒ、商工業、金融、文化、芸術の中心で、スイス最大の都市である。
我々のツアー、予算の関係で往復ともドイツのルフトハンザ航空を利用する。チューリッヒから日本まではスイス航空で直行便があるが、残念ながらルフトハンザのここからの直行便はない。
ということで、チューリッヒ観光は、ありません。
そこで、へなおじさんの海外旅行必需品、お荷物のご紹介。
まずは、秤(はかり)、今回のルフトハンザのエコノミークラスの荷物は23キロ、へなおじさん、荷物に余裕があれば2L入りのお茶を持参する。旅の途中で飲んでしまうので、行程が消化されるにつれて荷物は軽くなる。
 従って秤などは持ってこなくても良いのであるが、これを持ってくると帰りの空港でひっぱりだこ。 従って秤などは持ってこなくても良いのであるが、これを持ってくると帰りの空港でひっぱりだこ。
皆さんお土産買い過ぎで、スーツケースは重量オーバー、重量オーバーには特にドイツのルフトハンザは厳しいというウワサ。少しの重量オーバーで数千円の課徴金を取られてしまうので、皆さん、へなおじさんのところに、秤を借りに群がってくるのである。
次がWi−Fi電波の発送機器。最近はWi−Fi電波を送信しているホテルが増えてきたが、未だ有線のところも多い。
そこでこの機器の出番となる。AC電源をお借りして(もちろんコンセントの形状が日本と違うのでアダプタが必要となる。電圧は100〜240V対応で海外の高電圧にもOK)イーサネットケーブルをこれにつなぐと、Wi−Fi電波が発せられる。
 そのWi−Fi電波をiPhoneで受ければ、基本無料でインターネットが可能となる。 そのWi−Fi電波をiPhoneで受ければ、基本無料でインターネットが可能となる。
それ以外に、電気の延長ケーブル、風呂とか洗面所のゴムがないことが多くて、お湯が貯められない、水が貯められないから洗濯が洗面所でできないという場合に備えての、ゴルフボール(ストッキング入り、ストッキングに入れて使わないと、ゴルフボールが取れなくなる)、それにゴルフボールでは不可の場合の傾斜付きの風呂栓(これは使う機会がきわめて多い)。
それに、スイスアーミーナイフ、いろいろ組み込まれている道具の中で、はさみと、ナイフ(果物の皮むき)の出番が多い。但し、スーツケースに入れ忘れ、手荷物にしたりすると、空港のセキュリティで没収されてしまうので、注意が必要である。
電圧を変換するトランスを持ってくる方も多いと聞くが、シェーバー、ドライヤー、充電器などの電気器具を海外仕様のものにすれば240VまでOKなので、へなおじさんはトランスは不要である(しかもトランスは重い)。
 それに、ホテルで使わずにはおられない道具がこの湯沸かしとマグカップ。 それに、ホテルで使わずにはおられない道具がこの湯沸かしとマグカップ。
先進国ならミネラル分が強いことをガマンすれば、水道水でもOK、できればエビアンなどの水をこれで沸かして、コーヒーとか紅茶をいただく。
マグカップ1杯の水は数十秒で沸騰する。
ましおばさんが日本で入院した時にも使ったから、病院グッズにも欠かせないのがこの湯沸かし。
それにTOTO純正の携帯用ウォシュレット、いずれも軽量で荷物にならない。
|
 いよいよ今回のツアーの最終日、ホテル前で添乗のHさんと、ドイツ人のドライバーがご夫婦で参加のお客さんと記念撮影。
いよいよ今回のツアーの最終日、ホテル前で添乗のHさんと、ドイツ人のドライバーがご夫婦で参加のお客さんと記念撮影。
このホテルに宿泊していたインド人ご一行、朝食のバイキングで持参したタッパウェアに果物詰めてたなどとウワサしながら出発である。インドも発展途上国、中国人にも負けないくらいのツラの皮の厚さだ。
バスはチューリッヒからボーデン湖の横を通って北上している。
そろそろオーストリアの国境だ。
 スイスにもチェコ製のシュコダのクルマが走っている。スイスは国連には加盟しているがEUには加盟していないので、EUのマークは付いていない。そのかわりに赤地に白い十字のスイス国旗のシンボルが描かれている。
スイスにもチェコ製のシュコダのクルマが走っている。スイスは国連には加盟しているがEUには加盟していないので、EUのマークは付いていない。そのかわりに赤地に白い十字のスイス国旗のシンボルが描かれている。
EUには加盟していないがシェンゲン協定締結国なので国境はノンストップ、但し、スイスのクルマには、白地の楕円の中にCHと書かれている。
ドイツ語でもイタリア語でも、あるいはフランス語でも、はたまた英語であってもロマンシュ語であっても、国名の頭文字はSでいいはずだが、ここはさすが4カ国語が公用語のスイス、ラテン語の国名である、コンフェデラチオ・ヘルベチカの頭文字、CHとしているのだ。スイスがヘルベチカとは、全く知りませんでした。
 バスはオーストリアからドイツに入り、ミユンヘン国際空港に到着する。 バスはオーストリアからドイツに入り、ミユンヘン国際空港に到着する。
座席は中央席であったが、窓際の2人席が空いているというので、替えてもらう。
手荷物検査でましおばさんがひっかかり、全身をチェックされている。笑って見ていると、こんどは、へなおじさんの荷物を取りだして、女性の係員が集まってきてワイワイ騒いでいる。まるで、爆弾でも見つけたけど、どうしましょうという感じである。
日本人は英語などしゃべれないハズと決め込んで、遠巻きにして、今にも機械を分解しそうな勢いである。
 仕方がないので歩み寄って、英語で説明する。「君たちは、んこが手に付いたときは、紙で拭くか、手を洗うか?」「手を石鹸で洗います」という返事である。「君が手にしている機械は、用を足したあとで、水を噴射して、尻を洗う機械である、使っているところを見せようか?」というと、びっくり仰天、日本にはこんなにすごい機械があるのかと、感心しながらも、汚いものを手にしてしまった、という感じで投げてよこす。
仕方がないので歩み寄って、英語で説明する。「君たちは、んこが手に付いたときは、紙で拭くか、手を洗うか?」「手を石鹸で洗います」という返事である。「君が手にしている機械は、用を足したあとで、水を噴射して、尻を洗う機械である、使っているところを見せようか?」というと、びっくり仰天、日本にはこんなにすごい機械があるのかと、感心しながらも、汚いものを手にしてしまった、という感じで投げてよこす。
トラベルウォシュレット、へなおじさんは10年ほど前から海外で愛用している。多くの日本人も愛用しているハズであるが、ミユンヘン空港では初めての「発見」であったと思われる。
順調に飛行して翌日成田着。今回もお疲れ様でした。
|
|