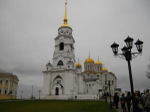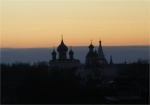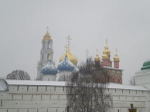ロシア旅行
|
 ロシア旅行を終えて、昨日、成田に帰国した。ロシアでは、こんなスタイルで寒さを凌いでいたが、東京はむしろ暑いくらい、車の中では半袖のTシャツ1枚、クーラーをつけて帰宅した。
ロシア旅行を終えて、昨日、成田に帰国した。ロシアでは、こんなスタイルで寒さを凌いでいたが、東京はむしろ暑いくらい、車の中では半袖のTシャツ1枚、クーラーをつけて帰宅した。
パック旅行の8日間に接したロシア人は、皆さん親切、特にモスクワ、サンクトペテルブルグの2人のガイドさん、人柄も良く親切で、ロシアの人たちに対する感覚が少し良くなったような気がする。
日本人のロシア人に対する感覚は、最近の尖閣問題で異常な対応を見せる中国人ほどではないにしても、かなり悪く、今回の旅行の前に接した友人の大半が、「ロシア人には気を付けろよ」「あんな国で、カネをいっぱい落としてくるんじゃないぞ、土産もいらないぞ」などと言っていた。
ロシア人に対する日本人の感覚は、日露戦争で闘った相手ということもあるが、やはり第二次世界大戦のどさくさに紛れて瀕死の日本人を痛めつけた、その記憶が大きい。
アメリカが1045年の8月6日、広島に原爆を投下して日本の敗戦が決定づけられたわけであるが、その2日後の8月8日、当時のソ連は駐ソ大使館に宛て、対日宣戦布告を行う。しかも、日本は中立条約を締結していた相手国。国と国との約束を一方的に破棄し、国土の防衛すらも出来なくなった瀕死の状態の我が国に対して戦争を仕掛けてきたのである。ソ連に駐在していた佐藤大使は本国に連絡しようとしたが電話線も切断されていて連絡できず、日本の前線基地は、いきなりソ連が攻めてきたという状態で大混乱になった。
日本は8月14日にポツダム宣言を受諾、もともと防衛能力のなくなった陸軍が終戦で武装解除しているさなか、ソ連は日本の傀儡国家満州国、日本が支配していた朝鮮半島、日露戦争で手にした南樺太、千島列島に大挙して侵攻し続けた。
つまり、仲良くしようと約束した相手が、ポカポカに殴られ、意識が遠のいて「負けました」と言いながら道に倒れたところにやってきて、殴り続けたのである。
連合国の一員であるアメリカは、さすがにスターリンに対して抗議したそうだが、それでも猛攻はおさまらず、ミズーリ号で日本が降伏文書に調印した2日後まで続いた。
更にスターリンは満州国などに駐留していた日本軍を国際ルールに違反して拉致、極寒のシベリアなどでの強制労働に従事させて、多くを死なせている。
そういう不法な戦争参加で得た北方領土に古くから住んでいた日本人を追い出し、不法占拠を続けて返すそぶりも見せず、更に最近、第二次大戦の戦争終結日を一方的に変更して、不法占拠を正当化しようとしたのである。
へなおじさんがロシア旅行をしていたのは、大統領のメドベージェフが、不法占拠の北方領土を訪問したその最中、駐ソ大使を引き上げて抗議する日本政府の対応は当然である。
共産国家ソ連を解体し、民主国家ロシアを復活させたのに、ソ連時代の一連の不法な行為を正当化する今のロシアの指導者達。まったく鼻持ちならないヤツらである。
でも一般の街の皆さんはみんないい人ばかりの愛すべき国ロシア、これからしばらくロシア旅行記が続きます。
|
今回訪問した首都モスクワも、古都サンクトペテルブルクも、朝夕は渋滞がひどい。モスクワなどは環状道が整備され、道路も広いのに大渋滞、1日目ホテルに到着するのが遅れてしまった。
極東のウラジオスットックなどの街風景をテレビなどで見ると、日本から輸入した使い古した中古車が大半という印象があるが、ヨーロッパに位置する2大都市は、日本でいうなら3000ccを超える新しい普通車が大半で、英仏伊の街にあふれている小型車は少数である。
但し、日本では法律で規制されているスパイクタイヤを履いている車が多いせいか、粉塵がひどく、大半の車は泥だらけである。洗ってもすぐに泥が付くので洗うのは夏だけという。汚れてはいるが、日本でいうなら200万円〜500万円くらいの価格帯の立派な車が揃っている。
中国のような極少数の超金持ち、少数の金持ち、大半の貧乏人という構図ではなく、ロシアでは貧富の格差は少なく、税制がうまく機能していることが、こういう車の行列を見るだけで想像できる。
ベンツ、アウディ、VW、ボルボなどのヨーロッパ車にまじり、トヨタ、日産、スズキ、三菱などの日本メーカー車も数が多い。聞くと、トヨタ、日産、スズキが既にロシアで現地生産をしているという。つまり、ロシア国産の日本車が活躍しているのだ。
車だけではなく、ソニー、日立、NECなどのエレクトロニクスメーカー、コマツ、日立建機などの建設機械メーカーもロシアの工場で、ロシア人従業員が製品を造りだしている。
またサハリン沖の天然ガス、シベリアの石油(日本が存在を確認した油田もある)などの資源も日本が権益を手にしている部分があって、日露の経済交流は活発である。
そんな中のメドベージェフ大統領の北方領土訪問である。昨日も書いたように、ロシアが不法に手にした我が国の領土である。戦争で領土を拡大することは、国際ルールでも禁止されている。
だから日本としては大使を引き上げて抗議せざるを得ないのである。さて、尖閣問題で失態を演じた民主党の外交、どう対処するか国民はもちろん、世界中が見守っている。
強攻策で、今まで営々と築いてきた経済交流やエネルギー政策を台無しにしてはならないし、弱腰で世界中から笑い者にされても将来に禍根を残すことになる。難しい舵取りが民主外交に託されているのである。
恥知らずのスターリンが行った不法占拠の北方領土。スターリンは今やロシア国内でも「バカな独裁者」というマイナス評価の指導者である。共産党一党独裁を放棄し、民主国家に移行したロシア、経済は自由化したが一党独裁をかたくなに守り続けるために、日本を仮想敵国にして反日教育を続けざるを得ない共産党中国とは違うのである。「革命無罪」と称して、未だに約束を平気で破る破廉恥な共産党国家とは違うことを念頭において、うまい解決を望むへなおじさんでありました。
|
 ロシアの入国にあたってはビザ(査証)が必要である。 ロシアの入国にあたってはビザ(査証)が必要である。
留学や就労する場合は、大半の国で査証が必要であるが、最近は短期の観光では不要とする国が多い。へなおじさんも、多くの国に観光旅行しているが、事前にビザを取得した記憶はない(というか、一般的にビザが必要なイスラム圏とかアフリカ諸国などは意識的に避けてきた)。
今回のロシア旅行にあたっては、英語で印刷された査証の申請書に署名し、写真とパスポートの現物を添えて旅行会社宛て1ヶ月以上前に送付し、ビザを取得することが必要であった。
パスポートにビザが貼られて返却されるのは旅行の直前であるので、ロシア旅行前1ヶ月間は、他の国に旅行することは不可能である。
しかもこのビザ、入国日、出国日が印字されているので、予定された飛行機が飛ばないとか、天候の異変で日程を変更せざるを得ないとなると、大問題になるというしろものである。
しかも、移動手段や、宿泊ホテル、旅行日程などもロシア当局に事前に申請されているので、ロシアでは自由に旅程を変更したりするような旅行は不可能である。
中国などでもホテルにチェックインする際にパスポートを求められるが、それは単に本人かどうか確認するだけのためであるが、ここロシアでは、ホテルが預かり、飛行機の中で記入した入出国カードにホテル名を記入するだけでなく、当局に対して宿泊者の情報を連絡してビザ通りの旅行をしているか、チェックしているとのことである。
ロシアを出国するにあたってもパスポート、パスポートに糊付けされたビザ、ホテルなどが情報を加えた出国カードと、本人の人相をじっくり点検チェックしているので、とにかく時間がかかって大変である。もちろん荷物の検査も厳しく、靴まで脱いでチェックされる。
共産党の一党独裁から解放されて自由化されたロシアであるが、今もチェチェン紛争にからむテロ事件など多くの国内紛争を抱えており、観光客に対する厳しい規制は当分続きそうである。
|
 クロアチアなどのマイナーな観光地のツアーでは、たとえばプリトヴィッツエ国立公園などの景色を見て、地元のガイドさんが、「私は知りませんが、ここは、中国の黄龍とか九寨溝、あるいはトルコのパムッカレなどと似ているなどと言われます」などと説明すると、大半のツアー客が、「うん、確かに似ているな」とうなずいた。
クロアチアなどのマイナーな観光地のツアーでは、たとえばプリトヴィッツエ国立公園などの景色を見て、地元のガイドさんが、「私は知りませんが、ここは、中国の黄龍とか九寨溝、あるいはトルコのパムッカレなどと似ているなどと言われます」などと説明すると、大半のツアー客が、「うん、確かに似ているな」とうなずいた。
つまり、クロアチア旅行に参加するお客さん、既に世界の典型的な世界遺産は旅行済み、旅慣れたお客さんたちなのだ。
ここロシア、面倒なビザも必要だし、昔の共産圏、なんだか危なっかしいような印象もあるし、チェチェンなどの国内紛争、グルジアなどとの対立など、治安にも不安材料を抱えているため、ここを旅行する人たちは、世界をいろいろ見尽くしたし、かといって、ロシアを見ずには死ねないしと、残された数少ない観光国のなかからロシアを選んだ人たちが多いのではと思いこんでいた。
 ところが、今回のツアーのお客さん、今年は1年に7回の海外旅行に行きますという元気印の茶色帽子のおばあちゃんを除くと、海外旅行初心者が大半であることが徐々に判明してくる。
ところが、今回のツアーのお客さん、今年は1年に7回の海外旅行に行きますという元気印の茶色帽子のおばあちゃんを除くと、海外旅行初心者が大半であることが徐々に判明してくる。
まずは、行きの飛行機の中、ロシア人のキャビンアテンダントが、入出国カードを配る。記入方法は、地球の歩き方などのガイドブックに詳しいし、旅行会社から配られた観光案内にもちゃんと書いてある。
この入出国カード、ロシア語と英語で交互に書いてある、ミドルネーム爛がある、ロシア側の招待者の爛がある、入国、出国の年月日を、日、月、年の順に記入しなければならないなど、他の国のものとは少し毛色が変わってはいるが、旅慣れた人なら、上記のガイドブックをみれば十分に書けるはずであるが、入国時点で書いてませんという老夫婦が出現した。
また、観光の途中で、トイレ休憩をかねて土産物屋さんに行くと、土産物に殺到、予定時刻を過ぎてもレジに長蛇の列という状態。ロシアなど、ことさら購入しなければならないような土産物はないし、どうしても必要ならネットなどで別に買えばすむわけで、あえて、重い荷物を抱えて移動しなければならないと、旅慣れた人なら思うハズであるのだが、とにかくすごい購買意欲なのである。
また、リタイヤ間もないというご夫婦、真新しい5年パスポートを持っておられる。5年パスポートしか取れない未成年者ならわかるが、熟年夫婦で5年パスポートは珍しい。何度も行くので査証欄が満杯になるほど行きますというならOKだが、日本の出入国で無人化ゲートを利用すれば、イモトアヤコでも10年モノで足りるはず。よくわからない。
また、添乗員に、スーツケースは20キロまでです、2〜3キロオーバーまでは大目に見てくれる場合もありますが、窓口に行ってみないとわかりません。オーバーしたらその場でスーツケースを開けて、手荷物にすればOKです、などと常識的な説明をされても、「1キロでも超えてはいけませんか」「4キロオーバーではどうですか」「超えたらどうすればいいのですか」などと、バスの前方に陣取った中年オバサンたちが、何度もしつこく聞いている。
つまり、このロシアツアーにご参加の皆さん、海外初心者の方が大半なのだ。ヨーロッパ初めてですという、参加者中、唯一の、きれいな若いOL2人組など、ロシアは海外旅行初心者を引きつける魅力にあふれる国なのだという、意外な事実に気がつきました。
|
ロシアではルーブルという通貨を使用する。1ルーブルが約3円、さて、いくら持っていくか?
今回のツアー、パンフレットを見ると、お食事のとき、皆さんにミネラルウォーターと、コーヒーまたは紅茶を無料でサービスと書いてある。
アルコールを飲まないへなおじさん夫婦、食事の際の飲みもの代が不要となると、土産を買うお金だけである。
ロシア土産というと、ウォッカ、キャビアやイクラ、それにマトリョーシカや琥珀。アルコールであるウォッカはまず除外。
キャビアは、アムール川やカスピ海に住む淡水魚のチョウザメの卵であるが、ソ連が崩壊し、旧ソ連邦を構成していた各国が独立、カスピ海に面するアゼルバイジャン、トルクメニスタン、カザフスタンそれにイランなどで乱獲がはじまり、チョウザメが激減、ワシントン条約の対象になってしまった。従って今はイラン産か、養殖モノ、あるいは、人工的に似せて作ったニセモノである。
イクラは?、ロシアでは魚卵のことを一般にイクラという。従ってサケの卵だけではなくて、タラコやカズノコもイクラであるが、サケの卵は極東産が大半、今回行くヨーロッパのロシアまでは輸送が大変で高級品である。
 マトリョーシカ、これはもともとがロシアの木地師が作ったオリジナルという説、日露戦争で愛媛県で捕らえられていた捕虜の方が、愛媛特産の姫ダルマを真似たという説、あるいは、ロシア正教会から箱根に派遣された牧師さんが、箱根の入れ子人形を真似て作ったという説などがある。
マトリョーシカ、これはもともとがロシアの木地師が作ったオリジナルという説、日露戦争で愛媛県で捕らえられていた捕虜の方が、愛媛特産の姫ダルマを真似たという説、あるいは、ロシア正教会から箱根に派遣された牧師さんが、箱根の入れ子人形を真似て作ったという説などがある。
1900年のパリ万博でこのマトリョーシカが賞を得ているので、その後に起きた日露戦争愛媛捕虜説は消えて、箱根説とロシアオリジナル説が残るが、箱根説が有力である。
可愛いロシア娘の顔のモノや、メドベージェフ、プーチン、ゴルビー、スターリンなど、歴代の為政者が現れてくるものなど、いろいろあるが、土産にしても喜ぶ家族や親戚、友人はいない。
琥珀は、今もロシアで大量に産出されるらしいが、これも虫が入っているような貴重なモノは大半がプラスチック製か、少量の琥珀にプラスチックを繋いだまがい物。
ということで、1500ルーブル、約4500円を両替しただけでロシアに入る。
トイレで10ルーブルずつ取られるが、枕ゼニなどはドルの方が喜ばれるということで、旅行中、その1500ルーブルはほとんど減っていかない。
3日目、履いていった靴が水漏れする。よく見ると、履き慣れた靴だが、しばらく使ってないものであったためか、底が劣化して穴が開いているのだ。ということで、靴屋さんに行ってロシア製の靴を購入。これはカードで買ってしまって、やはりルーブルが減らない。
 ということで、スーパーでチョコレート、イクラの缶詰、キャビアなどを購入することに。ホテルに戻ってチョコを食べると、まぎれもなくロシア製だが、ベルギー製のような美味しさは全く感じられない。イクラはタラコかもしれないし、キャビアは、紀伊国屋なら1万円は確実にしそうな量で、約200円は安すぎて、どう考えてもニセモノ。
ということで、スーパーでチョコレート、イクラの缶詰、キャビアなどを購入することに。ホテルに戻ってチョコを食べると、まぎれもなくロシア製だが、ベルギー製のような美味しさは全く感じられない。イクラはタラコかもしれないし、キャビアは、紀伊国屋なら1万円は確実にしそうな量で、約200円は安すぎて、どう考えてもニセモノ。
12月にロシアに行く友人にこのルーブルを残して、通貨そのものを土産にしようと決めた途端に、大型スーパー併設のファストフード店で、美味しそうなクレープを焼いている。思わず注文すると、カードも外貨もダメ、ルーブルしか受け付けないということで、結局最後まで残ったルーブルは30ルーブルほど。友人には約100円分、トイレなら3回分のルーブルをお土産にすることになりました。
なお、マトリョーシカの写真は楽天ショップものを借用させていただいております。
|
添乗員は大変な仕事である。タダで、お給料までもらって、世界中を旅できるから、いいななどと思うが、30人を超えるようなお客さん、現地のガイドさん、バスの運転手などを統率し、スケジュールに沿って安全、円滑に旅を進め、しかもお客さんに喜んでもらわなければならない。
参加するお客さんもいろいろで、集合時刻にいつも遅れる人、大切な話を聞いてない人、日頃の鬱憤をガイドにぶつけてくる人、添乗員に頼りきりで、自由時間などでも添乗員から離れない人などがある。そんな人たちにも愛想をふりまきながら、しかも肝心のところではビシッとけじめをつけなければならない。
特に乗るべき飛行機が飛ばないとか、バスが故障したとか、ホテルの部屋の水がでないなどのハプニングは旅行にはつきもので、そんな異常事態に上手く対応する能力も求められる。
特に点呼は最も大切な仕事で、一人でも置いてきてしまうと、致命傷になる。行方不明になると捜しようがない。韓国の現地添乗員の旅で、朝飯が外でという日、ホテルに一人置いてきてしまい、ホテルに連絡してタクシーで遅刻客を送り届けてもらったこと、
入れ歯を部屋の洗面台に忘れた客がいて、これもホテルに頼んでタクシーでバスを追いかけてもらったことなど、旅のエピソードは尽きない。
中国の奥地へのツアー、添乗の可愛いお嬢さん、中国語はペラペラだが、自分の大切なカバンは忘れるは、点呼のしかたがぎこちないわで、どうもスムーズにことが運ばない、「添乗ははじめてかい?」と聞くと、「いいえ」と答えていたが、結局旅の最後に、「北京の大学に留学していましたが、添乗ははじめて、だから、この地に来るのも初めてです」とこっそり教えてくれた。その子はいまや中国通のベテラン添乗員として、その旅行会社のパンフレットに写真入りで載っている。
また、最初から「添乗員になりたてで、今日がデビューです」と公言する初々しいお兄さん、とにかくやること、なすことダサい子が添乗したときのこと。一生懸命が空回り、そんなときには、ましおばさんの出番となる。「あなた、この子のスーツケース運びなさい」とへなおじさんに添乗員の大きなスーツケースを運ばせ、添乗員には「あなた、きちんと人数数えて、一番最後からついてきなさい」などと指示している。
どんな添乗員に巡り逢えるのか、ツアー旅行の楽しみのひとつである。
|
阪急のトラピクスブランドでは、人気添乗員の添乗ツアーなどというのを売りにしている。
旅行会社も競争は激しくて、大量のダイレクトメールなどを送ってくるが、そんな中に「人気添乗員のA(人の名前)の旅行に、過去に参加いただいたあなたに、Aが添乗するチュニジア旅行をオススメ」などというのもある。
へなおじさんは、スケジュール優先でツアーを選ぶので、人気添乗員添乗ツアーだから選んだということはないのだが、人気添乗員にたまたま遭遇することはあるのである。
確かにAさん、人気添乗員だけあって、とにかく気配りがすごい。30人を超えるお客さんの顔と名前をすぐに一致させて、集合時刻には、誰がいないということまでわかっている様子である。食事時もお客さんの食事の様子を観察している、ホテルに着くと、ありそうなトラブルをあらかじめ説明しておいて、お客さんに部屋に入ったら真っ先にこことここをチェックして下さい、と指示、数分後からそれぞれの客室を回って、確認している。
とにかく、客の身になって、トラブルになりそうなことを、事前に防ぎながら、上手に説明し、しかも防ぐことのできないトラブル対処も見事、しかもお客にストレスを感じさせず、さりげなくこなしているのである。
人気添乗員とパンフレットに書いてなくても、大半の添乗員はAさんと紙一重、すばらしい方ばかりに行き当たった。
ところが今回のロシア旅行、何か変である。客同士でトラブルになりがちな、バスの座席の割り振りもしないのである。
また、ましおばさんが到着したばかりのホテルのロビーでネックウォーマーを落とした。鍵が配られ、解散というときに、誰かが見つけて添乗員に渡し、「これどなたかお忘れ物ですよ」と示した。ましおばさん、まさか自分が落とすことはないと思ったので、そのまま確認せずに部屋に戻り、「あれ、私のかも」、ということになった。
翌朝、ホテルのロビーで集合時に添乗員に「昨夜のネックウォーマーは?」と聞くと、「椅子に置いておきました」という信じられない回答。一晩保管して、あらためて全員が揃ったところで全員に確認し、それでも誰のものか判らなければ、ホテルのフロントに届けるのが普通の対処方法。そうでなくても、客が言ってきたら、フロントに駆けつけて、忘れ物が届けられてないか確認するのが次善の対処方法である。ところが、何もしない。
へなおじさんがフロントに行って確認すると、忘れ物のネックウォーマーがでてきたのでOKであったが、英語が話せない他のお客さんなら、あきらめるところであった。
また、帰りの飛行機、マニュアル通り全員の座席番号を書き留め、席が並んでいるかチェックしたあとで、搭乗すると、通路側の4人席で、ペアが両脇に分かれている。それをペアの方が添乗員をつかまえて指摘すると、「アエロフロートは、気を利かせてペアをこういう配置にするのです」と、信じられない答え。ロシアのアエロフロートだから、aisle
seatと頼めば、気を利かせすぎて、確かに二人とも通路側になるので100%うそではないかもしれないが、「先ほど説明しました」と、これは明かな添乗員の失言。
ましおばさん、自分のことではないのに「そんな大事なこと、聞いてません」と大声で両側に分かれてしまったペアの方を応援している。ペアの方も「聞いてません」と、堪忍袋の緒が切れた様子。間に挟まった外国客との席を替わってもらう交渉もせずに、さっさと自分の席にもどってしまった。
まあ、こういう変な添乗員にあたってしまうのも、旅のエピソードのひとつと割り切れる我が夫婦のようなら問題ないが、旅慣れてない他のお客さん(今回は特に多かった)にとっては、旅の楽しみが何割も削減される旅行ではなかったかと心配している。
「旅の楽しみは添乗員しだい」と書いてある旅行パンフレットもある。
|
 今回のロシア旅行、利用するのはエアロフロート・ロシア航空である。 今回のロシア旅行、利用するのはエアロフロート・ロシア航空である。
言わずとしれたロシアのフラッグ・キャリア、世界最大の航空会社である。
旧共産圏の国営航空の過去をもつためか、あるいは我々になじみが薄いのか、イリューシンやツポレフなどの、ソ連製の航空機には、乗ったことがないせいなのか、何だか危ない感じがして今まで避けてきたような気もする。
今回我々を運んだのは、ロシア製ではなくて、EUがアメリカのボーイング社に対抗し、フランス、ドイツの工業力で立ち上げたエアバス社製のA319−200、A321,A330−300であった。
イリューシンやツポレフでなくて、正直ホッとしたが、世界で最初に人類を宇宙に運んだ工業国の飛行機、良かったなどというと、ロシア当局に叱られるかもしれないが、最近はエアバスやボーイング社から、新型機をどんどん買い入れているという。
フライトアテンダントのお嬢さん達はいずれも働き者で、きびきびと良くお客さんの面倒を見ている。足を投げ出して休憩ばかりしている、経営危機のイタリアの某国営航空会社とは大違い。そういえば、そのイタリアの某航空会社の飛行機は、国際線でも車内のテレビが半数は故障し、多くの椅子がリクライニングできない、リクライニングしたままなどのように故障していたのと大違い、すべての人が最新映画やゲームを楽しんでいた。
エアロフロートは、着陸すると拍手が起きるのよ!と過去にロシアを旅した友人が言っていた。それほど操縦が粗く、上手く着陸することが下手という意味にとらえていた。今回成田からモスクワのシェレメチェボ空港に、強風下、着陸した際、拍手がおこり、やっぱりそうかと思ったが、こんな強い風の中、実に上手く着陸したという賞賛の拍手で、以後搭乗した3回の飛行では、いずれも実にスムーズに着陸したが拍手はなかった。
エアロフロート・ロシア航空は、着陸すると拍手が起きるというのは、都市伝説であったことが判明したのである。空軍上がりのパイロットが多いせいもあるが、皆操縦は実に上手というのが真実らしい。
エール・フランスや大韓航空、KLMオランダ航空、デルタ航空などとスカイチームを結成している。従ってへなおじさんが提出したのはデルタ航空のマイレージカードである。JALやANAのカードが使えないのは残念であるが、またサイパンや、アメリカなどに行くときに、このマイレージを利用させていただこう。
なお、写真はサンクトペテルブルグ空港に駐機するエアロフロートのエアバス。例の添乗員が、「ここで飛行機を撮影したりすると、捕まりますよ」などと搭乗直前に言う前に撮影した映像である。どこにも撮影禁止の表示はなく、中国や、キューバの空港でもあるまいし、撮影禁止などというのも怪しいぞ?本当に撮影禁止なら、もっと早く言えよ!!
|
とにかくこのブログ、回りくどくてなかなか旅が始まらない。
24時間オープンの羽田が国際線を再開し、ヨーロッパ便も飛ばすようになれば様変わりするすることになるが、今は成田発の欧州便、その日の夕方にヨーロッパ各都市に到着することになる。
今回も昼に飛んですぐブランチ、到着2時間ほど前に夕食がでて、現地時刻午後5時過ぎにモスクワ空港に到着、渋滞のモスクワ市内を抜けて、午後8時頃、宿泊するコスモスホテルに到着する。
 このホテル、日本がボイコットしたモスクワオリンピックのときに建てられたというから、築30年、大きなホテルである。
このホテル、日本がボイコットしたモスクワオリンピックのときに建てられたというから、築30年、大きなホテルである。
警戒は厳重で、エレベーターの前に眼光鋭いプーチンのような顔をした背広姿のガードマンが24時間待機し、ひとりひとりの宿泊カードをチェックして、無用のものは客室には入れないぞ!と厳しく警戒している。
その横には何故か、「天上人間」という漢字に、カラオケクラブという日本語発祥の英語表記、多分中国人経営の怪しいナイトクラブが店をオープンしている。
 フロントの上には、世界時計、揃うはずの分針がバラついている。いかにもロシアらしいというか、きちんとしているようで、間が抜けている。
フロントの上には、世界時計、揃うはずの分針がバラついている。いかにもロシアらしいというか、きちんとしているようで、間が抜けている。
部屋に入る。温水の配管があって、部屋は猛烈な暑さ、窓を開けると外はみぞれまじりで極寒、調節する弁などはない。いったいどうしたらよいのか?
シャワーの水圧が高くて調整が難しい、風呂の栓は水が漏れる。いつものことだからあまり目くじらをたててはいけない。
おもむろに、持参した湯沸かしでお湯をわかし、これも持参した粉末みそ汁を溶かして、成田で購入したおにぎりを食べる。これはヨーロッパ旅行の際の我が家の定番である。成田から飛んで最終の機内食が午後の3時頃、だから、ヨーロッパ1日目は腹が減るのである。
日本時間では勿論深夜を過ぎている。しかしここで眠って目覚めれば2日目には時差が解消されている。成田発のヨーロッパ旅行は、そういう意味では楽である。
|
 まずは、池の横でバスが停まる。はい、見学ですよというガイドさんの声にみんな降りて池のほとりを散策する。 まずは、池の横でバスが停まる。はい、見学ですよというガイドさんの声にみんな降りて池のほとりを散策する。
ここ何よ?クレムリンまでの時間調整?というましおばさん。ガイドさんの話を聞くと、向こうに見えるのはノヴォデヴィチ修道院、金色のタマネギ坊主をいただくのが、修道院内にあるスモレンスキー聖堂という。
この修道院、クレムリンの出城としての役割も担い、厳重な城壁に囲まれている。16世紀、モスクワ川を渡って攻めてきたタタール軍をここで防いだり、聖堂は、ムソルグスキーの歌劇で有名な、ボリス・ゴドノフが皇帝に選ばれた場所でもあるという。ソ連の時代には博物館になっていたが、新生ロシアになってからは、女子修道院として復活、敬虔な祈りが捧げられている。
由緒正しき聖地であるが、ましおばさんが言うように、クレムリン入場までの時間稼ぎの散策らしい。
池越しに見ているわけであるが、モスクワで池ならぬ湖といえば、白鳥の湖、こじつけではなくて、この池、ほとりを散策しながらチャイコフスキーが、白鳥の湖の着想を練った場所であるという。白鳥はいないが、カモが泳いでいる。
いきなりトイレ休憩のお土産物屋さんに連れて行かれると、皆さん猛烈にお買い物。ここで、今回のお客さん達、海外旅行の素人さんが多いことがわかる。
 クレムリンの横、赤の広場に到着する。共産党が支配したソ連の時代、メーデーの日や、11月7日の革命記念日には、ミサイルや戦車がここを行進し、クレムリンの城壁の上には、ソ連の首脳部、当時ソ連の支配下、影響下にあった東欧の首脳、キューバのカストロ、北朝鮮の金日成などが謁見していたあの広場である。
クレムリンの横、赤の広場に到着する。共産党が支配したソ連の時代、メーデーの日や、11月7日の革命記念日には、ミサイルや戦車がここを行進し、クレムリンの城壁の上には、ソ連の首脳部、当時ソ連の支配下、影響下にあった東欧の首脳、キューバのカストロ、北朝鮮の金日成などが謁見していたあの広場である。
ロシアが民主化され、東西の冷戦が終結、鉄のカーテンの外から、ようやくここに来ることができたのだと、感慨ひとしお。
軍隊が行進していたところは、北京の天安門前のような、広い道路かと思っていたが、車両は通行止めの広場の一部で、そんなに広くもない広場であることが現地に来て実感。
赤の広場(クラースナヤ・ブローシャチ)は共産党の赤ではない。今のロシア語ではクラースナヤは赤という意味であるが、古代スラブ語では「美しい」。「美しい広場」というのが本来の意味なのだ。
|
 赤の広場のすぐ横、クレムリンの城壁の外側に、ディズニーランドのテーマパークのような、一見下品とも見える派手派手の寺院が見える。
赤の広場のすぐ横、クレムリンの城壁の外側に、ディズニーランドのテーマパークのような、一見下品とも見える派手派手の寺院が見える。
これぞまさしく、いかにもロシアらしい寺院というか、タマネギ坊主を9個もいただく、高さ46メートルもある聖ワシリー大聖堂で、ロシア正教会のれっきとした寺院であり、ユネスコの世界遺産でもある。
極彩色のタマネギ坊主は、それぞれデザインや配色が異なっているが、それぞれが、ひとつづつ、教会になっている。
この大聖堂、イヴァン4世(雷帝)が、イスラム勢力であるカザン・ハーンを退け、その記念に建てたものである。
あまりにきれいに仕上がったために、二度とこんな立派な建築をしないよう、設計者のポストニクとパルマの二人の技術者の眼をくりぬいてしまったという話がある。いかにも雷帝らしい逸話である。
内部の写真撮影には入場時に100ルーブル(300円)の撮影料が必要で、なぜかそれをケチってしまったへなおじさん、中に入って悔やむことになる。
ロシア正教の教会は、板に描いたテンペラ画、壁面に漆喰を塗ってから描かれたフレスコ画のイコン、イコンの祭壇であるイコノスタシスが有名であるが、ここはイコンとしては珍しいフレスコ画がよく残っている。16世紀に描かれたものもあって、必見である。内部は工事中というか、イコンを塗り直していたり、階段がそれぞれの段が非常に高く、登りにくく、降りにくい構造になっている。祈祷する信者の方も、年をとると大変である。
|
「先の遺恨(いこん)覚えたるか」は播州赤穂の殿様が松の廊下で叫んだセリフである。
ロシア正教のイコンは、遺恨ではなくて、キリストやマリア、その他の聖人、あるいはキリスト教にまつわるエピソードを描いた絵画をいう。
 これはサンクトペテルブルクの聖イサク寺院にあったイコン、板にテンペラ画で描かれている。最後の晩餐を描いたものであり、信者の方にとっても非常に分かりやすくキリスト教の教義を教える際に参考になる。
これはサンクトペテルブルクの聖イサク寺院にあったイコン、板にテンペラ画で描かれている。最後の晩餐を描いたものであり、信者の方にとっても非常に分かりやすくキリスト教の教義を教える際に参考になる。
カソリックやプロテスタントの寺院では、テンペラ画で描かれたイコンは少数であり、大理石、石灰岩の彫像、粘土の塑像に彩色したものなど、立体的なものが多いが、ロシア正教ではイコンが主流であるという。
イコンが平板、2次元のみかというと、そうではない。イコンのキリスト像、これは聖人中の聖人であるから頭に天使の輪があるが、その輪の部分が立体的に造られ、金箔を貼ってピカピカにし、平面のテンペラ画の上に置いているものもある。むしろイコンの絵が消えてしまって、金ピカの輪だけ残った遺物もロシアの博物館には展示されている。
このイコン、英語ではicon、そうコンピュータのデスクトップにあるアイコンと同義である。キリスト教の中身を分かりやすく絵にしたものと、ソフトやデータの中身を絵として表象したもの・・・・うーーーん、これが同じとは・・・・深い!。
|
 赤の広場に面して、クレムリンの城壁の反対側に、どこかの宮殿、あるいは博物館のような大きくて立派な建物がある。
赤の広場に面して、クレムリンの城壁の反対側に、どこかの宮殿、あるいは博物館のような大きくて立派な建物がある。
これがグム百貨店、モスクワ最大のデパートである。
グムは国立百貨店というロシア語の頭文字を並べて命名されたと言われても、キリル文字だからよくわからない。
キリル文字は、フランス人だかイギリス人が、冗談交じりにNとかRとかを鏡文字にしてバカなロシア人に教えたら、それを真に受けた、などと聞いたことがあるが、もちろんこれはウソ、ロシア人相手にこんなこと言ったら、怒られる。α、β、γではじまるギリシャ文字から派生した、英語のアルファベットとは兄弟、あるいはイトコにあたる文字である。ロシアでは、交通標識もロシア語だけで、英語の併記がないから、自ら運転してどこかに行こうと思ったら、少なくともこのキリル文字を読めるようにしなければならない。
1893年に建てられた工場を1921年にレーニンの命で百貨店に改装、更に戦後、大改装されたものというが、ソ連時代は庶民の生活に必要な日用品を売る市場であった。自由化された今は、グッチ、エルメス、ヴィトン、コーチなどの超有名ブランドが軒を並べている。食料品スーパーもあるというので見に行ったが、紀伊国屋とか、芦屋のいかりスーパーの品揃えから、更に値段の高いものだけ厳選したようなものばかり。
例の添乗員、「皆さんには用のない高級百貨店です」などとまたまた失言をして「失礼ね!」などとお客さんから叱られていたが、少なくともへなおじさん夫婦には縁遠い百貨店である。
でも添乗員は、我々がどうして貧乏団体とわかったか?成田、モスクワ便はビジネス路線でもある。ビジネスを展開するエグゼクティブの往復が多く、ビジネスクラスの座席数が多い。そんな中、我々30数人ご一行様は全員エコノミークラス、だれもビジネスクラスには乗らなかったのである。ツアー料金の飛行機、ホテル、食事、バス、ガイド代すべて込みの20万円程に、更に20数万円をプラスして支払えばビジネスクラスの座席に座ることができる。ワインも飲み放題だし、食事も豪華、また椅子もフラットにできて特に帰りの機内一泊には超楽チン。でもへなおじさん、ビジネス料金を支払うなら、また別のツアーに参加すると、あくまでも小市民である。
ビジネス座席、満席であったが、あまり垢抜けない服装の、最近あぶく銭を手にしたか、金持ちの親のスネをかじっているというような感じの若い中国人が大半、それに、いかにも富豪そうな少数のロシア人。日本のじじばば連合は、狭いエコノミー座席で、自ら持参したスリッパに履き替え、エコノミー症候群にならないように自ら運動したりして、頑張っているのである。かつて、我が国の経済を支えてきた我々じじばば連合は、お金を合理的に使うよう教えられた賢者である。貧乏人などと気軽に呼ぶな。でも、へなおじさんは、どう見ても、いかにも貧乏人である。ロシアにはいないが、中国などに多い物乞いも、決して寄ってこないのである。
|
海外旅行中といえども、いろいろな情報を入手したい。今回のようなツアー旅行ならまだしも、自由旅行などをしていると、インターネット情報の入手は必須といえる。
へなおじさんの現役時代の10数年前、長年勤続ご苦労さんということで会社から与えられたロンドン、パリ、ローマへの旅行では、小さなパソコン、各国の電話モジュラージャックに合うアダプタ、局線のプラスマイナスを変更するアダプタなどを持参して、日本との間のメールなどをしていたが、飛行機に乗るたびに持ち物チェックにひっかかり、しかもプロバイダにもなかなか繋がらず、繋がっても結構多額の通信費を取られたりして大変であった。
その後は、パソコン持参をやめて、どの国の街角にもあるインターネットカフェとか、ホテルのビジネスセンターなどにあるパソコンで通信することにしていた。
しかし海外での利用は、通信速度がきわめて遅いとか、英語圏以外ではキーボードの字がその国の文字になっていたりとか、@マークなどが出しにくかったりとか、日本語フォントが画面に出せてもキーボードで打てないとか、いろいろ不便があった。
最近はホテルなどで有線あるいは無線LANの設備が整えられ、持参するPCも小型になり、日本から持参する機器で楽にインターネットが可能になった。
また、日本で使っている携帯電話を持参しても、そのままメールや通話、web閲覧ができるようになり、便利になってきた。
もちろん無料というわけにはいかない。日本で定額制で使っていても、海外では別料金、家族間のメールも、海外では結構なお金がかかってくる。
最近は添乗員も日本から持参した携帯電話を持っていて、現地のアテンド会社やガイド、運転手などとの連絡に使用している。従って、添乗員の携帯番号を聞いておくのは絶対に必要である。
万一、海外の街角で皆とはぐれても、添乗員に電話をすればOKである。但し、通話は日本を経由するので高額である。日本経由だから電話は、+81のあとに0を省略して架けなければならない。090−1234−5678なら、+81−90−1234−5678である。(途中の−は不要)
+(プラス)は、携帯電話の機種によっても異なるが、数字の「0」を長押しすれば出る機種が大半、覚えておくと便利である。しかし行方不明になってしまうような人は、こういうことにも無頓着あるいは、無知で、このブログの愛読者の方は、そもそも迷子にはならない人たちである。
|
クレムリン入場前に昼食、ということで、今回の旅行はじめてのレストランへ。
 今回の旅行で判明したロシア料理の特徴は、前菜が出て、スープ、メイン、甘いスイーツというコース料理であることは、他のヨーロッパ諸国の旅行と変わらず。ロシアの家庭でもこういうコース料理的なメニューが、日常的に食されているのかとか、ツアー会社がレストランに、日本人ツアー客には、コース料理を出すようにと注文しているからなのか、調査不十分で不明。
今回の旅行で判明したロシア料理の特徴は、前菜が出て、スープ、メイン、甘いスイーツというコース料理であることは、他のヨーロッパ諸国の旅行と変わらず。ロシアの家庭でもこういうコース料理的なメニューが、日常的に食されているのかとか、ツアー会社がレストランに、日本人ツアー客には、コース料理を出すようにと注文しているからなのか、調査不十分で不明。
パンは、コストコで売っているフランスパンのようなものは美味しかったが、概してあまり美味しくない。特にライ麦の黒くて酸っぱいパンは、少なくともへなおじさんの口には、合わない。
ロシア料理は、素朴で、美味であるが、今回の旅行でも、出された料理は、香辛料などもクセのあるものはなく、いずれも美味しくいただけた。
富山から参加したというご夫婦、彼らも現役時代は転勤族で、名古屋勤務時代、美味しいロシア料理の店に行ったという話がでて、へなおじさん、ましおばさんが名古屋在住時代、行った店と同じであることが判明した。そこで食べたロシア料理は、赤いトマトベースのスープ「ボルシチ」、肉の詰まった揚げパン「ピロシキ」、それに、ジャムを入れた紅茶が思い出されるが、今回ロシアに来て判明したのは、
ボルシチの赤はトマトではなくて、赤カブ(ビート)の赤。柑橘類の酸で赤くなる岐阜県は高山の赤カブではなくて、もともと赤いカブで、北海道で栽培されている甜菜の赤いヤツと考えればスープの甘さも納得できる。(へなおじさんが、いつも娘に作っているトマトベースの野菜キノコたっぷりスープの方が美味い?)
ピロシキは、揚げパンではなくて、揚げてなくても肉の詰まったパンはピロシキというとのこと。むしろ日本のような揚げたピロシキはロシアでは少数派というから、オドロキ。(揚げた日本のピロシキの方が美味い)
また、紅茶(チャイ)は、中国からイギリス経由でここロシアをはじめ、中東のイスラム圏でも広く飲まれているが、ジャムを入れるのがロシア風というのは誤りで、普通はミルクとか、レモンなどに砂糖を少し多めに入れて、ガラスの器で飲まれているとのこと。(いちごジャムを入れた名古屋のロシアンティーは美味かった)
富山のご夫婦と、あの名古屋の体験は、何だったのでしょうねと、話が盛り上がる。やはり現地に来ないと、真実は見えてこないものである。
|
 厳重な持ち物チェックを経て、写真の中央の茶色の入り口(ボロヴィツカヤ塔)からクレムリンの城壁内に入る。クレムリンは、城壁に囲まれているので、お城というイメージを持っていたが、内部は大統領の執務室、かつての王宮、武器庫などの他に、ロシア正教の総本山として、多くの正教会の教会がそびえ、まさにロシアの政治、軍事、宗教の大切なものが詰まっている複合施設と考えた方が良さそうである。
厳重な持ち物チェックを経て、写真の中央の茶色の入り口(ボロヴィツカヤ塔)からクレムリンの城壁内に入る。クレムリンは、城壁に囲まれているので、お城というイメージを持っていたが、内部は大統領の執務室、かつての王宮、武器庫などの他に、ロシア正教の総本山として、多くの正教会の教会がそびえ、まさにロシアの政治、軍事、宗教の大切なものが詰まっている複合施設と考えた方が良さそうである。
ますは写真の右側にある武器庫に入場する。
この武器庫、19世紀の半ばに武器の製造、保管を目的に建造された建物であり、武器庫という名称もそこからきているが、ニコライ1世の命で博物館に改装され、ロシア帝国の戦利品、ロシアの工芸品、外国からの贈り物など、ロシアの宝物がこれでもかと展示されている。
まだ自動車がない頃に造られた実際にエカテリーナ2世などが乗っていた馬車が展示されていて、どうやって馬と繋いでいたのかとか、どうやって転回していたのだろうかと、身を乗り出して構造を探っていたへなおじさん、何度も赤外線アラームが鳴ってましおばさんに、叱られてばかり。
この中のロマノ夫王朝に関する宝物は、かつて池袋の東武美術館で展示されたものがあり、再会を果たした御物もあった(ような気がする)。
武器庫の展示では、ロシア人が「タタールのくびき」と呼ばれるモンゴル人に支配された時代を恥と思っていること。エカテリーナ2世は、ましおばさんより、はるかにデブであったことなどがわかったが、
レーニンによる社会主義革命の時代を経ても、労働者、農民の敵として抹殺したロシア王朝が、長年にわたって貯蔵した多くの宝物を、時の政権が、きちんと保管、管理して今に至ったことに感激した。ヒトラー率いるナチスドイツなどがロシアを爆撃した際も、疎開したり、地下に隠したりして守ったとのことであり、多くの宝物が蒋介石によって台湾に運び去られ、残った少数の貴重な品も、毛沢東による権力闘争たる文化大革命で破壊し尽くした中国とは、一線を画している。
|
武器庫のおびただしい展示物を見ると、ロシア人が「恥」と感じているのは13世紀から16世紀までの二百数十年続いたタタールのくびきと呼ばれる異民族による支配であることがわかる。
タタールというのは、中国でいえば「韃靼(だったん)」、すなわちモンゴル人、チンギスハーン、あるいはその子孫による侵略である。遊牧民だから羊とか馬の生の挽肉のタルタルステーキを食べるし、マヨネーズにピクルスを刻んだようなタルタルソースをかける。実際に彼らがそういう食物を食していたかは不明であるが、そういう少しモンゴルっぽい食物を、タルタルと呼んだ。タルタルはもちろんタタールである。
モンゴル人が日本に攻めてきたとき(いわゆる元寇)は朝鮮半島の高麗人を先兵とした。西に向かってロシアを攻めたときは、カザフスタンとかトルクメニスタンとか、何とかスタンという名のつく地区の遊牧民を主体とする異民族を先兵として攻めてきた。
日本と違って海がないので、容易に攻められてモンゴル民族の支配下に組み入れられてしまったのである。
モンゴルの支配は巧みであり、少数の代官を置いて多くのロシア人を支配し、税金を取り立てた。少しでも背けばモンゴルから大量の軍隊が来て、容赦なく住民を皆殺しにした。元横綱朝青龍の何事にも屈しない性格を思い出せばわかるように、目的のための手段は過酷を極めた。だから逆らえなかったのである。
モンゴル帝国の後を継いだキプチャク・ハーン国の支配を逃れ、タタールのくびきから脱したのは16世紀に入ってから、イワン3世(大帝)の時代になってからである。
ロシアは広大で、多くの異民族が住んでいる。タタールのくびきの元凶であるモンゴル人や、彼らの先兵として攻めてきた多くの異民族も、特にソ連の時代は居住区をソ連邦に併合し、今もロシア人としてロシア領内に暮らしている人々も多い。ロシア正教を信じるスラブ系のロシア人だけがロシア人ではないのである。
従って、「恥」というなら、日本との条約を一方的に破って瀕死の状態の日本を攻め、有史以来の日本の領土である北方4島を国際ルールに反してまでも不法に占拠し、今も占領し続けている無法ぶりの方が大恥である。
更に我が国の北方領土を勝手に視察し、鳩山(あの愚かなハトのおじいさんの一郎さん)、フルシチョフとの間の日ソ共同宣言という約束も反故にしようとするメドベージェフの言動の方が「恥」である。こら、プーチンや、メドベージェフ、聞いているか!
|
 どの国の国旗も、その国にはためいていると誇らしげである。特にロシアは、ソ連崩壊後、元のロシア帝国時代の白青赤の三色旗に戻したわけで、どうだ、伝統のある三色旗だぞと誇らしげに風にはためいている。
どの国の国旗も、その国にはためいていると誇らしげである。特にロシアは、ソ連崩壊後、元のロシア帝国時代の白青赤の三色旗に戻したわけで、どうだ、伝統のある三色旗だぞと誇らしげに風にはためいている。
もともと、造船などを学んだオランダの三色旗を参考にしたとか、起源については諸説あるようである。当時のロシアは後進国で、皇帝が幼い頃からドイツに留学していたとか、ヨーロッパ先進国から王妃を迎えたとか、いろいろな理由でロシア語がしゃべれない皇帝も多く、先進国の国旗を真似たという説がもっともらしいが、モスクワを治めていた王家のシンボルであったという説が有力である。
 ソ連時代はいうまでもなく横長の赤地に星、農民と労働者のシンボルの槌と鎌の旗である。 ソ連時代はいうまでもなく横長の赤地に星、農民と労働者のシンボルの槌と鎌の旗である。
この赤旗がはためいている間は、上空を通過すれば撃墜されるし、鉄のカーテンで囲われた内部は、うかがい知ることもできなかった。
武器庫を出ると隣にクレムリン大会宮殿がある。この大宮殿、クレムリン内では最も新しく、1961年に建造された建物である。周囲の景観ともマッチするようにと設計されたらしいが、巨大で立派すぎて浮いている。ソ連時代は共産党の党大会や中央委員会の会議場として使用され、新生ロシアになってからは国際会議やバレー、オペラの劇場としても使われているとのこと。それにしても客席数6000は、デカすぎである。
 宮殿の中央上部には、ロシアの国章が金色に輝いている。 宮殿の中央上部には、ロシアの国章が金色に輝いている。
この国章、ハプスブルク家と同様、双頭の鷲である。あれ?ロシア王室はハプスブルク家と関係あるのかな?調べてみると、もともと双頭の鷲は神聖ローマ帝国のシンボルマークである。
モスクワ大公イヴァン3世、あのタタールのくびきからロシアを解放したイヴァン大帝の2番目の妃が、東ローマ帝国の皇女、以来、ロシアは、神聖ローマ帝国の正統な流れをくむということをアピールするために使い始めたのである。
ロシアはハプスブルク家とは関係がないが、神聖ローマ帝国の正統な後継者であることをアピールするという、目的が同じであったのだ。
ハプスブルク家の双頭の鷲同様、中央に王冠をいただいている。この王冠、いうまでもなく主権と専政のシンボルである。民主国家ロシアのシンボルとして復活させる際には、少しデザインを変えるとか、何か工夫すれば良かったような気がするが、プーチンがこれを国章とするようサインした。ロシアはまだイギリスやフランスのような完全な民主体制にはなっていない。プーチンが一方的に財閥を解体してエネルギー会社を国有化するなど、メドベージェフを傀儡として王権ともいえる権力を一手に握っているのだ。
ハプスブルク家の双頭の鷲と違うのは中央に龍を退治する騎士像があること、この騎士は聖ゲオルギウスである。英語ではジョージ、ドイツ語でゲオルグ、キリスト教の聖人である。トルコのカッパドキアで生まれたとされる農民や旅人の守り神とされる聖人で、旅人へなおじさんの守り神でもある。
龍は中国皇帝のシンボルでもある。尖閣問題を契機に、メドベージェフが胡錦濤と手を結んでいる。ロシアの守護聖人、聖ゲオルギウス同様、メドベージェフも中国皇帝たる胡錦濤を、早く民主化せよ、情報統制するな、反日教育などするなと、「退治」しなければならないのである。
|
鉄のカーテンを破り捨て、東西冷戦を終結させた功労者はゴルバチョフである。
彼が推し進めたペレストロイカ(改革)と、グラスノスチ(情報公開)は、ソ連の国民に、ソ連は世界の後進国であること、ソ連政府は、世界の標準的な国家と比べてみても、奇妙な政策を展開していることなどを悟らせ、民主化推進のキッカケになった。
共産党書記長というソ連の最高権力者にまで上り詰めたミハエル・ゴルバチョフ、精力的に世界を飛び回り冷戦を終結させ、ペレストロイカ、グラスノスチを進めた。改革の過程でソ連の最初にして最後の大統領になったが、結局はソ連の改革半ばで失脚、肝心のロシア国内での人気は今ひとつである。
ところが世界では人気者、世界平和に貢献したとしてノーベル平和賞も受賞している。日本でも人気者で日大や明治大の名誉博士にもなっており、先日もニュースをわかりやすく解説してくれる池上さんのインタビューにも答えていた。
中国は、20年前のゴルバチョフ出現前のソ連よりひどい非民主国家である。webの中から政府に都合の悪いサイトを消去し、更に徹底的なアクセス制限をして国民の知る権利を侵害している、マスコミ規制もして都合の悪い報道は一切しないようにするどころか、事実を歪曲して伝えている。世界標準から見ても、いかにエゴイスティックで、奇妙な政府であるか、中国共産党が、日本の軍部と闘って勝利した誇らしげな存在ではないことがわかっては、一党独裁の中国共産党には都合が悪いのである。反日教育の中身が、いかに誇張されて、事実とはほど遠いものか、国民にわかっては都合が悪いのである。
ゴルビーさん、中国に行って講演してくれませんか。ソ連共産党は権力を失ってしまいましたが、ロシア国民は幸せになりましたと、貧富の格差が激しく、大部分の人が貧困にあえいでいる中国国民に、先人としての知恵を教えてあげてくださいな。
|
 クレムリンの内部はロシア正教の多くの寺院が目白押し。金色に輝くたくさんのタマネギ坊主が燦然と輝いている。 クレムリンの内部はロシア正教の多くの寺院が目白押し。金色に輝くたくさんのタマネギ坊主が燦然と輝いている。
寺院が異なると、その上に輝くタマネギ坊主も、微妙に形が異なっている。
形だけではなくて、タマネギ坊主の上にある十字架の形も違っている。シンプルな十字架、三方が膨らんでいるもの、フリルで十字架そのものが装飾されているもの、見ているだけで楽しい。
シンプルな十字架は、皇帝の個人的な礼拝堂であったブラゴヴェシチェンスキー聖堂のようだ。
 いっぱいフリルの付いた十字架は、リザパラジェーニヤ教会、この教会、少し小さめであるが、タマネギ坊主の数では他の教会に負けていない。
いっぱいフリルの付いた十字架は、リザパラジェーニヤ教会、この教会、少し小さめであるが、タマネギ坊主の数では他の教会に負けていない。
我々は、かつてのロシア国教会の総本山、ウスペンスキー大聖堂に入場する。
ガイドさんに言われるまでもなく、教会内部に入場する際は男子は脱帽がマナー。ガイドさんに言われても脱帽しないハゲのおっちゃんがいて、添乗員に叱られている。ヨーロッパ旅行は、どの街に行っても広場があり、マーケットがあり、広場の前に教会がある。毎日、教会見物があるから、脱帽は自然に身に付いてしまう。女性は脱帽しなくてもOK。
 このウスペンスキー大聖堂、ロシア皇帝が戴冠式を行い、葬儀に付された由緒ある寺院だけあって、威厳がある。 このウスペンスキー大聖堂、ロシア皇帝が戴冠式を行い、葬儀に付された由緒ある寺院だけあって、威厳がある。
大聖堂の外部にもイコンとフレスコ画があるが、内部はイコンで埋め尽くされている。12世紀というから今から900年ほど前の聖ゲオルギー像、少し時代が下る聖三位一体像が有名である。
祭壇を背にして右に双頭の鷲をいただく皇后の椅子、左にイワン雷帝の玉座がある。
見上げると堂内を照らす巨大なシャンデリアがある。ナポレオン軍から奪い返した300キロの金と、5トンの銀で造られたといわれてだけあって、巨大すぎて落ちてこないかと心配になるほど。ほの暗く輝いて、教会の壁という壁を埋め尽くす、多くのイコンを照らしている。ヨーロッパの多くの教会を見てきたが、ロシアの教会は、タマネギ坊主の外部だけでなく、内部の装飾も独特で面白い。
|
 クレムリンの内部はとにかく広い。城壁に囲まれているが、あまりに広大であるため、風も吹き抜けて寒い。 クレムリンの内部はとにかく広い。城壁に囲まれているが、あまりに広大であるため、風も吹き抜けて寒い。
写真はイヴァン大帝(雷帝)の鐘楼である。雷帝の命でイタリアの建築家が1500年代の初頭に建設、50年ほどを経て、八面体の鐘楼が付け加えられた。
鐘楼の高さは81メートル。雷帝の治世、これがモスクワで一番高い建物であった。これより高い建物を建てることを許さず、と彼がお触れをだしていたというのが理由らしい。
ナポレオンがモスクワを侵略、退却の際にこの鐘楼の鐘の爆破を命じたが、24個ある鐘のうち、18個は破壊を免れたという。
ソ連になってからは教会としての機能が停止されてしまったが、ソ連崩壊後に教会として復活した。
 その横に、超巨大な鐘がある。しかも一部が欠けている。 その横に、超巨大な鐘がある。しかも一部が欠けている。
まさか、横にあるイヴァン雷帝の鐘楼に架けようとした鐘か?それにしては大きすぎである。
この鐘、「鐘の皇帝」と呼ばれているもので、1733年から1735年にかけて、親子2代の技師により18世紀のロシアの建造技術の粋を集めて造られたが、鋳造中に火災が発生、あわて者の弟子が消火しようと水をかけたために脆くも割れてしまい現在に至るという。高さ6m、重さ200t、欠けた部分の重さだけでも11t、完成すれば世界最大の鐘であるが、残念ながら未完成である、というか、完成したらどんな音色を奏でたかと、コンピュータでシミュレーションをしたら、たいした音ではなかった由で、今後も未完の鐘である。ロマノフ王朝の皇帝が鐘の表面に描かれてはいるが、とにかく鐘が肉厚すぎて金属を使いすぎ、だから重すぎて、クレーンがない当時の技術では、小さな鐘楼にすら揚げることも無理、建造技術を誇るのはいいが、建造してからどうするという肝心の点が欠落、いかにもロシアらしいというか、間が抜けている。
 少し歩くと、こんどは「大砲の皇帝」と呼ばれている超巨大な大砲がある。1586年製、ブロンズでできた口径89cm、重量40tの大砲である。
少し歩くと、こんどは「大砲の皇帝」と呼ばれている超巨大な大砲がある。1586年製、ブロンズでできた口径89cm、重量40tの大砲である。
日露戦争で、日本が旅順港を砲撃した際に使用した大砲はもっと大きいので、おどろくべき大きさとは言えないかもしれないが、16世紀当時とすれば大きすぎ、しかも、当時は砲弾にも火薬を詰めて、着弾時にも爆破させるという技術は知られておらず、写真の大砲の下にあるような鉛の丸い玉を発射するように設計された。この大砲、一度も発射されたことはないというが、1tもある玉を発射できたかどうか、疑わしい。
こういう無用の長物のような鐘とか大砲を見ていると、ロシアの工業力に疑問がわいてくる。でもこれらは日本でいえば戦国時代とか江戸時代の技術、やっぱりすごいか。
|
 雪のちらつくモスクワ、郊外にある常設劇場に、ボリショイサーカスを見学に行く。 雪のちらつくモスクワ、郊外にある常設劇場に、ボリショイサーカスを見学に行く。
ボリショイサーカス、日本でも有名で、1958年というから、まだソ連の時代の昭和33年に初来日して以来、毎年日本のどこかで公演している。
ただ、このボリショイサーカス、ロシアの政府に所属する公団のような大組織で、8000人を超えるメンバーを抱え、常設の劇場も100以上と、実に巨大、海外に公演旅行に出る際は、どのグループも、偉大なというロシア語の形容詞、ボリショイを冠した「ボリショイサーカス」を名乗るそうで、今回見物した、モスクワではニューサーカスと呼ばれている組織が日本やアメリカに遠征して公演しているわけではなさそうである。
日本では、名門の矢野サーカスが廃業、キグレサーカスもつい先日公演を中止したという中、ロシアではこの大サーカス団が、国内はもちろん世界公演を続けているし、中国でも雑伎団と呼ぶサーカスが上海や北京で奮闘している。
そんなことを考えながら、眠い眼をこすりながらショーを見物する。まずはヒグマが直立してカートを押して登場する。ぬいぐるみを人間が着ているのかと思わせるほど、良く訓練されていて、観客もびっくり。
アシカ、犬などの動物ショーが充実していている。引田天功を彷彿とさせるイリュージョンも大仕掛けで、びっくり仰天。サーカスの花、空中ブランコも高さがあってスリル満点、更に数頭の牡のライオンがたてがみをなびかせ、野生の泣き声をあげながら、今にも人間に襲いかからんばかりのショーは圧巻で、ハラハラドキドキである。
海外旅行の夜のショーは、へなおじさんの寝る時間と重なるので、いつもパスしていたが、今回ばかりはツアー料金に含まれていたし、参加して正解でありました。サーカスは面白い。東京ディズニーリゾートにできた常設劇場で海外のシルクドソレイユがZEDという公演をしているというが、帰国したら、それも一度見に行こう。
|
 首都モスクワの北東に、ウラジーミル、スーズダリ、ヤロスラヴリ、セルギエフ・ポサートなどの古都が点在している。
首都モスクワの北東に、ウラジーミル、スーズダリ、ヤロスラヴリ、セルギエフ・ポサートなどの古都が点在している。
それらをモスクワも含めてつなぐと、丸い輪のようになることから、黄金の環と呼ばれている。いずれも12世紀あるいは13世紀から続く伝統のある街であり、かつてはモスクワと覇権を争ったこともある古都である。
朝まだ暗いモスクワを8時に出発、途中1回のトイレ休憩をはさみ、古都ウラジーミルに到着したのは12時過ぎ。まずは、道路の真ん中に車の走行を邪魔するように建つ城門を見学する。これは、黄金の門、ウラジーミルを取り囲んでいた城壁の中に入るための、12世紀に建てられた城門である。中世から残るのはこの黄金の門だけという。
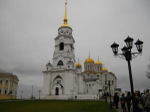 近くのレストランで昼食後、バスで少しだけ移動、ウスペンスキー大聖堂を見学する。1158年に神聖ローマ帝国から派遣された職人も参画して着工、14世紀の初めまではロシア大聖堂の最高位にあった由緒のある教会で、5つの黄金のタマネギ坊主をいただく威風堂々とした様式は、その後のロシアの教会建築の模範になったという。
近くのレストランで昼食後、バスで少しだけ移動、ウスペンスキー大聖堂を見学する。1158年に神聖ローマ帝国から派遣された職人も参画して着工、14世紀の初めまではロシア大聖堂の最高位にあった由緒のある教会で、5つの黄金のタマネギ坊主をいただく威風堂々とした様式は、その後のロシアの教会建築の模範になったという。
昨日のクレムリンの教会群からのタマネギ坊主は食傷気味のへなおじさん、ガイドさんの説明も上の空、まったく贅沢なツアー客である。
少し歩いてこんどはドミトリエフスキー聖堂へ。
 こじんまりした白い教会であるが、外壁一面に施されたレリーフは見事で、聖人、歴史上の英雄、動植物などが、石灰石を使って豊かなイメージで表現されている。
こじんまりした白い教会であるが、外壁一面に施されたレリーフは見事で、聖人、歴史上の英雄、動植物などが、石灰石を使って豊かなイメージで表現されている。
12世紀末のロマネスク様式の建築物であるが、この石灰石を使った装飾は「石の詩」とか「石のカーペット」と呼ばれている。
旧約聖書のダビデ王の他、アレキサンダー大王、ソロモン王、ヘラクレス、それに建築を命じた公爵自身も息子を抱いてちゃっかりレリーフに収まっている。
寒風の吹きすさぶ高台からからは、スーズダリの街並みが一望できる。シベリヤ鉄道の駅や線路、火力発電所なども霞んでいる。足下の水たまりは凍っている。雪こそ降っていないが氷点下の寒さである。
|
 中世の雰囲気を残すロシアの田舎町を見たかったら、スーズダリに行きなさいとガイドブックに書いてある。 中世の雰囲気を残すロシアの田舎町を見たかったら、スーズダリに行きなさいとガイドブックに書いてある。
ということで、ウラジーミルから40分ほどバスに乗ってスーズダリに到着する。
真っ赤な実を付けたナナカマドの木が延々と続いている。ナナカマドは、7回かまどにくべても、燃えないというところから付いた名前、日本のナナカマドは、秋になると葉っぱが赤く色づいてきれいであるが、ここロシアのナナカマドは、葉っぱはもちろん、むしろ実の赤色が際だっている。
ガイドさんによれば、酢漬けにしたり、酒に入れたり、ジャムにして食用にしているという。試しに実を取ってかじってみる。「苦!!!」とても食用とは思われないが、加工すると美味しくいただけるとのこと。
このスーズダリ、街並み保存のルールがあって、木造の平屋建て、石造りの1階に木造の2階を継ぎ足した2階建て、石造りの2階建ての3種類の家屋しか建てられないとのことで、中世の雰囲気が残り、映画の撮影にも使われているとのこと。
 城壁が取り囲み、要塞のような堅固な砦という感のあるスパソ・エフフィミエフ修道院を見学してカーメンカ川という小川のほとりにある木造建築博物館の中に入る。
城壁が取り囲み、要塞のような堅固な砦という感のあるスパソ・エフフィミエフ修道院を見学してカーメンカ川という小川のほとりにある木造建築博物館の中に入る。
まだ行ったことはないが、ルーマニアの世界遺産の教会のような、すべて木造の教会が地味に建っている。
中にはテンペラ画のイコンが並んだイコノスタシスがあって、いかにも素朴なキリスト信仰の雰囲気を醸し出している。
木の風車、木の水車と木枠の井戸など、木造の博物館という名前にふさわしい構造物がある。
 それから木の小橋を渡ってクレムリンの中に入る。クレムリンは、城塞という意味のロシア語。最も有名なのはモスクワの権力の中枢のクレムリンであるが、ここスーズダリのクレムリンの城壁の中は、宗教施設である。
それから木の小橋を渡ってクレムリンの中に入る。クレムリンは、城塞という意味のロシア語。最も有名なのはモスクワの権力の中枢のクレムリンであるが、ここスーズダリのクレムリンの城壁の中は、宗教施設である。
星が描かれた鮮やかなブルーのタマネギ坊主をいただくのは、スーズダリに現存する最も古い教会、ラジェストヴェンスキー聖堂である。
ここから今晩のホテルまではわずか15分、部屋にはバスタブも電話もない。しかも断水でシャワーの水も出ない。持参したミネラルウォーターを沸かしてホットココアを作る。海外の旅ではこのホットココアが実に美味い。待つこと30分でシャワーの水が復活。
電話がないので明日の朝は「モーニングノック」とのこと。幸い部屋は暖かい、夕食後は早く寝てしまおう。
|
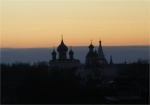 スーズダリを朝8時に出発、緯度が高いので8時はまだ真っ暗だ。 スーズダリを朝8時に出発、緯度が高いので8時はまだ真っ暗だ。
太陽が地平線を赤く照らし始めると、そこにタマネギ坊主の教会の屋根がシルエットに浮かんで、実に美しい。
「朝焼けは雨」のことわざは、ロシアでも正解のようで、途中で雪が降り始めた。バスの窓ガラスが曇ってきた。
確かこのバス、ノーマルタイヤを履いている。大丈夫か?
 まもなくシベリア鉄道の線路を横切ります。とガイドさんの声、日本以外では踏切で一旦停止しないので、慌ててカメラを取りだし、バスの車窓からパチリ。
まもなくシベリア鉄道の線路を横切ります。とガイドさんの声、日本以外では踏切で一旦停止しないので、慌ててカメラを取りだし、バスの車窓からパチリ。
広軌の線路が一直線に延びている。これぞ、モスクワと極東のウラジオストックを結ぶ全長9000キロを超える世界一の長距離鉄道、シベリア鉄道である。
1891年、同盟を結んでいたフランスの技術を借りて着工、1904年、日露戦争中にようやく完成した。ヨーロッパ主流の標準軌ではなく、広軌を採用、ナポレオンのような侵略者がヨーロッパから攻めてきては一大事と、敢えて広軌を採用したという。
線路はモンゴルのウランバートルを経由して北京にも繋がっているし、更には平壌にも通じており、飛行機の嫌いな独裁者、金正日が、シベリア鉄道を経由してモスクワを表敬訪問したこともある。
古くは日本人女性2人の名前が思い出される。
一人目は俳優の岡田嘉子、日中戦争のさなか、共産主義者で演出家の杉本良吉と樺太の国境を越えてソ連に入り、モスクワを目指すが、ソ連軍につかまり杉本は処刑、嘉子は、極東の刑務所に入れられる。後に念願のシベリア鉄道でモスクワに送られて、隠遁生活に入ることになる。モスクワで、これが岡田嘉子が住んでいたマンションですと、ガイドさんが説明していたが、岡田嘉子を知っているのは、へなおじさんより前の世代の人である。
二人目は与謝野晶子、あの「君死にたまふことなかれ」の、与謝野晶子である。フランスにいた夫の与謝野鉄幹に合いに行くために、シベリア鉄道を経由してパリに渡っている。ヨーロッパ各国に4ヶ月ほど滞在して帰りはマルセイユから船で帰国したが、その間の出来事を夫鉄幹との共著で、「巴里より」として発表している。ましおばさんに、俺がパリにいたら、シベリア鉄道で来るか?と聞くと、バカじゃないの?と相手にしてもらえない。設問自体に無理がありました。
ソ連崩壊でウラジオストックが外国人にも開放されたので、晶子同様我々もシベリア鉄道に乗車可能である。但し、ビザの制限があるので(このブログで前述)、実際にはかなりハードルは高い
|
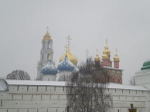 途中から雪がひどくなってくる。ソ連の時代にはザゴールスクと呼ばれていた街、セルギエフ・ポサードに到着する。
途中から雪がひどくなってくる。ソ連の時代にはザゴールスクと呼ばれていた街、セルギエフ・ポサードに到着する。
バスを降り、雪の積もる道を歩いてトロイツェ・セルギエフ大修道院の見えるレストランに入る。昼食は、グリーンピースとジャガイモのサラダ、ピロシキ、スープに、豚とジャガイモの壷煮、デザートはアイスクリームと豪華。ロシアはミルクが美味いので、アイスクリームも美味いとガイドブックに書いてあるが、その通りに美味い。
地下道を通って大修道院に入る。実に立派な大修道院である。この修道院を築いたのは聖セルギウス。宗教的尊敬を集めるとともに、台頭して支配力を強めていたモンゴルに対抗するためにモスクワの諸侯のまとめ役としても活躍、彼の祝福を受けたロシア軍がモンゴル軍を破るとともに、その後も奇蹟を起こし、ロシアの守護聖人になった人物である。
大修道院の中央は、レストランからも見えたウスペンスキー大聖堂、モスクワのクレムリンにあった同じ名前の大聖堂同様、立派な聖堂である。
この大聖堂の北側には、雨ざらしになった、皇帝ボリス・ゴドノフの墓所があるという。ロシアを混乱に招いた皇帝ということで、雨ざらしにされている。
一方でトロイツキー聖堂の中には、聖セルギエフの棺が安置されていて、熱心な信者が賛美歌が流れる中、次々と棺に歩み寄り、キスをしている。雨ざらしのボリス・ゴドノフとは待遇の違いが歴然としていて少し恐ろしい。
聖堂には幻のイコン画家として著名なアンドレイ・ルブリョフの描いたイコンなど、多くのイコンがあって壮観である。
モスクワのシェレメチェヴォ空港に到着、今まで誠心誠意尽くしてくれた真面目なガイドさんとお別れし、サンクト・ペテルブルクに向かうことになる。
|
 モスクワのシェレメチェボ国際空港、国内便というのにセキュリティチェックは極めて厳しく、靴まで脱いで調べられ、入場するのに1時間半もかかる。国内でもチェチェンなどの紛争を抱えており、しかも大統領が北方領土を訪問したということで日本人には厳しくしているのか、良くわからないが、とにかく厳重である。
モスクワのシェレメチェボ国際空港、国内便というのにセキュリティチェックは極めて厳しく、靴まで脱いで調べられ、入場するのに1時間半もかかる。国内でもチェチェンなどの紛争を抱えており、しかも大統領が北方領土を訪問したということで日本人には厳しくしているのか、良くわからないが、とにかく厳重である。
液体類はチェックで没収されたので、待合室でジュースとペプシを購入、サンドイッチなどを食べようか迷ったが、サンクトペテルブルグ到着後に夕食のレストランに行くので、買わずにガマンする。
1時間20分のフライトなので、まさかと思っていたが、水平飛行にはいるとサンドイッチの軽食がサーブされる。これは、おなかが空いていたので完食してしまう。20時35分の定刻にサンクトペテルブルグ着、モスクワより更に緯度が高いので、勿論真っ暗。夕食も完食してしまい、少し食べ過ぎ。
 大きなホテルに到着、今日から3連泊、明日朝は遅いので、少しだけ洗濯。 大きなホテルに到着、今日から3連泊、明日朝は遅いので、少しだけ洗濯。
部屋の窓からサンクトペテルブルグの街並みが見える。ここサンクトペテルブルグはかつてのロシア帝国の首都である。このホテルから少し走れば、中世の建物が建ち並び、しかも旧市街は高さ制限がなされているので、美しい街並みが保存されていて、ヨーロッパの窓としての雰囲気が残されているという。
といっても、ピョートル大帝がここに来るまではバルト海のフィンランド湾に面した沼地であった。
1703年、ピョートルはここに運河を堀り、沼を埋め立て、港と要塞を築き、陸地を造りあげる。ピョートルはロシア皇帝なのになぜかドイツ語しかしゃべれない。自分の名前はピョートル、守護聖人は聖ペテロ、ドイツ語読みでサンクト・ペテロ、サンクトペテルブルクというドイツ語読みの地名を付けて首都にする。
ピョートルの死、ロマノフ王朝の栄光と盛衰、ロシア革命、民主革命を経て、この都は、ペテログラード(ロシア語でペテロの地)、レニングラード(レーニンの地)と改名され、再び元のサンクトペテルブルグに戻る。
ロシアの栄枯盛衰がよくわかり、美しく保存された古都サンクトペテルブルグ、明日からの観光が楽しみだ。
|
 本日は9時の出発、朝時間があるのでホテルから5分ほどの24時間スーパーに行ってみる。 本日は9時の出発、朝時間があるのでホテルから5分ほどの24時間スーパーに行ってみる。
こんな都会の一等地にあるスーパーでも物価は安く、日本なら1万円は軽く超えそうなキャビアが65ルーブルと、200円以下の価格、あまり安いので、ニセモノかもしれないが、とにかく安い。
約27キロほど離れた郊外の、プーシキンという街に到着する。
日本の迎賓館のようなゲートの前には、各国からの観光客が並んでいる。我々は、予約してあるので、並ばずに入場、並んでいる皆さん、お先にスミマセン!
 おーーっ、フランスのベルサイユ宮殿、ウィーンのシェーンブルン宮殿と並び称されるエカテリーナ宮殿が見えてくる。
おーーっ、フランスのベルサイユ宮殿、ウィーンのシェーンブルン宮殿と並び称されるエカテリーナ宮殿が見えてくる。
1724年、ピョートル大帝の妃である女帝エカテリーナ1世のために建設されたので、宮殿は彼女の名前をとってエカテリーナ宮殿と呼ばれるようになる。
その後、女帝エリザベータが大々的にバロック様式に、エカテリーナ2世がクラシック様式で改装、いろいろな様式が混在して、ロシアバロック様式と呼ばれている。外壁の長さは300m、ロマノフ王朝の栄華を象徴する壮大な宮殿である。
北棟の上に、ロシア独特の金色に輝く5つのタマネギ坊主が見える。このドームの下には、礼拝堂があるという。

クロークにコートを預け、宮殿内を見学する。
まばゆいばかりに装飾された巨大な部屋が延々と続いている。それぞれの部屋には名前が付けられ、それぞれ贅が尽くされ、装飾されている。
その中には、再建された有名な琥珀の間がある。世界中の観光客がこの部屋を目当てにロシアに来るというのに、ましおばさん、「部屋中全部が琥珀と思っていたのに、全部じゃないのね」、とがっかりしている。
おいおい、こんな豪華な部屋でがっかりされては、我が家で一番広い8畳の間はどうなるのよ!
|
 ましおばさんがガッカリしたという琥珀の間。部屋中全部ではないが、部屋の大部分が琥珀で装飾されている。 ましおばさんがガッカリしたという琥珀の間。部屋中全部ではないが、部屋の大部分が琥珀で装飾されている。
琥珀は松ヤニなどの植物樹脂の化石である。その希少性から宝石として珍重されている。色が微妙に異なるので、その天然の色の違いを利用して模様が描かれており、その美しさと、これを造った職人の細工の繊細さには目を見張るものがある。
もともとこの琥珀の間、ドイツ、プロイセンのフリードリッヒ1世が、ロシアで採れた琥珀を使って部屋の一面を装飾したことに始まる。
王は部屋の完成を見ずに亡くなったが、息子は全く興味を示さず、たまたまプロイセンを訪れたピョートル1世にこの壁面をプレゼントする。
それをエリザベータが命じて冬用の別荘の部屋の装飾に使い、後にエカテリーナ宮殿に移築される。
エカテリーナ宮殿の琥珀の間は壁面が大きい。エカテリーナ2世が琥珀に、鏡、宝石、ガラスのモザイク、金メッキ装飾などを加えて装飾、徐々に琥珀細工に置き換えられて琥珀の間は完成していく。
そこで第2次世界大戦である。ナチスドイツはエカテリーナ宮殿にも現れ、琥珀の間は分解されて、そっくり持ち出されてしまう。
その後の琥珀の間がどうなったのか、捜索が進められているが、火災で焼失したのか、船ごと沈んでしまったのか、今も不明である。
一方でロシア政府は、1980年代から失われた琥珀の間の再建作業を、乏しい資料をもとに開始した。職人達の努力の結果、2003年、サンクトペテルブルグ建都300周年の年、その優雅な姿をエカテリーナ宮殿に再び現した。それが今目の前にある琥珀の間なのである。どうだ、ましおばさん、まいったか。
|
 エカテリーナ宮殿で思い出す日本人はといえば、大黒屋光太夫である。 エカテリーナ宮殿で思い出す日本人はといえば、大黒屋光太夫である。
井上靖の小説を映画にした「おろしや国酔夢譚」で、緒方拳が演じた男である。
1751年、伊勢の国(三重県)は白子で生まれる。白子は、伊勢型紙の生産地、徳川家康が本能寺の変で信長が死んだことを堺で聞き、伊賀を越えてたどりついたのがこの白子である。ここの浜から伊勢湾を渡って岡崎に帰り着いた。「これ、越後屋、お前もアコギじゃのう」と悪代官のセリフの阿漕(あこぎ)ケ浦もこの近くである。
話が白子から思わぬ方向に脱線したが、とにかく大黒屋光太夫は、白子から江戸に荷物を運ぶ回船の船頭である。シケで船が難破、北に大きく流されてカムチャツカ半島にまで来てしまう。
そこでラッコなどの毛皮を採取に来ていたロシア人に遭遇、ロシア語を学んでサンクトペテルブルグまでたどり着くのである。
 日本は江戸時代、将軍様の住む江戸のお城といえども、木と土と紙でできている。 日本は江戸時代、将軍様の住む江戸のお城といえども、木と土と紙でできている。
通されたエカテリーナ宮殿の謁見の間は、まばゆいばかりの金ピカの部屋で、キラキラ輝いている。
このときの大黒屋光太夫のオドロキはどんなものだったろうか?
寒いシベリヤを越えてやってきたら、宮殿には暖炉があって実に暖かい。
 向こうからやってきたのは、これまた金ピカのエカテリーナ2世。びっくり仰天するするヒマはない。 向こうからやってきたのは、これまた金ピカのエカテリーナ2世。びっくり仰天するするヒマはない。
とにかく日本に帰りたいと、学んだロシア語でエカテリーナに訴え、許される。
ラクスマンに伴われて根室に帰り着いた光太夫は、折から鎖国中の江戸幕府の取り調べをうける。
光太夫の口述は桂川甫周が「北槎聞略」、「漂民御覧之記」としてまとめ、日本はロシア情勢を知ることになった。光太夫は幕府の禁を犯したので幽閉されたといわれているが、小石川に妻を迎えて住み、伊勢白子にも帰郷したという記録がある。比較的自由に暮らしていた模様である。
大黒屋光太夫は、まさに死ぬか生きるかという大冒険でサンクトペテルブルグにたどり着いている。へなおじさんと、ましおばさん、観光で楽々とこの宮殿に来て、寒いななどと言っている。光太夫さん、誠に申し訳ありません。
|
 サンクトペテルブルクから南西に30キロ、ピョートル大帝の夏の宮殿に到着する。 サンクトペテルブルクから南西に30キロ、ピョートル大帝の夏の宮殿に到着する。
フィンランド湾に面した階段状の地形に目を付けたピョートル大帝、遠くの池から高低差を利用して水を引き、噴水が吹き上がるように設計した庭園を造るのである。
まだ水中ポンプなどの動力装置がない時代、重力、つまりサイホンの原理を利用した噴水である。金沢の兼六園にもサイホンの原理を利用した噴水があるので、ロシアの専売特許ではないのだが、ここの噴水は雄大、なんと、142本の吹き出し口から水が噴出するのである。
 ところが、ところが、残念ながら、噴水は10月で水が止められ、春になるまではお休みとのこと、池は水が枯れ、噴水の楽屋裏が露出してしまっている。
ところが、ところが、残念ながら、噴水は10月で水が止められ、春になるまではお休みとのこと、池は水が枯れ、噴水の楽屋裏が露出してしまっている。
サンクトペテルブルクに観光に来るなら、やはり夏の暑い時期、ツアー料金の跳ね上がる時期に来なければならないのである。
というので、冬のツアーは夏の宮殿の内部の見学、見事な天井画が描かれた多くのきらびやかな部屋を見て回る。
また、この夏の宮殿の広大な敷地には、フランスのベルサイユ宮殿のトリアノンのような隠れ家もあり、市内の有名な美術館と同じ、エルミタージュと呼ばれているとのことである。ここも残念ながら時間切れで訪問不可、バルト海を眺めてため息をつく、へなおじさんでありました。
|
 ピョートル大帝の夏の宮殿、今日は噴水が出ていないが、噴水の向こうにバルト海のフィンランド湾が見えている。フィンランド湾を出てバルト海を南下し、はるかに航海していけば日本に行くことが出来る。
ピョートル大帝の夏の宮殿、今日は噴水が出ていないが、噴水の向こうにバルト海のフィンランド湾が見えている。フィンランド湾を出てバルト海を南下し、はるかに航海していけば日本に行くことが出来る。
ロシアは広大で、海軍はウラジオストックや旅順港の極東艦隊、オデッサなどの黒海艦隊、それに、強敵スエーデンやプロイセンなどに備えるここバルト海の、バルチック艦隊の3方面に展開することが必要であった。
さて日露戦争である。1904年、中国東北部や朝鮮半島の利権を巡ってロシアと日本の軋轢が高まり、旅順港に停泊していた軍艦が日本によって奇襲攻撃を受け沈没、今のインチョン空港がある朝鮮半島の仁川沖でも日本海軍によって戦艦が沈没させられるなど、極東太平洋艦隊は壊滅状態に陥った。
そこでニコライ2世は、ロジェストウェンスキーに極東へのバルチック艦隊派遣を命ずるのである。
オデッサにいる黒海艦隊は、ロンドン条約により黒海の外に出るのは禁じられていて動けない。北極海を通れば最短距離で日本に行き着くことが出来る。最近では地球の温暖化で氷がゆるみ、流氷の間を縫って航海することも検討されているようであるが、当時はそんな危険な航海は夢のまた夢。従って、現在のラトビアのリエバーヤ、当時のリバウ軍港を出発したバルチック艦隊は、南に行かざるをえないのである。
まずは出発したばかりの北海で、イギリスの船舶を日本の待ち伏せと勘違いして砲撃、ただでさえ敵対中のイギリスと事を起こしてしまう。
スエズ運河を通ればはるかに近いが、当時の日本の同盟国イギリスが支配していて通れない。
従ってアフリカを回らなければならないが、イギリスと仲の良かったフランスにも気をつかうと、停泊させてくれる港が極端に限られ、水や食料、それに燃料の石炭の補給もままならない。
長い航海ではフジツボなどを落としてきれいにしないと、船足が極端に落ちるが、それもままならない。何とかフランス領のインドシナ、今のベトナムにたどり着いて、数少ない極東艦隊と合流して日本海をめざすが、結果はご案内の通りである。
NHKの坂の上の雲でもあなじみの秋山兄弟の弟、真之が補佐する東郷平八郎に、これでもかというくらいの歴史的な敗北を喫するのである。
ついにへなおじさん、バルト海にも来てしまったのである。こんなに遠くから日本に向かうのなら、どんなに強大な海軍でも背負うハンデは大き過ぎだなーーー。と、ロジェストウェンスキーが気の毒に思えてくる、へなおじさんでありました。
|
ニコライ2世、ロマノフ王朝最後の皇帝で、日露戦争で敗れたあとロシア革命が勃発、一家もろとも処刑されてしまう。まさに悲劇の皇帝である。
さてこのニコライ、皇太子の時代に日本を訪問している。ロシア艦隊を率い、シベリア鉄道の極東までの線路敷設を視察するために、日本に立ち寄ったのである。
さて大国ロシアの皇太子の訪日である。当時はまだ日露の関係は悪くはなかったが、将来の極東の利権争いの視察に来たのではないかと、庶民レベルでは歓迎一色というわけではなかったが、明治天皇はじめ明治の元勲諸侯は歓迎せざるをえなかった。
西南戦争で死んだはずの西郷隆盛は実はロシアに逃れ、ニコライとともに日本に帰ってくるとのうわさもあった、それを信じた西南戦争の英雄、滋賀県の警察官に採用されていた津田三蔵、西郷が帰ってきてしまってはもらった勲章が台無しと思いこみ、サーベルを抜いてニコライに斬りつけた。これが大津事件である。
さあ一大事、伊藤博文はじめ明治の元勲諸氏、津田の死刑は、政治的にも不可避と、大審院長(今の最高裁判所長官)児島惟謙に死刑判決を出すよう圧力をかける。
どこかで聞いたような話である。大国である中国を刺激しては一大事、我が国の領土、尖閣諸島に入り込み、海上保安庁の船に体当たりしてきた無法者を、法律を無視して釈放せよ。バカだが、権力だけを握っている政治家が圧力をかけた。
ところがこの明治の裁判官は偉かった。我が国の法では、天皇に斬りつければ死刑だが、外国の要人は、皇太子だろうが王様本人だろうが特別な規定はない。天皇の規定を準用して死刑にすることは法律に反することになる、と、政治家の圧力を断固はねのけて、無期懲役としたのである。
今の民主党の誰かさんとは、雲泥の差、とにかく日本は、この時代、いろいろな意味で、すでに世界の標準に達していたのである。日本が再び世界標準から外れたのは、つい最近である。今、世界標準から外れている国は、北朝鮮、中国、イランそれに残念ながら日本なのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
エルミタージュ美術館
 いよいよ今回のツアーのハイライト、エルミタージュ美術館に入場する。エルミタージュ美術館の建物はかつての皇室の宮殿である。
いよいよ今回のツアーのハイライト、エルミタージュ美術館に入場する。エルミタージュ美術館の建物はかつての皇室の宮殿である。
エルミタージュというのは「隠れ家」、とてもでかくて隠れ家とはいえないが、広い宮殿内だからどこにでも隠れることができそうである。
絵画だけでも4000点以上、ヨーロッパからオリエント、インド、中国まで数多くの美術品が収蔵されている。
ルーベンス、ヴェラスケス、エル・グレコ、ゴヤ、レンブラント、セザンヌ、ルノワール、ゴッホ、マチス、ピカソなどなど、誰もが知っている巨匠の絵画が、これでもかと展示してあって、頭が混乱してくる。
まずは、ダビンチの「リッタの聖母」。ダビンチは小品が2点だけ、これと「ベヌアの聖母」である。小さいので見逃してそのまま行ってしまう観光客の方も多い。
 次に外せないのは、ラファエロである。これは「コンスタービレの聖母」、これも絵そのものは小さいが、金ピカの額縁に飾られてガラスケースに収まっている。何気なく展示されているので、これもそのまま行きすぎてしまいそうである。
次に外せないのは、ラファエロである。これは「コンスタービレの聖母」、これも絵そのものは小さいが、金ピカの額縁に飾られてガラスケースに収まっている。何気なく展示されているので、これもそのまま行きすぎてしまいそうである。
ピカソの青の時代や、キュビズムの時代の作品は、相変わらず暗くてあまり好きではないし、マチスなどは、下手で俺でも描けそうなどと言っては、ましおばさんに「無駄な線がないでしょ、デッサン力がないと、描けないのよ、バカもん!」と叱られる。
あまりに収蔵品が多いので、日本語の解説書を300ルーブル、約1000円で購入して美術館の喫茶店に行ってコーヒータイム。
同じように疲れた我々のツアーご一行様も、数組休んでいる。あれ、お金が足りないぞ!どうも、解説書を買うとき、100ルーブル札2枚と500ルーブル札1枚を渡したような気がしてくる。100と500のルーブル札、色や形がそっくりなのだ。1200円くらい損したが、まあ、きれいな解説書だからいいか、などと無理矢理納得していると、ましおばさんに「バカね」とまた叱られる。
 外に出て宮殿広場に出ると、エルミタージュ美術館の向かいに旧参謀本部のアーチ状の建物がある。 外に出て宮殿広場に出ると、エルミタージュ美術館の向かいに旧参謀本部のアーチ状の建物がある。
その中心の凱旋アーチの上には馬車に乗った勝利の女神がいる。ベルリンのブランデンブルク門の上の馬車に似ているような気がしてくる。
これで、ロシア観光のすべてが終了だ。来てよかったな!ロシア。
|
|
|
|
モスクワのドモジェドボ空港の国際線ターミナルで爆発があり、35人の方がお亡くなりになった。
LALの成田からの便が到着した1時間後の爆発で、日本からの客は入国審査などを済ませており、被害は免れたという。ロシア当局はテロには屈しないぞ、テロがあっても、空港の機能は麻痺しないぞ、という姿勢が鮮明で、JAL便は、爆発の1時間後にはモスクワからの新たな客を乗せて成田に向けて出発した。
ロシア情勢は不安定、地下鉄などでのテロもあって、外務省も旅行者に対して注意を呼びかけていたが、その心配が現実になってしまったのである。
今回の爆発はドモジェドボ空港、2ヶ月ほど前、我々のアエロフロート便が発着したのはシェレメチェボ空港で、空港こそ異なるが、同じモスクワの大規模国際空港、まさに間一髪、難を免れたと言って良い。
ロシアは多民族国家である。大半はロシア人であるが、ヨーロッパから極東に至る広大な領土には多くの異民族が住んでいる。宗教もロシア正教が中心であるがムスリムも多数いる。
もともとソ連邦に無理矢理吸収されてしまった、異民族、異宗教の国々は、ソ連邦の崩壊で分離し、再独立を果たしている。
しかし、チェチェン共和国、その周辺のダゲスタンやカルバダ・バルカル共和国など、ロシアの支配下から逃れられなかった地域では、ロシア当局の強権的支配に反発して過激派の動きが活発である。
資源も豊富でロシアは独立させる気などサラサラない。プーチンは強権的な支配者であったが、メドベージェフも大統領選挙をにらんで、同じく強権的な支配を目指している。ロシアは共産党の一党支配を脱したが、必ずしも民主国家ではないのである。
チュニジアの大統領追放で、北アフリカ、アラビア半島、中東のアラブ諸国も、為政者の強権発動に反発する民衆の動きが激化して治安が不安定になってきている。
まあ、タイミング良くロシアとエジプトの旅行を済ませて良かったへなおじさん夫婦、次の旅行先は、普段はあまり見たこともない外務省の情報なども見ながら、よく考えて選ばないといけない。それにしても、外務省の情報は、石橋を叩いても渡らせないぞ、という感じの、あつものに懲りてなますを吹くコメントであるので、まともに読んでいたら日本脱出は無理になってしまう。さあ、どうしよう。
|
 ロシア旅行を終えて、昨日、成田に帰国した。ロシアでは、こんなスタイルで寒さを凌いでいたが、東京はむしろ暑いくらい、車の中では半袖のTシャツ1枚、クーラーをつけて帰宅した。
ロシア旅行を終えて、昨日、成田に帰国した。ロシアでは、こんなスタイルで寒さを凌いでいたが、東京はむしろ暑いくらい、車の中では半袖のTシャツ1枚、クーラーをつけて帰宅した。